2015年01月15日
南信雪山紀行♪ 地獄極楽 前編
2015/01/11
七難
鬼面山
(赤石山脈南部エリア)
全山行 432回

 鬼面山の情報はこちら
鬼面山の情報はこちら
標高 鬼面山 1889.3m(1850mまで到達)
天気 曇り・
曇り・ 雪
雪
山行時間 7時間(休憩時間を含む)
〈コース〉虻川林道・第二駐車場下(8:15)-登山口(8:45)-
トチの木(9:30)-西尾根の稜(10:40-10:50)-展望地(1:00)-
ピストンで林道駐車スペース(3:15)
「鬼」と名のつく山は多々あれど
これほど鬼らしい山はないだろう
それが厳冬期の 鬼面山 だ
伊那山脈の最高峰鬼面山
南信の南アルプスの前に立ちはだかる山だ

この山は谷の奥にあったため 登山や信仰の対象には
ならなかったそうだが 近年 林道・山林作業道の開発で
日帰りの山として登山者が増える傾向にあるそうだ
一般的には国道152号の途中にある
地蔵峠から登るルートが使われる
しかぁ~し
今回 ひとちがは冬季に登るため地蔵峠までの道は
ゲートが閉鎖されているので無理
豊丘村からの虻川林道から攻めることにした
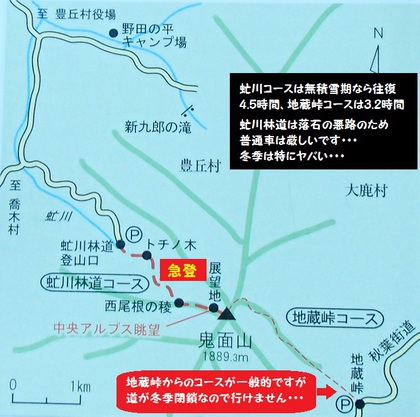
数日前 ちがこさんは豊丘村の役場に電話を入れた
あのー
ヘビ川林道は冬季閉鎖にはなりませんか?
車で駐車場まで行けます?
え゛? ヘビ川林道?
あ゛ー あ゛ー
ヘビ ぢゃなくて アブ ですよ
アブ
初っ端から大恥をかいてしまった
*言い訳ですがガイドブックの文字が小さくて
老眼の ちがこさんには 虻が蛇 に見えたんですわ
まぁ いいです
4WDなら入れますよ
昨年の12月の降雪で雪が残ってますが
それなりの装備を持っていれば大丈夫です
役場の人が自信あり気に言った
そうなんですかー
よかったー
チェーンもシャベルもあるから大丈夫ですね
最後に役場の人が言った
山の雪の状態はわかりませんよ
林道の入口に到着
それまでは民家もあり雪もなくフツーの道路なので
特に問題もなく順調

野田の平キャンプ場方向に向かい
途中を虻川沿いに登山口までの林道を走る
まだキャンプ場の分岐まで行かない道もこの通り

ひどい落石 よけるにも道幅が狭いので
そのまま落石の上をタイヤで通過するしかない
いつ落ちてくるかわからない石を恐れて
ハンドルを握る ひとしさんも緊張気味
ガイドブックに書いてあるじゃないですか
悪路って
え? ごめん読まなかった
上るにつれ 融け残った雪が氷になり
つるつるのスケート場みたいな狭い林道が
標高を上げながら九十九に続いた
それでも うちらの車は無敵だ
ますます落石はひどくなり
座布団級の鋭角の落石でとうとう先に進めなくなった
車から降りて落石を動かそうにも
重すぎてびくともしない
ダメだこりゃ
緊張が続いた運転で疲れ切った
ひとしさんが言った
これ以上は無理ですぅー
林道の安全な広い場所までバックして
歩いて登山口まで行きましょう
ふぁ~い
ツルツルの狭い林道を横滑りしながらバックし
安全な林道脇に駐車完了
第一難所
落石つるつる林道
あ゛―
大変だった

いきなりアイゼン装着の出発と
予想外の展開になったのも致し方ない
さっそく駐車場を通過した先にある登山口まで
つるつる林道を歩き出した
とはいえ ずーっと つるつるってわけでもない
陽当りのいい場所は雪や氷もなく
ゴロゴロと落石のひどい道

林道横の山斜面を見上げてみれば
白くいつ崩れてもおかしくないような岩が
こっちを睨んでいた

くわばら くわばら
なるべく刺激しないように通過
それでも時折ザザーっと崩れるのがコワい
ずんずん進んでいくと山から染み出た水が凍りつき
蛇の歯みたいなツララが何本も垂れ下がっている

これぞヘビ川林道
ぢゃなくて虻川林道

登山口に到着
嬉しいのは進むべき方向に足跡があったこと

ふにゃぁ~ 大丈夫そうだね
足跡もあるし問題なさそうだよ
そうですかね
赤テープもあるみたいだし問題ないかな
まずは虻川を渡る

そこから先は虻川に沿って高巻きの狭い道を
落っこちないように進むわけ

ともかく道幅が狭いのと 半分雪が凍って
滑りやすいのでピッケルを使って
確実に進むしかない危険個所

無積雪期なら問題ないはず
第二難関
高所から川に滑落しそうな道

あ゛―
コワかった

ようやく地に足がつくようなユルい道に変わった

おかげさまで足跡もバッチリなので
道迷いの心配もせずに済んだ
見上げるとこんな空

今日は曇りって言ってたから
展望あんまり期待してなかったけど
もしかするといいかもね
第一ポイント
豊丘村の天然記念物パワースポット

ふたりで幹に手を当て
木の温もりを感じた
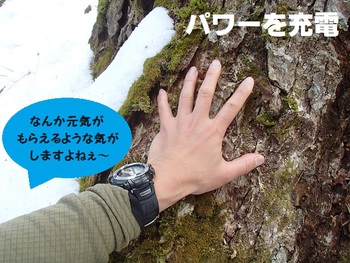
順調に足跡を追い
赤テープを確認しながら進んでいく

最後の渉渡を終えると
そこからは急登の連続
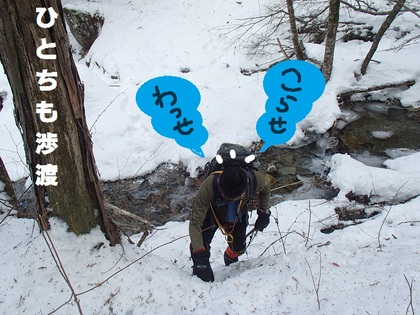
山の急斜のとりつきにポールに
かけられていた数々の謎の品物
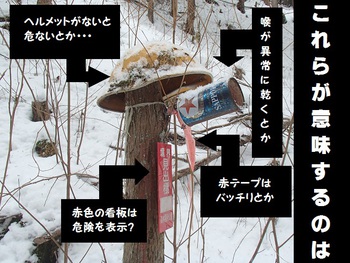
さぁー
登りますよぉ~

出だし雪はくるぶし程で固め
アイゼンを効かせて登れば問題なし
が 雪の下はアイスバーンなので
注意しながら登らなくていけませんな
100mごとに このような立派な看板

いつも使っているストックでは太刀打ちできないので
ピッケルをグサグサ刺しながら登る
標高が上がるにつれ傾斜が増すため
目の前は雪の壁のようだ

時々見えるのといえば

木の根っこが邪魔して登りにくい場所もありーの
つかみたくてもポキポキ折れてしまう木の枝ばかり

頼りにならない物ばかり
這い登っていくしかない

気温が一気に下がったような気がする
天気はやっぱり予報通りの曇り空
風も強く見上げると白い物が・・・

雪が降るなんて言いませんでしたよね
山だから 雪も降るよ
急登を登りきった場所は 第二ポイント
西尾根の稜

ようやく座ることのできる場所
天気が急速に悪くなって寒くなってきたのと
頼りにしていた足跡がこの場所を最後になかったこともあり
ちょっぴり心がクジけた
もう諦めて下山しよーかな
ひとしさんはどう思ってるのかな?
たぶん行きたくないと思ってるよ
そうかな
でもここで敗退するのは納得できないから
もうちょっと がんばってみるね
あー そう

全く足跡のない白い山
コースを確認できるのは ピラピラ風に揺れる
白ちゃけたビニール紐だけ

尾根に沿って登るしかないので
ここで登場 先頭ラッセル員 ひとしさん

急登だけど 後ろにさえ ひっくり返らなけりゃ
大丈夫そうだけど 下山の時は大丈夫かな?
たぶん大変だよ
もうヤメた方がいいよ
うるさいな

第三難関
急登の連続

どこまで登るんだろね?

順調に登ってはきたものの
やはり雪山の急登ラッセルともなると
二倍近く時間がかかるのが悔しい

こんなでピークまで到達できるのかな?
ちゃんと ちがこさん下山のこと考えてるのかな?
もう私は温かい温泉の方がいいんですけど
先頭ラッセル員 ややへたれ

一向に登るのをヤメようとしない ちがこさんに
「もうヤメませんか?」と言えない ひとしさん

ひとちー 言えば
もうヤメようって

ダメですぅー
ちがこさんは自分が納得しないとヤメませんからね
そうだ 納得できることを探せばいいかも

いい案あるの?

まあね まかして下さい
しばらく登っていくと ひとしさんの足が止まった
大きな岩の横からトラバースして尾根上部に出るらしい
まず岩をトラバースする前に 岩まで到達するには
超危険な山斜面を横断しなければいけない

ね いい場所あったでしょ
ホントだね
これで諦めるかな
じーっと危険な山斜面を眺めてギリギリまで進んでみたものの
やはり危険で赤テープ通りに岩を巻くのは不可能だと思った
ぐるりと見上げると 岩方向に移動するのではなく
登りにくいとは思われたが そのまま尾根の急斜を
這い登れば岩をトラバースせずとも尾根上部に
出ることができそうに見えた
こっちから行ってみるよ
え゛ 登るんですか?
うん 私が行ってダメなら諦めるから
そう言うと腰丈まである深さの雪をもろともせず
ちがこさんは ずんずん登っていってしまった

あ゛―
ダメじゃん 作戦失敗
行けるよぉー
ちがこさんが叫ぶ声がした
シブシブと ひとしさんも続く
冬道は簡単に作れるからいいねぇ~
無積雪期じゃ こーはいかないもんね
第四難関
危険な大岩トラバース
こーなったらもう先に進むしかないね
再び急登ラッセル員を任された ひとしさん
必死に登り続ける

もう時間的にピークは無理じゃないかな
なんとかして諦めさせなきゃ
なんとかなりそう?
まぁね 今度こそ
目の前に大岩がある

登るのは大変そうだな
お尻の重い ちがこさんには登れないかも
もしかして諦めるかもね
そんな簡単に行くかな?
ちがこさん意地でも登るよ きっと
予想通り 大岩に向かって
這い登る ちがこさん

無積雪期ならいったいこの場所は
どんな風になっているのかな?
登れたよぉ~っ
シブシブ ひとしさんが後を追う
大丈夫ですか?
登ったら下ることも考えて下さいよ
わかってるしー
第五難関
大岩までの這い登り
さてと 岩まで来たのはいいけど道がない
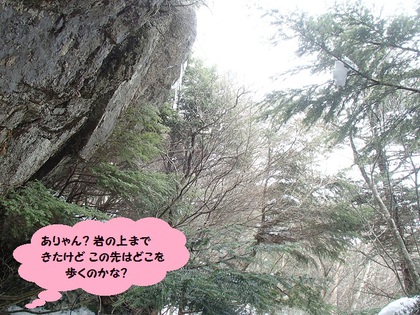
キョロキョロ見回すと
あった あった
岩の横に白ちゃけたビニール紐が
ひょろっぴい木に巻き付いていた

こっちから通過するんだ
まだ行くつもりだよ
いいの? ひとち?
よくないですぅー
岩のコワい斜面を岩にしがみつきながらカニ歩き
更に尾根を登っていくと
目の前に鬼面山のピークが見えた

こーなったら進まないわけがない
気合が入った ちがこさん
ズンズン先頭ラッセル員を始めた

あと ちょっとで山頂だい♪
1800mを示す看板から100mは尾根を
登っただろうか?
イヤなものが目の前にある
またしても大岩

あれまぁ 岩の横はカニ歩きかー
踏み外せばお陀仏だね
ブツブツ言いながら先頭で進んでみた
岩の上部に上がるためには
氷のスベリ台みたいになってる岩の隙間を
なんとか這い登るしかない
げ 無理
カニ歩きして岩の前まで戻ると
ひとしさんに言った
ありゃ 登れん
え゛?
あれほど諦めなかった ちがこさんが
山頂を目の前にして諦めようとするなんて
自分の目で確かめてしたかったのもある
私なら登れるかも ちょっと挑戦してみたい
危ないよ ひとち
ちがこさんが行けない場所はヤメた方がいいよ
ほら 虫倉山の橋の時 もそうだったじゃん
わかってますけど
男なら行ってみたい時もあるんですぅ
ちがこさんとチェンジして今度は
ひとしさんが岩の横をカニ歩きで移動し
岩の隙間のスベリ台を身体を突っ張りながら這い登る
な なんとか登れましたぁ~
でも景色よくありませ~ん

この先はどうなっているのか?
岩の展望地からは樹林帯で簡単にピークを
踏めたかもしれない
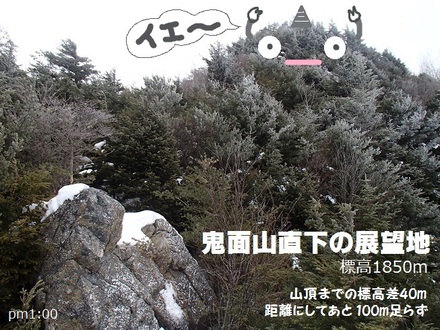
しかぁーし
現実 岩の下でこのような状態で
動けないでいる ちがこさんがいた

やっぱ無理
いいですよ
もうタイムオーバーです
下りましょう
上から声がした
第六難関
大岩の氷のスベリ台
山頂を目前にして下山することに決定
ひとちが下山誘導しなくても
ちがこさん諦めたね
はい 三度目の正直じゃなくて
三度目の岩 ですね
この後 困ったのは
ひとしさんが氷のスベリ台を
なかなか降りれなかったこと
登らなきゃ よかったですぅー
ほ~らね
二人で写真を撮るはずのピークに到達できなかったので
少し下った1800mの標識で記念撮影

下山も予想通り大変だ
急登は急坂

手に持つピッケルは上部の歯の部分を雪に刺しブレーキ
お尻をついて足はアイゼンでブレーキ

つかまれるような木もなく
雪に埋もれた木の根っこもあてにはならない
あまりにコワい時は腹を雪斜面につき
腹ばいになって下ることも多々

岩はツルツルに凍り突起もないので
つかまる場所もなくバランスを崩せば滑落


尻セードで下りたくても意外と
木の根っこが邪魔して滑れない

第六難関
急坂の恐怖
空はどんよりと薄暗い

よかったねぇー 下山決めて
ロープがあったら岩登れたかな?
そうかもしれませんね
でも時間ギリギリでしたから
これでよかったんですよ
まぁね~
また季節を変えて挑戦しようね
はい~

雪が降る

黒い岩が見えていた川の石も雪化粧

登りの時は異常なほど怖かった急登は
意外とそこまで怖くなく下れたのが不思議

帰りの高巻きの道も利き手側でピッケルを
突くことができたので安心だったよ

駐車場スペースに戻ると
白く雪をかぶったエクストレイルが待っていた
ただいま!

最後の第七難関
つるつる林道 お尻フリフリ
帰路の車の中は叫び声が響いた

お願いだから突っ込むときは山側にして
谷に落ちたら死ぬぅーっ
んなこといっても
こっちも必死なんですからぁー
厳冬期の鬼面山
七つもの難関がある
鬼の名にふさわしい山であった
翌日は好天の樹氷が美しい山を歩いたよ
空は紺碧 お楽しみにぃ~
 この日の立ち寄り湯はこちら
この日の立ち寄り湯はこちら
昼神温泉 ゆったり~な昼神
スキー帰りの人でいっぱいでした
 この日の車泊地はこちら
この日の車泊地はこちら
ヘブンスそのはらスキー場
24時間使用可のトイレがあり快適な車泊ができます
極楽編はこちら
七難

鬼面山
(赤石山脈南部エリア)
全山行 432回

 鬼面山の情報はこちら
鬼面山の情報はこちら
標高 鬼面山 1889.3m(1850mまで到達)
天気
 曇り・
曇り・ 雪
雪山行時間 7時間(休憩時間を含む)
〈コース〉虻川林道・第二駐車場下(8:15)-登山口(8:45)-
トチの木(9:30)-西尾根の稜(10:40-10:50)-展望地(1:00)-
ピストンで林道駐車スペース(3:15)
「鬼」と名のつく山は多々あれど
これほど鬼らしい山はないだろう

それが厳冬期の 鬼面山 だ

伊那山脈の最高峰鬼面山

南信の南アルプスの前に立ちはだかる山だ


この山は谷の奥にあったため 登山や信仰の対象には
ならなかったそうだが 近年 林道・山林作業道の開発で
日帰りの山として登山者が増える傾向にあるそうだ

一般的には国道152号の途中にある
地蔵峠から登るルートが使われる

しかぁ~し
今回 ひとちがは冬季に登るため地蔵峠までの道は
ゲートが閉鎖されているので無理

豊丘村からの虻川林道から攻めることにした

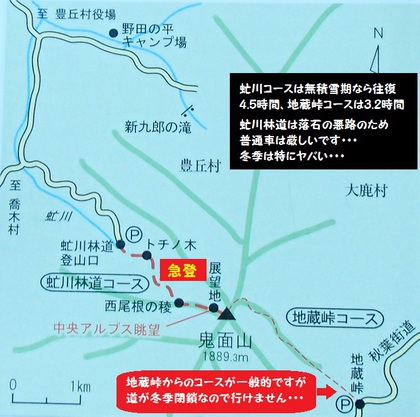
数日前 ちがこさんは豊丘村の役場に電話を入れた

あのー
ヘビ川林道は冬季閉鎖にはなりませんか?
車で駐車場まで行けます?
え゛? ヘビ川林道?
あ゛ー あ゛ー
ヘビ ぢゃなくて アブ ですよ
アブ
初っ端から大恥をかいてしまった

*言い訳ですがガイドブックの文字が小さくて
老眼の ちがこさんには 虻が蛇 に見えたんですわ

まぁ いいです

4WDなら入れますよ

昨年の12月の降雪で雪が残ってますが
それなりの装備を持っていれば大丈夫です

役場の人が自信あり気に言った

そうなんですかー

よかったー
チェーンもシャベルもあるから大丈夫ですね

最後に役場の人が言った

山の雪の状態はわかりませんよ

林道の入口に到着

それまでは民家もあり雪もなくフツーの道路なので
特に問題もなく順調


野田の平キャンプ場方向に向かい
途中を虻川沿いに登山口までの林道を走る

まだキャンプ場の分岐まで行かない道もこの通り


ひどい落石 よけるにも道幅が狭いので
そのまま落石の上をタイヤで通過するしかない

いつ落ちてくるかわからない石を恐れて
ハンドルを握る ひとしさんも緊張気味

ガイドブックに書いてあるじゃないですか

悪路って

え? ごめん読まなかった

上るにつれ 融け残った雪が氷になり
つるつるのスケート場みたいな狭い林道が
標高を上げながら九十九に続いた

それでも うちらの車は無敵だ

ますます落石はひどくなり
座布団級の鋭角の落石でとうとう先に進めなくなった

車から降りて落石を動かそうにも
重すぎてびくともしない

ダメだこりゃ

緊張が続いた運転で疲れ切った
ひとしさんが言った

これ以上は無理ですぅー

林道の安全な広い場所までバックして
歩いて登山口まで行きましょう

ふぁ~い

ツルツルの狭い林道を横滑りしながらバックし
安全な林道脇に駐車完了

第一難所
落石つるつる林道
あ゛―
大変だった


いきなりアイゼン装着の出発と
予想外の展開になったのも致し方ない

さっそく駐車場を通過した先にある登山口まで
つるつる林道を歩き出した

とはいえ ずーっと つるつるってわけでもない

陽当りのいい場所は雪や氷もなく
ゴロゴロと落石のひどい道


林道横の山斜面を見上げてみれば
白くいつ崩れてもおかしくないような岩が
こっちを睨んでいた


くわばら くわばら
なるべく刺激しないように通過

それでも時折ザザーっと崩れるのがコワい

ずんずん進んでいくと山から染み出た水が凍りつき
蛇の歯みたいなツララが何本も垂れ下がっている


これぞヘビ川林道

ぢゃなくて虻川林道


登山口に到着

嬉しいのは進むべき方向に足跡があったこと


ふにゃぁ~ 大丈夫そうだね

足跡もあるし問題なさそうだよ

そうですかね

赤テープもあるみたいだし問題ないかな

まずは虻川を渡る


そこから先は虻川に沿って高巻きの狭い道を
落っこちないように進むわけ


ともかく道幅が狭いのと 半分雪が凍って
滑りやすいのでピッケルを使って
確実に進むしかない危険個所


無積雪期なら問題ないはず

第二難関
高所から川に滑落しそうな道

あ゛―
コワかった


ようやく地に足がつくようなユルい道に変わった


おかげさまで足跡もバッチリなので
道迷いの心配もせずに済んだ

見上げるとこんな空


今日は曇りって言ってたから
展望あんまり期待してなかったけど
もしかするといいかもね

第一ポイント
豊丘村の天然記念物パワースポット


ふたりで幹に手を当て
木の温もりを感じた

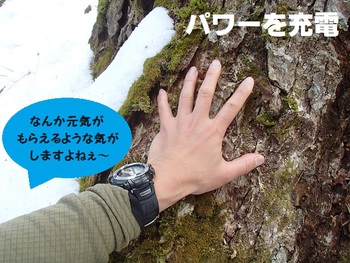
順調に足跡を追い
赤テープを確認しながら進んでいく


最後の渉渡を終えると
そこからは急登の連続

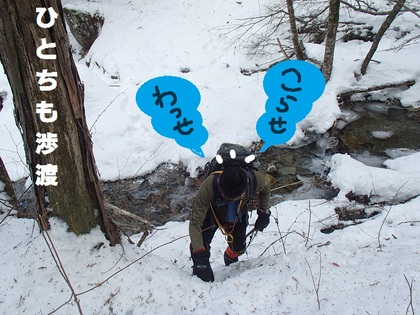
山の急斜のとりつきにポールに
かけられていた数々の謎の品物

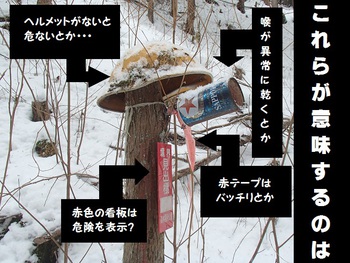
さぁー
登りますよぉ~


出だし雪はくるぶし程で固め
アイゼンを効かせて登れば問題なし

が 雪の下はアイスバーンなので
注意しながら登らなくていけませんな

100mごとに このような立派な看板


いつも使っているストックでは太刀打ちできないので
ピッケルをグサグサ刺しながら登る

標高が上がるにつれ傾斜が増すため
目の前は雪の壁のようだ


時々見えるのといえば

木の根っこが邪魔して登りにくい場所もありーの
つかみたくてもポキポキ折れてしまう木の枝ばかり


頼りにならない物ばかり
這い登っていくしかない


気温が一気に下がったような気がする

天気はやっぱり予報通りの曇り空
風も強く見上げると白い物が・・・

雪が降るなんて言いませんでしたよね

山だから 雪も降るよ

急登を登りきった場所は 第二ポイント
西尾根の稜


ようやく座ることのできる場所

天気が急速に悪くなって寒くなってきたのと
頼りにしていた足跡がこの場所を最後になかったこともあり
ちょっぴり心がクジけた

もう諦めて下山しよーかな

ひとしさんはどう思ってるのかな?
たぶん行きたくないと思ってるよ
そうかな

でもここで敗退するのは納得できないから
もうちょっと がんばってみるね

あー そう


全く足跡のない白い山

コースを確認できるのは ピラピラ風に揺れる
白ちゃけたビニール紐だけ


尾根に沿って登るしかないので
ここで登場 先頭ラッセル員 ひとしさん


急登だけど 後ろにさえ ひっくり返らなけりゃ
大丈夫そうだけど 下山の時は大丈夫かな?
たぶん大変だよ

もうヤメた方がいいよ

うるさいな


第三難関
急登の連続

どこまで登るんだろね?

順調に登ってはきたものの
やはり雪山の急登ラッセルともなると
二倍近く時間がかかるのが悔しい


こんなでピークまで到達できるのかな?
ちゃんと ちがこさん下山のこと考えてるのかな?
もう私は温かい温泉の方がいいんですけど

先頭ラッセル員 ややへたれ


一向に登るのをヤメようとしない ちがこさんに
「もうヤメませんか?」と言えない ひとしさん


ひとちー 言えば
もうヤメようって


ダメですぅー

ちがこさんは自分が納得しないとヤメませんからね

そうだ 納得できることを探せばいいかも


いい案あるの?

まあね まかして下さい

しばらく登っていくと ひとしさんの足が止まった

大きな岩の横からトラバースして尾根上部に出るらしい

まず岩をトラバースする前に 岩まで到達するには
超危険な山斜面を横断しなければいけない


ね いい場所あったでしょ

ホントだね
これで諦めるかな

じーっと危険な山斜面を眺めてギリギリまで進んでみたものの
やはり危険で赤テープ通りに岩を巻くのは不可能だと思った

ぐるりと見上げると 岩方向に移動するのではなく
登りにくいとは思われたが そのまま尾根の急斜を
這い登れば岩をトラバースせずとも尾根上部に
出ることができそうに見えた

こっちから行ってみるよ

え゛ 登るんですか?
うん 私が行ってダメなら諦めるから

そう言うと腰丈まである深さの雪をもろともせず
ちがこさんは ずんずん登っていってしまった


あ゛―
ダメじゃん 作戦失敗

行けるよぉー

ちがこさんが叫ぶ声がした

シブシブと ひとしさんも続く

冬道は簡単に作れるからいいねぇ~

無積雪期じゃ こーはいかないもんね

第四難関
危険な大岩トラバース
こーなったらもう先に進むしかないね

再び急登ラッセル員を任された ひとしさん
必死に登り続ける


もう時間的にピークは無理じゃないかな

なんとかして諦めさせなきゃ

なんとかなりそう?
まぁね 今度こそ

目の前に大岩がある


登るのは大変そうだな

お尻の重い ちがこさんには登れないかも
もしかして諦めるかもね

そんな簡単に行くかな?
ちがこさん意地でも登るよ きっと

予想通り 大岩に向かって
這い登る ちがこさん


無積雪期ならいったいこの場所は
どんな風になっているのかな?
登れたよぉ~っ

シブシブ ひとしさんが後を追う

大丈夫ですか?
登ったら下ることも考えて下さいよ

わかってるしー

第五難関
大岩までの這い登り
さてと 岩まで来たのはいいけど道がない

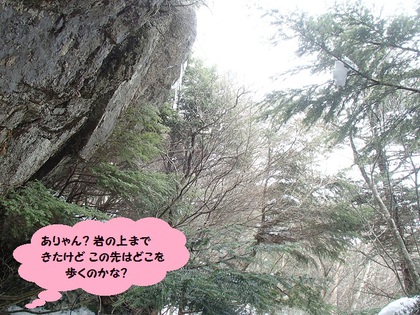
キョロキョロ見回すと
あった あった

岩の横に白ちゃけたビニール紐が
ひょろっぴい木に巻き付いていた


こっちから通過するんだ

まだ行くつもりだよ
いいの? ひとち?
よくないですぅー

岩のコワい斜面を岩にしがみつきながらカニ歩き
更に尾根を登っていくと
目の前に鬼面山のピークが見えた


こーなったら進まないわけがない

気合が入った ちがこさん
ズンズン先頭ラッセル員を始めた


あと ちょっとで山頂だい♪
1800mを示す看板から100mは尾根を
登っただろうか?
イヤなものが目の前にある

またしても大岩

あれまぁ 岩の横はカニ歩きかー
踏み外せばお陀仏だね

ブツブツ言いながら先頭で進んでみた

岩の上部に上がるためには
氷のスベリ台みたいになってる岩の隙間を
なんとか這い登るしかない

げ 無理

カニ歩きして岩の前まで戻ると
ひとしさんに言った

ありゃ 登れん

え゛?
あれほど諦めなかった ちがこさんが
山頂を目の前にして諦めようとするなんて

自分の目で確かめてしたかったのもある
私なら登れるかも ちょっと挑戦してみたい

危ないよ ひとち

ちがこさんが行けない場所はヤメた方がいいよ

ほら 虫倉山の橋の時 もそうだったじゃん

わかってますけど
男なら行ってみたい時もあるんですぅ

ちがこさんとチェンジして今度は
ひとしさんが岩の横をカニ歩きで移動し
岩の隙間のスベリ台を身体を突っ張りながら這い登る

な なんとか登れましたぁ~
でも景色よくありませ~ん


この先はどうなっているのか?
岩の展望地からは樹林帯で簡単にピークを
踏めたかもしれない

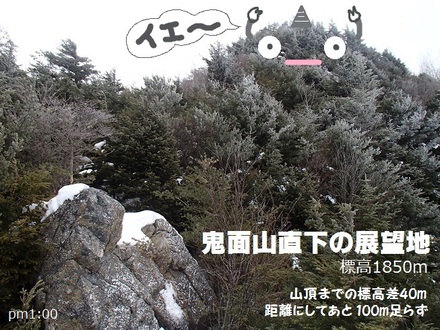
しかぁーし
現実 岩の下でこのような状態で
動けないでいる ちがこさんがいた


やっぱ無理

いいですよ

もうタイムオーバーです

下りましょう

上から声がした

第六難関
大岩の氷のスベリ台
山頂を目前にして下山することに決定

ひとちが下山誘導しなくても
ちがこさん諦めたね

はい 三度目の正直じゃなくて
三度目の岩 ですね

この後 困ったのは
ひとしさんが氷のスベリ台を
なかなか降りれなかったこと

登らなきゃ よかったですぅー

ほ~らね

二人で写真を撮るはずのピークに到達できなかったので
少し下った1800mの標識で記念撮影


下山も予想通り大変だ

急登は急坂

手に持つピッケルは上部の歯の部分を雪に刺しブレーキ
お尻をついて足はアイゼンでブレーキ


つかまれるような木もなく
雪に埋もれた木の根っこもあてにはならない

あまりにコワい時は腹を雪斜面につき
腹ばいになって下ることも多々


岩はツルツルに凍り突起もないので
つかまる場所もなくバランスを崩せば滑落



尻セードで下りたくても意外と
木の根っこが邪魔して滑れない


第六難関
急坂の恐怖
空はどんよりと薄暗い


よかったねぇー 下山決めて
ロープがあったら岩登れたかな?
そうかもしれませんね

でも時間ギリギリでしたから
これでよかったんですよ

まぁね~
また季節を変えて挑戦しようね

はい~


雪が降る


黒い岩が見えていた川の石も雪化粧


登りの時は異常なほど怖かった急登は
意外とそこまで怖くなく下れたのが不思議


帰りの高巻きの道も利き手側でピッケルを
突くことができたので安心だったよ


駐車場スペースに戻ると
白く雪をかぶったエクストレイルが待っていた

ただいま!

最後の第七難関
つるつる林道 お尻フリフリ
帰路の車の中は叫び声が響いた


お願いだから突っ込むときは山側にして
谷に落ちたら死ぬぅーっ

んなこといっても
こっちも必死なんですからぁー

厳冬期の鬼面山
七つもの難関がある
鬼の名にふさわしい山であった

翌日は好天の樹氷が美しい山を歩いたよ

空は紺碧 お楽しみにぃ~

 この日の立ち寄り湯はこちら
この日の立ち寄り湯はこちら
昼神温泉 ゆったり~な昼神
スキー帰りの人でいっぱいでした

 この日の車泊地はこちら
この日の車泊地はこちら
ヘブンスそのはらスキー場
24時間使用可のトイレがあり快適な車泊ができます

極楽編はこちら

2014年09月05日
雨にもマケズ! 後編
2014/08/30・31
雨上がりの晴れ間に♪
塩見岳
(赤石山脈北部エリア)
全山行 420回

 塩見岳の情報はこちら
塩見岳の情報はこちら
 前編はこちら
前編はこちら 
標高 三伏山 2615m 本谷山2657.9m
西峰 3046.9m 東峰 3052m
天気 晴れ・
晴れ・ ガス・
ガス・ 雨
雨
山行時間 10時間30分
〈コース〉
二日目:三伏峠テン場(5:00)-三伏山-本谷山-ゴーロ-
塩見小屋(7:20-7-30)-西峰(8:40-8:45)-東峰(8:50-9:00)-
ピストンでテン場(1:00-1:30)-下山(4:00)
バリバリとヘリが近づく音がした
ひとしさんはいない
後編
早朝4時
小屋がざわめきだした
低い自家発電機の音がテン場に響く
暗やみの中 山頂に向けて次々出発する人の
靴音がボカボカと忙しい
ふにゃぁー
お天気もつかな?
早く出発しましょう
様子見ですね
ささっと身支度 テント内の荷物を
コンパクトにまとめてからテントを飛び出した
ヘッデンを頼りに山頂へのコースを進む

水場との分岐を越えると
すぐに稜線に出た 三伏山だ
振り返ると 小屋の小さな灯りが
今日の山行を応援してくれているようにも見える

北側には立派な塩見岳の姿

三伏山からは天気がよければ360度の眺望が得られるが
早朝の薄暗い時間帯 黒い形だけは周囲の山を特定できない
どうしますか?
山頂まで がんばります?
まだ雲は多いよね
山頂にも でっかい雲がいるけど
展望いいのかな?
ガスの中だったら悲しいよね
うじゃうじゃ話をしていると
近くにいた単独のおじさんが言った
前線が停滞してるから微妙だね
先の本谷山で決めたら?

見上げた空には 黒い筋状の長い雲が
山を横断するように長く伸びている

そう言えば
小屋の人も言ってたっけ
今年の夏は毎日こんなお天気で
スカっと晴れた日がないよ
昼間はガス 夕方になると雨が降る
山小屋泣かせのお天気続き
早朝ならまだマシ
雲いなくなるかもね
じゃ 進んでみますか
足元がしっかり見え始めたので
ヘッデンをしまい本谷山へ向かう

迷うことない一本道
と
花畑の途中 コースを外れた場所に
いい展望地発見
岩が突き出た場所で西側の景色が
すこぷるいのだ

ここで食べなきゃ
いつ食べる?

ザックに詰め込んできた食料でお腹いっぱい
これが後に仇となることを
ひとちは知らない・・・・・

満腹ぷくぷくになったので
再びコースに戻り山頂を目指す
ちょっと登ると本谷山
さっきまで山頂を覆っていたでっかい雲が
いつの間にかいなくなっていた

いいじゃん いいじゃ
行きましょう!
本谷山を下り塩見に向けて登り返す

この辺りは「山と高原地図」に記載されている
標準コースタイムをかなりカットできるポイント
実際 塩見を登った人の記録や感想からも
同じように時間短縮できると記載されていたものの
自分のペースで果たして通じるのか不安だった
ちがこさんにも行けそうだ!
長いと想像していたものが 実際短いと
あっという間に次のポイントに着くのが嬉しい

鬱陶しい樹林帯からも解放
バッチリ空が見える稜線に

見たいですか?
それじゃ お見せしましょう

昨日のどしゃ降りからは想像も
しなかった素晴らしい景色

山頂アタック決めてよかったね
はい 雨でリベンジ戦になるとばかり
思ってましたから嬉しいですぅ
塩見小屋に到着

ここはとても小さな小屋
それにボロっちいね
でもね この小屋は塩見岳に登る時 とっても重要
なくてはならない小屋なんだよ
ふ~ん
小屋を一段上がった場所のベンチからは
こんな景色を堪能できる

小屋の裏側には塩見岳につながる
手前の勇ましい山の姿

小屋のお姉さんが慌ただしく
小屋付近にいる人に声をかけていた
大型のヘリがつくので 帽子や細かい荷物が
吹き飛ばされる可能性があるので
みなさん気をつけて下さい
呼びかけが終わるか終らないうちに
バリバリとヘリが近づく音がした

朝食を食べ過ぎたのがいけなかったのか?

小屋にはトイレはありません。
携帯トイレを購入して用足し小屋を使わせてもらいます。
排泄物はヘリで下界に運ばれるシステムです。
ヘリの音がしますぅ
用足し小屋が揺れているような気がする

もしかしてヘリは この小屋ごと排泄物を
下界に運ぶわけぢゃありませんよね?

ガタ ガタ ガタ
ヤバい
ヤバいですよー
どうしましょう
戸を開けたら空の上を小屋が飛んでたら
シャレにもなんないよね

そうなんですぅ
コワくて戸を開けられません
しばし 小屋で待機
バリ バリ バリ
ヘリはしばらくすると
空の彼方に去っていった
よかったぁー
やっと解放された

長い休憩となりました
まぁいいです
ともかく下から雲が湧きあがってくるので
できるだけ早く山頂に到達したい所
急ぎましょう
岩がゴツゴツした場所にも
花たちは咲き誇っていた

あっちを ずーっと歩いてきたんだよね
帰りもロングコース がんばらなきゃ
はい
+テントをたたんで下山ですからね

黄色のペンキがつけられたコース
ストックをしまい登っていく
地図には危険マークもついていたけど
それほどコワいと感じる場所はない

天狗岩を越えると

どかーん

あまりの迫力に
一瞬引き気味
写真だけ見ると とても登れそうにないように感じるけど
以外にも登り始めると フツーに登れるのが不思議
岩場を這い登り 山頂に到着

登れてよかったね
はい 昨日の夜の時点では
絶対敗退かと思ってましたから
やればできるもんだ

広がり始めた雲で遠くの山々の姿はよく見えないけど
この山頂だけは晴れている

やったぁー
立派な山頂標識は西峰にあるが
実際 標高が高いのは東峰

二つのピークを結ぶ稜線上にも花はある
あと少しで花びらを開くであろう
山の花のつぼみは格段に美しい

小さなお地蔵さんがいる東峰

がんばったご褒美は
充実した達成感

ピークの岩の間からも
かわいい顔をだしている花

東峰から南に続く
すてきな稜線

なかなか足を踏み入れることができない
ロングコースの魅力ある尾根道

うっとりと景色を眺めている間にも
雲たちは容赦してくれない
もうじき山頂
雲の中に入っちゃうね
そうですね
帰りも長いですから
そろそろ下山しましょう

登りは早かったけど
下りに弱い ちがこさん
標準タイムを
オーバーしないようにしなくっちゃ
がんばってテン場を目指すことにした

振り返ればこの景色

雲が到着するの早かったですね
雨が降り出すのは時間の問題
落ちてこないうちにテントをたたまないと
大変なことになりますぅ
だよね
急げ 急げ
急げ 
景色もへったくりもなくなったので
こーなったら テン場目指して
小走りで下るしかない

テン場に到着
他のキャンパーのテントはすでになく
入れ替わりでテントを張る登山者がいるのみ
大急ぎで移動式住宅をザックにしまい
初日にあえいだ鳥倉駐車場までの道を下る

花がきれいですね
今更かい

登りの時は必死で 周囲を見ることも
しなかった ひとしさん
帰路は余裕か?

塩見からの道のりは長かった

登山口に到着するころには
雨がバラバラと降りだし 林道歩きはカッパ隊
大急ぎで車に乗り込んだ
窓には大粒の雨
終わってみれば 不安定な天気の中
短時間だけど晴れ間を拝むことができた
今度 雨テントになっても行けるね
色々なパターンを経験するのって大事
そうですね
でも どうせならテン泊はやっぱり
晴れた日の方がいいかな
 雨もまたよろし
雨もまたよろし 

楽しいことが凝縮した
有意義な山歩きとなった
おしまい
 この日の立ち寄り湯はこちら
この日の立ち寄り湯はこちら
松川温泉 清流苑
高速から近いので便利、今時期からは
有名な松川のリンゴも販売してますよ
雨上がりの晴れ間に♪
塩見岳
(赤石山脈北部エリア)
全山行 420回

 塩見岳の情報はこちら
塩見岳の情報はこちら
 前編はこちら
前編はこちら 
標高 三伏山 2615m 本谷山2657.9m
西峰 3046.9m 東峰 3052m
天気
 晴れ・
晴れ・ ガス・
ガス・ 雨
雨山行時間 10時間30分
〈コース〉
二日目:三伏峠テン場(5:00)-三伏山-本谷山-ゴーロ-
塩見小屋(7:20-7-30)-西峰(8:40-8:45)-東峰(8:50-9:00)-
ピストンでテン場(1:00-1:30)-下山(4:00)
バリバリとヘリが近づく音がした

ひとしさんはいない

後編
早朝4時
小屋がざわめきだした

低い自家発電機の音がテン場に響く

暗やみの中 山頂に向けて次々出発する人の
靴音がボカボカと忙しい

ふにゃぁー
お天気もつかな?
早く出発しましょう

様子見ですね

ささっと身支度 テント内の荷物を
コンパクトにまとめてからテントを飛び出した

ヘッデンを頼りに山頂へのコースを進む


水場との分岐を越えると
すぐに稜線に出た 三伏山だ

振り返ると 小屋の小さな灯りが
今日の山行を応援してくれているようにも見える


北側には立派な塩見岳の姿


三伏山からは天気がよければ360度の眺望が得られるが
早朝の薄暗い時間帯 黒い形だけは周囲の山を特定できない

どうしますか?
山頂まで がんばります?
まだ雲は多いよね

山頂にも でっかい雲がいるけど
展望いいのかな?
ガスの中だったら悲しいよね

うじゃうじゃ話をしていると
近くにいた単独のおじさんが言った

前線が停滞してるから微妙だね

先の本谷山で決めたら?

見上げた空には 黒い筋状の長い雲が
山を横断するように長く伸びている


そう言えば
小屋の人も言ってたっけ

今年の夏は毎日こんなお天気で
スカっと晴れた日がないよ

昼間はガス 夕方になると雨が降る
山小屋泣かせのお天気続き

早朝ならまだマシ
雲いなくなるかもね

じゃ 進んでみますか
足元がしっかり見え始めたので
ヘッデンをしまい本谷山へ向かう


迷うことない一本道

と
花畑の途中 コースを外れた場所に
いい展望地発見

岩が突き出た場所で西側の景色が
すこぷるいのだ


ここで食べなきゃ
いつ食べる?

ザックに詰め込んできた食料でお腹いっぱい

これが後に仇となることを
ひとちは知らない・・・・・

満腹ぷくぷくになったので
再びコースに戻り山頂を目指す

ちょっと登ると本谷山

さっきまで山頂を覆っていたでっかい雲が
いつの間にかいなくなっていた


いいじゃん いいじゃ
行きましょう!
本谷山を下り塩見に向けて登り返す


この辺りは「山と高原地図」に記載されている
標準コースタイムをかなりカットできるポイント

実際 塩見を登った人の記録や感想からも
同じように時間短縮できると記載されていたものの
自分のペースで果たして通じるのか不安だった

ちがこさんにも行けそうだ!
長いと想像していたものが 実際短いと
あっという間に次のポイントに着くのが嬉しい


鬱陶しい樹林帯からも解放
バッチリ空が見える稜線に


見たいですか?
それじゃ お見せしましょう


昨日のどしゃ降りからは想像も
しなかった素晴らしい景色


山頂アタック決めてよかったね

はい 雨でリベンジ戦になるとばかり
思ってましたから嬉しいですぅ

塩見小屋に到着


ここはとても小さな小屋

それにボロっちいね

でもね この小屋は塩見岳に登る時 とっても重要

なくてはならない小屋なんだよ
ふ~ん

小屋を一段上がった場所のベンチからは
こんな景色を堪能できる


小屋の裏側には塩見岳につながる
手前の勇ましい山の姿


小屋のお姉さんが慌ただしく
小屋付近にいる人に声をかけていた

大型のヘリがつくので 帽子や細かい荷物が
吹き飛ばされる可能性があるので
みなさん気をつけて下さい

呼びかけが終わるか終らないうちに
バリバリとヘリが近づく音がした


朝食を食べ過ぎたのがいけなかったのか?

小屋にはトイレはありません。
携帯トイレを購入して用足し小屋を使わせてもらいます。
排泄物はヘリで下界に運ばれるシステムです。
ヘリの音がしますぅ

用足し小屋が揺れているような気がする


もしかしてヘリは この小屋ごと排泄物を
下界に運ぶわけぢゃありませんよね?

ガタ ガタ ガタ
ヤバい

ヤバいですよー

どうしましょう

戸を開けたら空の上を小屋が飛んでたら
シャレにもなんないよね


そうなんですぅ

コワくて戸を開けられません

しばし 小屋で待機

バリ バリ バリ
ヘリはしばらくすると
空の彼方に去っていった

よかったぁー
やっと解放された


長い休憩となりました

まぁいいです

ともかく下から雲が湧きあがってくるので
できるだけ早く山頂に到達したい所

急ぎましょう

岩がゴツゴツした場所にも
花たちは咲き誇っていた


あっちを ずーっと歩いてきたんだよね

帰りもロングコース がんばらなきゃ

はい
+テントをたたんで下山ですからね


黄色のペンキがつけられたコース
ストックをしまい登っていく

地図には危険マークもついていたけど
それほどコワいと感じる場所はない


天狗岩を越えると


どかーん

あまりの迫力に
一瞬引き気味

写真だけ見ると とても登れそうにないように感じるけど
以外にも登り始めると フツーに登れるのが不思議

岩場を這い登り 山頂に到着


登れてよかったね

はい 昨日の夜の時点では
絶対敗退かと思ってましたから

やればできるもんだ


広がり始めた雲で遠くの山々の姿はよく見えないけど
この山頂だけは晴れている


やったぁー

立派な山頂標識は西峰にあるが
実際 標高が高いのは東峰


二つのピークを結ぶ稜線上にも花はある

あと少しで花びらを開くであろう
山の花のつぼみは格段に美しい


小さなお地蔵さんがいる東峰


がんばったご褒美は
充実した達成感


ピークの岩の間からも
かわいい顔をだしている花


東峰から南に続く
すてきな稜線


なかなか足を踏み入れることができない
ロングコースの魅力ある尾根道


うっとりと景色を眺めている間にも
雲たちは容赦してくれない

もうじき山頂
雲の中に入っちゃうね

そうですね
帰りも長いですから
そろそろ下山しましょう


登りは早かったけど
下りに弱い ちがこさん

標準タイムを
オーバーしないようにしなくっちゃ

がんばってテン場を目指すことにした


振り返ればこの景色


雲が到着するの早かったですね

雨が降り出すのは時間の問題
落ちてこないうちにテントをたたまないと
大変なことになりますぅ

だよね

急げ
 急げ
急げ 
景色もへったくりもなくなったので
こーなったら テン場目指して
小走りで下るしかない


テン場に到着

他のキャンパーのテントはすでになく
入れ替わりでテントを張る登山者がいるのみ

大急ぎで移動式住宅をザックにしまい
初日にあえいだ鳥倉駐車場までの道を下る


花がきれいですね

今更かい


登りの時は必死で 周囲を見ることも
しなかった ひとしさん

帰路は余裕か?

塩見からの道のりは長かった


登山口に到着するころには
雨がバラバラと降りだし 林道歩きはカッパ隊

大急ぎで車に乗り込んだ

窓には大粒の雨

終わってみれば 不安定な天気の中
短時間だけど晴れ間を拝むことができた

今度 雨テントになっても行けるね
色々なパターンを経験するのって大事

そうですね
でも どうせならテン泊はやっぱり
晴れた日の方がいいかな

 雨もまたよろし
雨もまたよろし 

楽しいことが凝縮した
有意義な山歩きとなった

おしまい

 この日の立ち寄り湯はこちら
この日の立ち寄り湯はこちら
松川温泉 清流苑
高速から近いので便利、今時期からは
有名な松川のリンゴも販売してますよ

2014年09月03日
雨にもマケズ! 前編
2014/08/30・31
初体験! 雨テント
塩見岳
(赤石山脈北部エリア)
全山行 420回

 塩見岳の情報はこちら
塩見岳の情報はこちら
標高 三伏峠 2580m
天気 晴れ・
晴れ・ 雨
雨
山行時間 4時間
〈コース〉
初日:鳥倉駐車場(12:00)-登山口(12:40)-コル-
豊口山分岐-三伏峠・テン場(4:00)
雨は濁流のように階段状のテン場を流れ下り
取り残された中州みたいな場所にテントを張った
水没する可能性はある
前編
今年の夏は週末になると
お天気があまりよろしくない
8月はお天気にふりまわされて
ろくに山を登っていない現実
これじゃいかん
ということで 不安定な天気承知で
百名山を目指すことにした
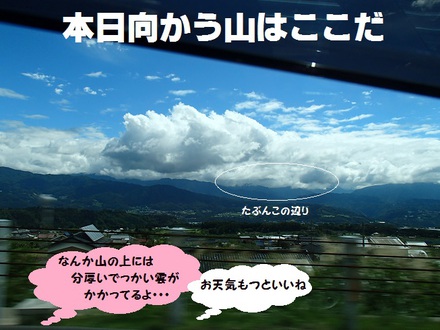
松川インターから約1時間半
鳥倉登山口に昼に到着
本日は三伏峠にテントを張る
この時期の鳥倉駐車場は土日ともなれば
恐ろしい混雑が予想された
しかぁ~し お天気が悪いためか車は超少ない
ラッキー♪

よかったですぅー
車停める場所が確保できて
ひとちがと同じように三伏峠を
今日の目的地とする登山者が次々と出発していく
みんなザックが小さいのは何故?
テン泊する人あんまりいないのかな?
マケジとひとちがも登山届を提出した後
どでかいザックを背負いゲートから鳥倉林道に突入した
いってみよう

お盆の不摂生のせいか身体が重い
ザックの重みが落ちた筋肉に堪える
30分は歩かなきゃいけない舗装路の林道は
山を巻きゆるやかに続く
ずんずん無言で先を歩く ひとしさん

このパターン
辛い状態に時に発症するよね
ねぇ 大丈夫?
後方から声をかけても
うんとも すんとも言わない
おい 無視かい?
いいもん いいもん
相手にしてくれないので
林道沿いに咲く花たちを撮影することにした

不安定な天気とはいえ ありがたいことに
まだ おてんとさんは頭の上で機嫌がいい

喉が渇くほどの暑さでもなく快適
秋は刻々と進んでいる

荒い息使いの ひとしさんとは対照的に
ちがこさんはウロウロと林道を歩きまわる

林道っていっても
山の花が意外とたくさんあるよね
パチ パチ パチ



いつの間にか ひとしさんの姿はない
待ってよぉ~っ

そのころ ひとしさんは前を歩きながら
心の中で格闘していた

あ~ぁ ザックやたら重いですぅ
いったい ちがこさん何を入れてきたのかな?
山支度は ほとんど ちがこさんにおまかせの
ひとしさんゆえ いったいザックに何が詰め込まれて
いるのかさえわからない状況
あ~ 辛い 重すぎる
心が折れていく・・・
ポキ ポキ ポキ

も もう帰りたい
天気もあまりよくないし
ポキ ポキ ポキ

まだ林道だよ ひとち
そんなんで峠まで登れるの?
ポ キ
わかりませ~ん
天窓橋から見えた景色

雨雲が早いか
ひとちがが峠まで登るのが早いか
そんな状況下 ひとしさんのペースは
上がることもなく
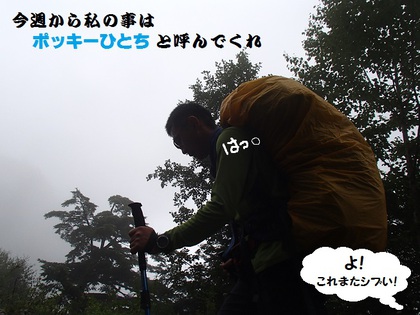
相変わらず
折れ続ける心

登山口に到着
ここからが本番だ

登山道に入ると山は白く煙っていた
霧が立ち込め幻想的な景色が広がる

シダが群生し しばらく登ると
紫色の花の花畑が目の前に

心と身体に余裕のない ひとしさんは
ただひたすら無言でザックと戦っていた
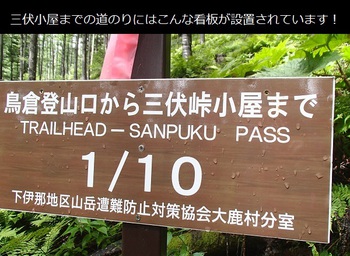
くそー くそー

ひとりうかれポンチキで花の撮影やら
キョロキョロと山の景色を眺め
楽しんでいるのは ちがこさん

久しぶりの山歩き
展望がなくってもいいんだぁー
山はいいねぇ~

のん気だね ちがこさん
ひとち 死にそうだよ
ありゃ そう

あまり整備がいきとどいていない
急登の歩きにくい登山道とは違い
ゆるやかな歩きやすいコースは快適だ

それでも4/10あたりにくると
木橋が待ち構えていた

まるでビーバーの巣のように
細い丸太を積み重ねたような木橋は
なんとも足場が悪く 心もとない

サイドにつけられた手すりだって
力入れたら外側に折れちゃうんじゃないかと
出した手を思わずひっこめたほど

ようやく道のり半分を過ぎた

にゃ?
まだ橋があるよ

トポトポと水の溜まる音
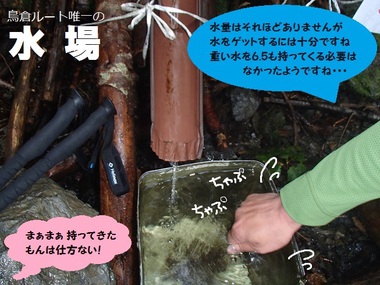
駐車場から2時間半
重い水を背負わなくてもここで水は調達できる
ごめん
重いザックの中身半分は
水だったわけね
山を巻くように木橋状のコースが続く

バランスとってしっかり歩いてね
ほ~ら 危ないったら

それほど高度感はないものの
できれば落ちたくはない
豊口山分岐

こちらのコースにも興味はあったものの
「通行止め」期間が長く あえて選択しなかった
とうとう最後の看板だ

あれほど無表情・無言で登り続けた
ひとしさんにも笑顔が戻った
やっとここまでこれました
あ゛~ 大変だった
折れた心復活
ところが
さっきまで霧状だった雨は本降りとなり
カッパを着なければいられない

雨でしとった登山道
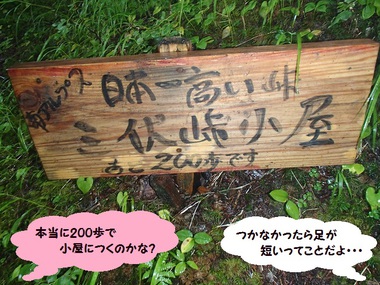
1・2・3・4・5・6・7・8・・・
・・・・・・・200!
小屋に到着

すばらしい!
ちがこさんの足の長さは標準ってことだよ
そうゆーことにしよう
小屋の前には花畑
でもスルー

雨ひどいもんね
大急ぎで小屋前の屋根のある場所に避難
先客のパーティーが ぼそぼそ話していた
もう15分待って小雨にならなかったら
テン泊はやめて素泊にしませんか?
そうだねぇー
雨だとテントは大変
特に後片付け
だよねぇー
明日だって雨ひどいかも
もう濡れるのいやだし
やっぱ素泊にしますか
賛成!

こんな会話を耳にしてしまうと
気持ちが萎えてくる
これからテント張るってのにヤメてくれー
どうする ひとしさん?
え?
どうするってテントでしょ
やっぱね
小屋で受け付けを済ませると
雨がザーザー降る中 テン場へ移動
しばしウロウロと雨の中
設営地を物色
ここにき~めたっと♪
雨降る中 ひとしさんはテントを張り
ちがこさんはテント内で濡れたザックや
荷物を手際よく片づける

15分以内ですべて完了
初めての雨テントの割に上出来
ようやくテントに落ち着いたものの
外で夕食準備などできるわけもなく
テントの中で夕食

バラバラ バラバラ
ザザー ザザー
テントに落ちる雨の強さは風こそないものの
今までに経験したことのないレベルに達した
まるでゲリラ豪雨みたいですね
テントが流されたらどうしよう
確かに・・・
雨は濁流のように階段状のテン場を流れ下り
取り残された中州みたいな場所にテントを張った
水没する可能性はある

ヤバいじゃん
早めに小屋に避難した方がいいんじゃない?
いいの
テントがヨットになったら避難するよ
なんとかなるっしょ
テントがヨットになりそうになった経験 は
過去にもある
別の意味で違うヨットだけど
テント内に侵入する雨水を考慮し
できるだけ荷物が濡れないようにしたものの
夜を持ち越すことができるのだろうか?
明日 山頂まで行くんですか?
天気がこれじゃ~ねぇ~
雨ひどかったらスパっと諦めよう
リベンジってことで
よかったぁー
気が楽になりました
ちがこさんのことだから絶対行くと言うんじゃないかと思ってました
おやすみですぅー

 その夜のこと
その夜のこと 
ちがこさんは 普段なら聞こえないものが
聞こえてしまったらしい・・・
必見! 初秋の怪談
5時間続いた豪雨
0時を過ぎるとピタリとやんだ
翌朝テントから顔を出した ひとしさんが言った
☆が出てますぅ

こりゃ 行くっきゃないね
山の神は どうやら
ひとちがに味方してるみたいだよ
 後編に続く
後編に続く 
初体験! 雨テント
塩見岳
(赤石山脈北部エリア)
全山行 420回

 塩見岳の情報はこちら
塩見岳の情報はこちら
標高 三伏峠 2580m
天気
 晴れ・
晴れ・ 雨
雨山行時間 4時間
〈コース〉
初日:鳥倉駐車場(12:00)-登山口(12:40)-コル-
豊口山分岐-三伏峠・テン場(4:00)
雨は濁流のように階段状のテン場を流れ下り
取り残された中州みたいな場所にテントを張った

水没する可能性はある

前編
今年の夏は週末になると
お天気があまりよろしくない

8月はお天気にふりまわされて
ろくに山を登っていない現実

これじゃいかん

ということで 不安定な天気承知で
百名山を目指すことにした

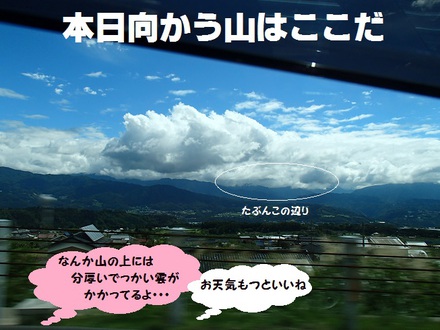
松川インターから約1時間半

鳥倉登山口に昼に到着

本日は三伏峠にテントを張る

この時期の鳥倉駐車場は土日ともなれば
恐ろしい混雑が予想された

しかぁ~し お天気が悪いためか車は超少ない

ラッキー♪

よかったですぅー
車停める場所が確保できて

ひとちがと同じように三伏峠を
今日の目的地とする登山者が次々と出発していく

みんなザックが小さいのは何故?
テン泊する人あんまりいないのかな?
マケジとひとちがも登山届を提出した後
どでかいザックを背負いゲートから鳥倉林道に突入した

いってみよう


お盆の不摂生のせいか身体が重い
ザックの重みが落ちた筋肉に堪える

30分は歩かなきゃいけない舗装路の林道は
山を巻きゆるやかに続く

ずんずん無言で先を歩く ひとしさん


このパターン
辛い状態に時に発症するよね

ねぇ 大丈夫?
後方から声をかけても
うんとも すんとも言わない

おい 無視かい?
いいもん いいもん

相手にしてくれないので
林道沿いに咲く花たちを撮影することにした


不安定な天気とはいえ ありがたいことに
まだ おてんとさんは頭の上で機嫌がいい


喉が渇くほどの暑さでもなく快適
秋は刻々と進んでいる


荒い息使いの ひとしさんとは対照的に
ちがこさんはウロウロと林道を歩きまわる


林道っていっても
山の花が意外とたくさんあるよね

パチ パチ パチ



いつの間にか ひとしさんの姿はない

待ってよぉ~っ


そのころ ひとしさんは前を歩きながら
心の中で格闘していた


あ~ぁ ザックやたら重いですぅ

いったい ちがこさん何を入れてきたのかな?
山支度は ほとんど ちがこさんにおまかせの
ひとしさんゆえ いったいザックに何が詰め込まれて
いるのかさえわからない状況

あ~ 辛い 重すぎる
心が折れていく・・・
ポキ ポキ ポキ

も もう帰りたい

天気もあまりよくないし

ポキ ポキ ポキ

まだ林道だよ ひとち
そんなんで峠まで登れるの?
ポ キ

わかりませ~ん

天窓橋から見えた景色


雨雲が早いか
ひとちがが峠まで登るのが早いか

そんな状況下 ひとしさんのペースは
上がることもなく

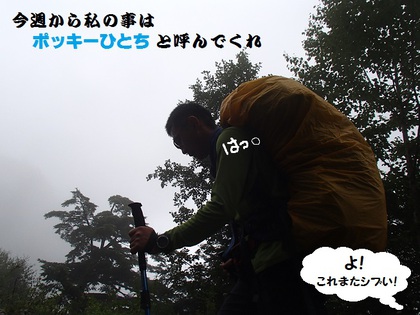
相変わらず
折れ続ける心


登山口に到着

ここからが本番だ


登山道に入ると山は白く煙っていた
霧が立ち込め幻想的な景色が広がる


シダが群生し しばらく登ると
紫色の花の花畑が目の前に


心と身体に余裕のない ひとしさんは
ただひたすら無言でザックと戦っていた

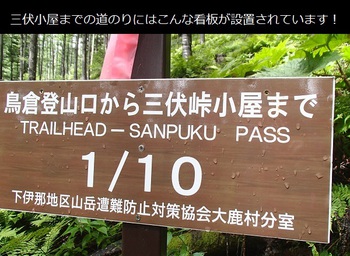
くそー くそー

ひとりうかれポンチキで花の撮影やら
キョロキョロと山の景色を眺め
楽しんでいるのは ちがこさん


久しぶりの山歩き
展望がなくってもいいんだぁー

山はいいねぇ~


のん気だね ちがこさん
ひとち 死にそうだよ
ありゃ そう


あまり整備がいきとどいていない
急登の歩きにくい登山道とは違い
ゆるやかな歩きやすいコースは快適だ


それでも4/10あたりにくると
木橋が待ち構えていた


まるでビーバーの巣のように
細い丸太を積み重ねたような木橋は
なんとも足場が悪く 心もとない


サイドにつけられた手すりだって
力入れたら外側に折れちゃうんじゃないかと
出した手を思わずひっこめたほど


ようやく道のり半分を過ぎた


にゃ?
まだ橋があるよ


トポトポと水の溜まる音

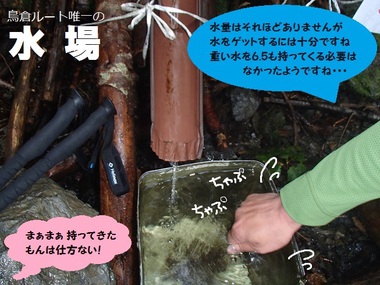
駐車場から2時間半
重い水を背負わなくてもここで水は調達できる

ごめん

重いザックの中身半分は
水だったわけね

山を巻くように木橋状のコースが続く


バランスとってしっかり歩いてね

ほ~ら 危ないったら


それほど高度感はないものの
できれば落ちたくはない

豊口山分岐


こちらのコースにも興味はあったものの
「通行止め」期間が長く あえて選択しなかった

とうとう最後の看板だ


あれほど無表情・無言で登り続けた
ひとしさんにも笑顔が戻った

やっとここまでこれました

あ゛~ 大変だった

折れた心復活

ところが

さっきまで霧状だった雨は本降りとなり
カッパを着なければいられない


雨でしとった登山道

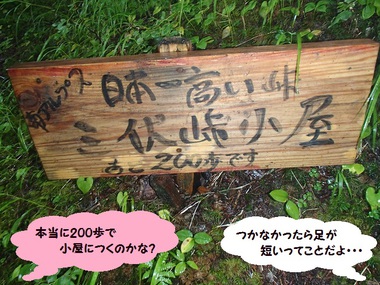
1・2・3・4・5・6・7・8・・・
・・・・・・・200!
小屋に到着


すばらしい!
ちがこさんの足の長さは標準ってことだよ

そうゆーことにしよう

小屋の前には花畑
でもスルー


雨ひどいもんね

大急ぎで小屋前の屋根のある場所に避難
先客のパーティーが ぼそぼそ話していた

もう15分待って小雨にならなかったら
テン泊はやめて素泊にしませんか?
そうだねぇー
雨だとテントは大変

特に後片付け

だよねぇー
明日だって雨ひどいかも

もう濡れるのいやだし
やっぱ素泊にしますか

賛成!

こんな会話を耳にしてしまうと
気持ちが萎えてくる

これからテント張るってのにヤメてくれー

どうする ひとしさん?
え?
どうするってテントでしょ
やっぱね

小屋で受け付けを済ませると
雨がザーザー降る中 テン場へ移動

しばしウロウロと雨の中
設営地を物色

ここにき~めたっと♪
雨降る中 ひとしさんはテントを張り
ちがこさんはテント内で濡れたザックや
荷物を手際よく片づける


15分以内ですべて完了

初めての雨テントの割に上出来

ようやくテントに落ち着いたものの
外で夕食準備などできるわけもなく
テントの中で夕食


バラバラ バラバラ
ザザー ザザー
テントに落ちる雨の強さは風こそないものの
今までに経験したことのないレベルに達した

まるでゲリラ豪雨みたいですね
テントが流されたらどうしよう

確かに・・・
雨は濁流のように階段状のテン場を流れ下り
取り残された中州みたいな場所にテントを張った

水没する可能性はある


ヤバいじゃん
早めに小屋に避難した方がいいんじゃない?
いいの

テントがヨットになったら避難するよ

なんとかなるっしょ

テントがヨットになりそうになった経験 は
過去にもある

別の意味で違うヨットだけど

テント内に侵入する雨水を考慮し
できるだけ荷物が濡れないようにしたものの
夜を持ち越すことができるのだろうか?
明日 山頂まで行くんですか?
天気がこれじゃ~ねぇ~

雨ひどかったらスパっと諦めよう

リベンジってことで

よかったぁー
気が楽になりました
ちがこさんのことだから絶対行くと言うんじゃないかと思ってました

おやすみですぅー


 その夜のこと
その夜のこと 
ちがこさんは 普段なら聞こえないものが
聞こえてしまったらしい・・・

必見! 初秋の怪談
5時間続いた豪雨

0時を過ぎるとピタリとやんだ

翌朝テントから顔を出した ひとしさんが言った

☆が出てますぅ


こりゃ 行くっきゃないね

山の神は どうやら
ひとちがに味方してるみたいだよ

 後編に続く
後編に続く 
2014年09月01日
初秋の怪談・・・
2014/08/30
テン場の幽霊さん?

あなたは山でこんな経験ありますか?
見えない何かを感じたこと
その日の夜 テントに叩きつける雨は
益々ひどくなっていった
バケツの水をひっくり返したような
雨の重みがテントにのしかかる

テントがペシャンコになるかも
あわや ひとちが危機一髪か
そんなことを 考えながら
シュラフに深々と潜り込む
雨で冷えた身体がまだ冷たい
それにしても ひどい どしゃぶり
ちがこさんの天気予報では
こんなに雨が降るはずなかったんだけどな
山の天気は予想外
雨音に混じって何か違う音が聞こえる
何の音かな?
しばらく じっと耳を澄ませ
雨音以外の音が何なのか確かめた
おかしい
んなわけないのに
横で疲れきった ひとしさんは
グーグーいびきをかいて眠っている

テントから顔出して確かめたら
雨でびちょ濡れになりそうだし
気になる 気になる 気になる・・・
眠れない 眠れない 眠れない 眠れない
眠れない 眠れない 眠れない 眠れない
うーん やっぱり眠れない
暗やみの中で ひとしさんに
そっと声をかけてみた
ひとしさん?
起きてる?
ふが
何ですか?
寝るの早いね
もう いびきかいてたよ
え?
私 いびきしてました?
で 何ですか?
あのさー
音がするんだけどね・・・
何の音ですか?
たぶん動物でもなく
人でもない・・・
え゛
じゃ いったい何ですか?
この日 小屋の裏側のテン場に
ひとちが以外のテントは三張しかなかった
天気のいい土日なら 混み合うテン場だけど
雨がガンガン降ってるからテントは少ない
ケチな ひとちがといえば
ここまで重たいザックを上げた以上 小屋泊など
選択するわけがなく 雨がガンガン降る中
大急ぎ 突貫工事で移動式住宅を建築した
テントを立てたのは階段状になっている
テン場の一番下から三番目の段
テン場の横につけられた登山道から入った
二つ目のスペースだ
どこにテントを張っても水たまりの中に
テントを張ることには変わりはないけど
できるだけ被害の少ない場所に張ったつもり

どしゃぶりのため 一端テントに入ったら
外に出るのは ほぼ不可能で
トイレに行きたくても小降りになるまで
がまんしなきゃいけない状況
たぶんこの先テントが増えることはないだろう
と 正直思った
テントに入ってからすでに三時間
外は暗闇
もしテン泊の人や小屋泊の人が近くにくれば
ヘッデンの明かりでチラチラとわかるはず

しかし そんな光はなく
テン場は暗やみの世界だ
なのに ちがこさんは感じるのだ
いるはずのない人の気配
で いったい何が聞こえるんですか?
うんとね
うちのテントの二つ下 一番下のスペースにね
いるわけよ
だから いったい何がいるんですか?
ハッ ハッ
ハッ ハッ
ハッ
って雨音に混じって人の荒い息使いと
ペチャペチャ テン場の中を歩き回る足音
幽霊さんかな?

え゛
それと横の登山道を小屋方向に階段を登っていく
登山靴のガボガボした音
大きなサイズの山靴みたいだよ
幽霊さんだと思うよ・・・

え゛
たぶん どっちも山の人みたいだけど
生きてる人じゃないことは確かだと思う
山で遭難とかして亡くなった人じゃないかな
え゛ ー
本当に聞こえるんですか?
うん
ちがこさんは どっちらかというと
そーゆーのに敏感ぢゃない
でもね 今夜は何故だか聞こえるのだ
・・・・・
大丈夫だよ
悪さするような人たちじゃなさそうだし
きっと混み合ったテン場には出ずらいとか?
今夜はどしゃぶりで人も少ないから
たまたま出てきたとか?
そうゆーもんですかね
それっきり ひとしさんは黙ってしまった

気になりつつも ひとしさんに話したので満足
早くテントを張る場所が決まればいいね
なんて思いながらいつの間にか深い眠りに入った
この話
信じるも信じないもあなた次第
真実が知りたければ どしゃぶりの日 このテン場に
テントを張って確かめてみるべし
次回はこの時の山歩きのブログだよ
初体験 どしゃぶりテントのお話
どこに行ったかは次回のお楽しみ♪
テン場の幽霊さん?

あなたは山でこんな経験ありますか?
見えない何かを感じたこと

その日の夜 テントに叩きつける雨は
益々ひどくなっていった

バケツの水をひっくり返したような
雨の重みがテントにのしかかる


テントがペシャンコになるかも
あわや ひとちが危機一髪か

そんなことを 考えながら
シュラフに深々と潜り込む

雨で冷えた身体がまだ冷たい

それにしても ひどい どしゃぶり

ちがこさんの天気予報では
こんなに雨が降るはずなかったんだけどな

山の天気は予想外
雨音に混じって何か違う音が聞こえる

何の音かな?
しばらく じっと耳を澄ませ
雨音以外の音が何なのか確かめた

おかしい
んなわけないのに

横で疲れきった ひとしさんは
グーグーいびきをかいて眠っている


テントから顔出して確かめたら
雨でびちょ濡れになりそうだし
気になる 気になる 気になる・・・
眠れない 眠れない 眠れない 眠れない
眠れない 眠れない 眠れない 眠れない
うーん やっぱり眠れない

暗やみの中で ひとしさんに
そっと声をかけてみた

ひとしさん?
起きてる?
ふが

何ですか?
寝るの早いね

もう いびきかいてたよ

え?
私 いびきしてました?
で 何ですか?
あのさー
音がするんだけどね・・・
何の音ですか?
たぶん動物でもなく
人でもない・・・
え゛
じゃ いったい何ですか?
この日 小屋の裏側のテン場に
ひとちが以外のテントは三張しかなかった

天気のいい土日なら 混み合うテン場だけど
雨がガンガン降ってるからテントは少ない

ケチな ひとちがといえば
ここまで重たいザックを上げた以上 小屋泊など
選択するわけがなく 雨がガンガン降る中
大急ぎ 突貫工事で移動式住宅を建築した

テントを立てたのは階段状になっている
テン場の一番下から三番目の段

テン場の横につけられた登山道から入った
二つ目のスペースだ

どこにテントを張っても水たまりの中に
テントを張ることには変わりはないけど
できるだけ被害の少ない場所に張ったつもり


どしゃぶりのため 一端テントに入ったら
外に出るのは ほぼ不可能で
トイレに行きたくても小降りになるまで
がまんしなきゃいけない状況

たぶんこの先テントが増えることはないだろう
と 正直思った

テントに入ってからすでに三時間
外は暗闇
もしテン泊の人や小屋泊の人が近くにくれば
ヘッデンの明かりでチラチラとわかるはず


しかし そんな光はなく
テン場は暗やみの世界だ

なのに ちがこさんは感じるのだ

いるはずのない人の気配

で いったい何が聞こえるんですか?
うんとね

うちのテントの二つ下 一番下のスペースにね
いるわけよ

だから いったい何がいるんですか?
ハッ
 ハッ
ハッ ハッ
ハッ
って雨音に混じって人の荒い息使いと
ペチャペチャ テン場の中を歩き回る足音

幽霊さんかな?

え゛

それと横の登山道を小屋方向に階段を登っていく
登山靴のガボガボした音

大きなサイズの山靴みたいだよ

幽霊さんだと思うよ・・・

え゛

たぶん どっちも山の人みたいだけど

生きてる人じゃないことは確かだと思う

山で遭難とかして亡くなった人じゃないかな

え゛ ー

本当に聞こえるんですか?
うん

ちがこさんは どっちらかというと
そーゆーのに敏感ぢゃない

でもね 今夜は何故だか聞こえるのだ

・・・・・

大丈夫だよ

悪さするような人たちじゃなさそうだし
きっと混み合ったテン場には出ずらいとか?
今夜はどしゃぶりで人も少ないから
たまたま出てきたとか?
そうゆーもんですかね

それっきり ひとしさんは黙ってしまった


気になりつつも ひとしさんに話したので満足
早くテントを張る場所が決まればいいね
なんて思いながらいつの間にか深い眠りに入った

この話
信じるも信じないもあなた次第
真実が知りたければ どしゃぶりの日 このテン場に
テントを張って確かめてみるべし

次回はこの時の山歩きのブログだよ
初体験 どしゃぶりテントのお話

どこに行ったかは次回のお楽しみ♪
2014年07月30日
中年の証明♪ Ⅲ
2014/07/26
大変な山歩き第三弾!
鋸岳
(赤石山脈北部エリア)
全山行 418回

 鋸岳の情報はこちら
鋸岳の情報はこちら
 中年の証明Ⅰはこちら
中年の証明Ⅰはこちら
 中年の証明Ⅱはこちら
中年の証明Ⅱはこちら
標高 鋸岳 第一高点 2685m
天気 晴れ
晴れ
山行時間 14時間
〈コース〉戸台駐車場(4:30)-白岩堤防-角兵衛沢案内板-一合目-
大岩下ノ岩小屋-角兵衛沢ノ頭-第一高点(12:30-1:00)-ピストンで駐車場(6:30)
我が家のトイレのカレンダーには
こんな文句が書かれている
山や壁が与えられると
つい嬉しくなる
これを乗り越えたら
どんな幸せが待っているのかと
幸せって何だろ?
 真夜中12時半
真夜中12時半
二人同時に目が覚めた
少し早いですけど出発しますか?
うん
先週は あまり体調もすぐれなかったため
大変な山シリーズはお休みした
ホントのこと言うと
前回 笹山の山頂でぶっ倒れた ので
またあの時と同じ状態になるんじゃないかと
気が進まなかったのも事実
そんなこと言っちゃおれん
気を引き締め対策を練ることに
前回は ひとしさんに「お酒が悪いんですぅ」って
無理やり休肝日を作らされた
それも週に二日

素直に従ったものの ちがこさん的には
どう考えてもお酒より 山で摂取する物が
足りないからだと思えて仕方ない
そこで今回は ポカリスエット・飲用ゼリー・
塩分補給のためのタブレットなどを準備し万全を期す
これでよし
戸台までは運転手のひとしさんには申し訳ないが
フガフガしながらの3時間半
ようやく夜が明けたころ
たくさんの乗用車が待機している戸台口へ
スゴイですね
これって北沢峠にバスで入る人たちの車ですよね
うん
あたしたちは 近くの駐車場から
歩きだから問題ないよ
大丈夫ですか?
ちゃんと駐車場あるんでしょうね?
うじゃうじゃと会話しながら
細くなった道を河原方向へ下った
戸台の駐車場は河原の一部みたいだ
車は数台停まっているのみ
実に静か
監視小屋の看板には山に入る注意が書かれ
今日登る山が一般路ではないことを強調している

そんなに危険なんですか?
山調べをしていない ひとしさん不安そう
戸台川の河原からは山が
じっとこちらを見ているように見えた
こいや ひとちが

山との戦いが今始まる

鎖のかけられたポールの横を通過
しばらくは未舗装のフラットな車道を歩く
頭痛い
ゲボゲボ・・・
久しぶりの早起きのためか
あまり体調がすぐれない ちがこさん
出がけに ひとしさんに言われたこと
体調が悪いのに無理に登っても
途中で下山することになり兼ねません
自分の足で登って下山できないなら
最初から行かない方がいいですよ
なんて冷たいおじさん
じゃなかった 愛するマイダーリン
ちがこさんだって好きで
体調不良になるわけじゃない
いいもん
頭痛薬飲んだからすぐによくなるもん
強情だねぇ~
ひとちは心配してるんだよ
わかってるしぃー

鋸岳は 北沢峠までバスでアクセスし
甲斐駒経由で鋸に移動し下山するパターンが多い
一泊二日山行
日帰りのピストンや周遊で別コースから
下る人は少ないみたいだ
2時間以上も延々と足場の悪い河原を歩く

蛇行して流れる川を右に左にと何度も渉渡し
角兵衛沢の登山口まで歩くってのは
帰路の駐車場までの同じ河原歩きを考えると
気持ちが萎えてくるのもウソじゃない
ちゃんとした登山道があるわけでもない河原を
延々と歩き続けるわけだから

ようやく角兵衛沢の入口に到着

最後の渉渡
が 簡単にはいかない
意外と川幅があるのと 流れが速いのと
ハマればふくらはぎくらいの水位ときた
さ~てとどうする
ひとちが?
しばし ひとしさんは周辺を物色
なんとか渡れるポイントを探ってみたものの
やっぱり無理がある
同時期に出発した単独のお姉さんは
ささっと準備してきた川用のブーツに履き替え
颯爽と川を渡って行った

同時期に出発したおじさんもいたが
渉渡に失敗したのか 渡った先で荷物を広げ
水没した中身の整理中?
(このおじさんはその後 そのまま敗退したようです )
)

じゃ 行きますよ
そう言うと ひとしさんは飛んだ

片足若干突っ込んだものの
なんとか渉渡成功
やるじゃん ひとち
まあね
次は ちがこさんの番です
思いっきり飛んで下さい
思い出してしまった笊の沢
これから山登りが始まるのに
水槽みたいにグジュグジュの山靴で
山を登るわけにはいかん
でも 渡るの無理そう

ということで 少しでも水位が下がるように
大きな石を何度も運んでとび石を作ることにした


いつまでも作っているわけにいかないので
意を決して とび石に乗っかった
ずる
ボテ

足を乗せたとたん 積んだはずの石は崩れ
見事に水の中に足を突っ込んだ
最初っから水の中に
足突っ込めばよかったね
うるさい
沢を渡りすぐ山にとりつく
入口付近にはこのような看板

枯葉が積もっている山はやや不明瞭
その上 薄暗いときた
赤テープを追って登ること数分
途中 道を見失いウロウロすること数分
タイムロスはあったものの
無事正規ルートにのった
山を登り始めたころ 頭痛薬が効いたのか
すっかり 体調がよくなり元気に山を登っていく
うが うが
うが うが
うが
今日は 調子いいや
体調不良にならないように
気をつけよぉ~っと
振り返って驚いた
ひとしさんが遠い

ノロノロと苦しそうに山を登ってくる

ありゃ? どうしたの?
具合わるい??
心臓がバクバクして苦しいですぅ
出だしだから仕方ないか
と最初は思った
ところが いつもの十八番症状が

ゲボゲボ
おえーっ

よっぽど苦しいのかな?
ちがこさん荷物少し持ってあげなよ
2リットルのポカリが ちがこさんの
ザックに移動した
陽があたらない山でも登りは暑い
ダラダラ流れ落ちる汗と戦いながら
水分補給を欠かさず ひたすら登る

心の中で思った
出だしに言われた言葉
そのまんま返してやるわ!
うはは!!
とはいえ 苦しいのは可哀想
これからもっと大変なのに大丈夫なんだろうか?

シャクナゲの林を通過

右手側に大きなガレ場が見えた
 角兵衛沢のガレ
角兵衛沢のガレ
目の前に巨大な岩の壁が現れた
大岩下ノ岩小屋があるという岩壁だ

登山道から外れ 少し下った場所に
テントを張る場所と水場があるそうだが
今日は日帰り強行なので素通り
ようやく樹林帯が終わり
やや荷物が軽くなったせいか
ひとしさんも元気になってきた

ヘルメット装着

このガレ場は崩れやすく
手や足をかけた場所はそのまま崩れてしまう
赤ちゃんの頭ほどの石から 座布団級の石が
不安定に何層も積み重なり どうやって登って
いいのかわからない
見ているだけじゃ登れないので
ともかく登れそうな場所を探して登るしかない

一歩進めば 二歩分崩れ
三歩進めば 六歩分崩れ
なんじゃい
ちっとも前に進まないじゃん
だから2時間半もかかるんだね
そうみたいですぅ

振り返ると西側の景色が開けていた

ともかく登りにくいガレ場
ガラ ガラ ガラ ガラ
大きくガレが崩れる音が山に鳴り響いた
下ってきた登山者がラークさせた音
このガレ場の石は
すべてが浮石
と想像していただきたい
ガレ場には赤テープは ほとんどなく
正しいコースっていうのはない

石をラークさせないようにしなきゃいけない上
他の登山者が落とす石から身を守るためにも
ヘルメットは必需品
なるべく登山者とかぶらないコースをとって
危険回避するしかないので注意
細かいザレ場のような場所は悲惨で
四つん這いにならないと登れない

なんとかなんないのかね?

なんともならんのよ

雲がわいてきた

こっちに来ますよ
山頂までガスが早いか?
ひとちがが早いか?
こんな赤ペンキを見つけると
当たりくじを引いたみたいな幸せな気分になれる

そりゃ ちがこさんだけだよ
ありゃ? そう?
ガレ場の横移動はもっと大変

身動きがとれないほど
ガレが崩れていく

ようやく青い空が近づき
ガレ場も終盤かと思われた

そして目の前には

見上げると目がまわりそう

ひとちも続け!
おー

とうとう角兵衛沢のガレ場を登りきった

ガレ場の登りで 変な所に力が入ったためか
手足すべてのパーツがヨレヨレ
最後の力をふりしぼって
第一高点の最後の登りを進んでいく

が ここはナイフリッジ
右側は大きく崖になっている
左は低木があるので身体を寄せて
稜線から落ちないように注意
細い稜線は雨風の強い日や雪なら
更に怖さは倍増するに違いない
くわばら くわばら

とうとう念願の山頂に

登りに費やした7時間半
実に大変な山であった
誰もいない山頂
二人で登れた喜びを分かち合う

気が付けば こんなに高い場所
難山として渋っていた山のピークに
今立つことができた
で 景色はどうなの?

ガスに負けた
ガスがなければ360度の大パノラマの
はずなんだけどね・・・
本来なら第二高点経由で下山したいけど
時間的にも体力的にも これが限界

いいんですぅ ここまでで

まだまだ遊んでいたい所だけど
下山にも時間がかかるので
そろそろおいとますることに

ピークを下り始めると ガスのヤローは
意地悪にも山頂付近から通過していった

すきっと出た青空と景色を楽しみながら
角兵衛沢ノ頭に戻る



さ~てと
大変なガレ場を今度は下らなきゃいかん

足をおけば崩れすっこける

こーゆー場合は三点確保ではなく
お尻も含めて五点確保

下から登ってくる登山者がいないことを
確認しながらゆっくりと下るしかない

それでも容赦なく岩はラークし
恐ろしい音をたてながらゴロゴロと落ちていくのだ

ちょっと気を抜けば
まるでガレ場のすべり台みたいなことになる

ヤバい ヤバい

口から出るのはこの言葉のみ

ガレ場の脇に生えている木も
申し訳ないが利用させてもらう

それでも留まることを知らないガレ場
ガラ ガラ ガラ


ガレ場の傾斜が落ち着いたころ
ようやく立って歩くことができた

大岩から 暗い樹林帯に突入

朝 必死で登った道は
ガレ場を下った後の足に優しかった
それでも延々と下る登山道は尋常なく長く
下っても下っても時間がかかる
4時をまわったころ ようやく戸台川に出た
川岸ではテントを張った登山者が数名
ひとちがが下って行くと
これから帰るの?
日帰り?
よくやるねー
と一言
帰りの渉渡ポイントは浅瀬を選んで
一気に渡ることにした

ちがこさん?
ジャブジャブ

川を渡って一息

登った山を下から眺めた

ここまででも 十分ヘロヘロだったけど
歩かにゃ帰れん ということで
河原を延々と歩いたよ

陽も沈みかけたころ
駐車場まで歩ききることができた
山梨百名山・三難山
すべて登頂

山や壁が与えられると
つい嬉しくなる
これを乗り越えたら
どんな幸せが待っているのかと
答えは 達成感
幸せってこのことかな?
ひとりで心の中で笑った
 この日の立ち寄り湯はこちら
この日の立ち寄り湯はこちら
高遠温泉 さくらの湯
ちょっとカルキ臭いけど泉質は悪くない温泉だよ
翌日・・・
笊の時よりはマシだけど

筋肉痛で 変な動きになってる ひとちががいた
大変な山歩き第三弾!
鋸岳
(赤石山脈北部エリア)
全山行 418回

 鋸岳の情報はこちら
鋸岳の情報はこちら
 中年の証明Ⅰはこちら
中年の証明Ⅰはこちら
 中年の証明Ⅱはこちら
中年の証明Ⅱはこちら
標高 鋸岳 第一高点 2685m
天気
 晴れ
晴れ山行時間 14時間
〈コース〉戸台駐車場(4:30)-白岩堤防-角兵衛沢案内板-一合目-
大岩下ノ岩小屋-角兵衛沢ノ頭-第一高点(12:30-1:00)-ピストンで駐車場(6:30)
我が家のトイレのカレンダーには
こんな文句が書かれている

山や壁が与えられると
つい嬉しくなる
これを乗り越えたら
どんな幸せが待っているのかと
幸せって何だろ?
 真夜中12時半
真夜中12時半
二人同時に目が覚めた

少し早いですけど出発しますか?
うん

先週は あまり体調もすぐれなかったため
大変な山シリーズはお休みした

ホントのこと言うと
前回 笹山の山頂でぶっ倒れた ので
またあの時と同じ状態になるんじゃないかと
気が進まなかったのも事実

そんなこと言っちゃおれん

気を引き締め対策を練ることに

前回は ひとしさんに「お酒が悪いんですぅ」って
無理やり休肝日を作らされた
それも週に二日


素直に従ったものの ちがこさん的には
どう考えてもお酒より 山で摂取する物が
足りないからだと思えて仕方ない

そこで今回は ポカリスエット・飲用ゼリー・
塩分補給のためのタブレットなどを準備し万全を期す

これでよし

戸台までは運転手のひとしさんには申し訳ないが
フガフガしながらの3時間半

ようやく夜が明けたころ
たくさんの乗用車が待機している戸台口へ

スゴイですね

これって北沢峠にバスで入る人たちの車ですよね

うん
あたしたちは 近くの駐車場から
歩きだから問題ないよ

大丈夫ですか?
ちゃんと駐車場あるんでしょうね?
うじゃうじゃと会話しながら
細くなった道を河原方向へ下った

戸台の駐車場は河原の一部みたいだ

車は数台停まっているのみ

実に静か

監視小屋の看板には山に入る注意が書かれ
今日登る山が一般路ではないことを強調している


そんなに危険なんですか?
山調べをしていない ひとしさん不安そう

戸台川の河原からは山が
じっとこちらを見ているように見えた

こいや ひとちが


山との戦いが今始まる


鎖のかけられたポールの横を通過

しばらくは未舗装のフラットな車道を歩く

頭痛い

ゲボゲボ・・・
久しぶりの早起きのためか
あまり体調がすぐれない ちがこさん

出がけに ひとしさんに言われたこと

体調が悪いのに無理に登っても
途中で下山することになり兼ねません

自分の足で登って下山できないなら
最初から行かない方がいいですよ

なんて冷たいおじさん

じゃなかった 愛するマイダーリン

ちがこさんだって好きで
体調不良になるわけじゃない

いいもん
頭痛薬飲んだからすぐによくなるもん

強情だねぇ~
ひとちは心配してるんだよ

わかってるしぃー


鋸岳は 北沢峠までバスでアクセスし
甲斐駒経由で鋸に移動し下山するパターンが多い

一泊二日山行
日帰りのピストンや周遊で別コースから
下る人は少ないみたいだ

2時間以上も延々と足場の悪い河原を歩く


蛇行して流れる川を右に左にと何度も渉渡し
角兵衛沢の登山口まで歩くってのは
帰路の駐車場までの同じ河原歩きを考えると
気持ちが萎えてくるのもウソじゃない

ちゃんとした登山道があるわけでもない河原を
延々と歩き続けるわけだから


ようやく角兵衛沢の入口に到着


最後の渉渡

が 簡単にはいかない

意外と川幅があるのと 流れが速いのと
ハマればふくらはぎくらいの水位ときた

さ~てとどうする
ひとちが?
しばし ひとしさんは周辺を物色

なんとか渡れるポイントを探ってみたものの
やっぱり無理がある

同時期に出発した単独のお姉さんは
ささっと準備してきた川用のブーツに履き替え
颯爽と川を渡って行った


同時期に出発したおじさんもいたが
渉渡に失敗したのか 渡った先で荷物を広げ
水没した中身の整理中?
(このおじさんはその後 そのまま敗退したようです
 )
)
じゃ 行きますよ

そう言うと ひとしさんは飛んだ


片足若干突っ込んだものの
なんとか渉渡成功

やるじゃん ひとち

まあね

次は ちがこさんの番です
思いっきり飛んで下さい

思い出してしまった笊の沢

これから山登りが始まるのに
水槽みたいにグジュグジュの山靴で
山を登るわけにはいかん

でも 渡るの無理そう

ということで 少しでも水位が下がるように
大きな石を何度も運んでとび石を作ることにした



いつまでも作っているわけにいかないので
意を決して とび石に乗っかった

ずる

ボテ


足を乗せたとたん 積んだはずの石は崩れ
見事に水の中に足を突っ込んだ

最初っから水の中に
足突っ込めばよかったね

うるさい

沢を渡りすぐ山にとりつく
入口付近にはこのような看板


枯葉が積もっている山はやや不明瞭
その上 薄暗いときた

赤テープを追って登ること数分
途中 道を見失いウロウロすること数分

タイムロスはあったものの
無事正規ルートにのった

山を登り始めたころ 頭痛薬が効いたのか
すっかり 体調がよくなり元気に山を登っていく

うが
 うが
うが うが
うが
今日は 調子いいや

体調不良にならないように
気をつけよぉ~っと

振り返って驚いた

ひとしさんが遠い


ノロノロと苦しそうに山を登ってくる


ありゃ? どうしたの?
具合わるい??
心臓がバクバクして苦しいですぅ

出だしだから仕方ないか
と最初は思った

ところが いつもの十八番症状が


ゲボゲボ
おえーっ


よっぽど苦しいのかな?
ちがこさん荷物少し持ってあげなよ

2リットルのポカリが ちがこさんの
ザックに移動した

陽があたらない山でも登りは暑い

ダラダラ流れ落ちる汗と戦いながら
水分補給を欠かさず ひたすら登る


心の中で思った

出だしに言われた言葉
そのまんま返してやるわ!
うはは!!
とはいえ 苦しいのは可哀想

これからもっと大変なのに大丈夫なんだろうか?

シャクナゲの林を通過


右手側に大きなガレ場が見えた

 角兵衛沢のガレ
角兵衛沢のガレ目の前に巨大な岩の壁が現れた

大岩下ノ岩小屋があるという岩壁だ


登山道から外れ 少し下った場所に
テントを張る場所と水場があるそうだが
今日は日帰り強行なので素通り

ようやく樹林帯が終わり
やや荷物が軽くなったせいか
ひとしさんも元気になってきた


ヘルメット装着


このガレ場は崩れやすく
手や足をかけた場所はそのまま崩れてしまう

赤ちゃんの頭ほどの石から 座布団級の石が
不安定に何層も積み重なり どうやって登って
いいのかわからない

見ているだけじゃ登れないので
ともかく登れそうな場所を探して登るしかない


一歩進めば 二歩分崩れ
三歩進めば 六歩分崩れ
なんじゃい
ちっとも前に進まないじゃん

だから2時間半もかかるんだね

そうみたいですぅ


振り返ると西側の景色が開けていた


ともかく登りにくいガレ場

ガラ ガラ ガラ ガラ
大きくガレが崩れる音が山に鳴り響いた

下ってきた登山者がラークさせた音

このガレ場の石は
すべてが浮石
と想像していただきたい

ガレ場には赤テープは ほとんどなく
正しいコースっていうのはない


石をラークさせないようにしなきゃいけない上
他の登山者が落とす石から身を守るためにも
ヘルメットは必需品

なるべく登山者とかぶらないコースをとって
危険回避するしかないので注意

細かいザレ場のような場所は悲惨で
四つん這いにならないと登れない


なんとかなんないのかね?

なんともならんのよ


雲がわいてきた


こっちに来ますよ

山頂までガスが早いか?
ひとちがが早いか?
こんな赤ペンキを見つけると
当たりくじを引いたみたいな幸せな気分になれる


そりゃ ちがこさんだけだよ

ありゃ? そう?
ガレ場の横移動はもっと大変


身動きがとれないほど
ガレが崩れていく


ようやく青い空が近づき
ガレ場も終盤かと思われた


そして目の前には


見上げると目がまわりそう


ひとちも続け!
おー


とうとう角兵衛沢のガレ場を登りきった


ガレ場の登りで 変な所に力が入ったためか
手足すべてのパーツがヨレヨレ

最後の力をふりしぼって
第一高点の最後の登りを進んでいく


が ここはナイフリッジ

右側は大きく崖になっている

左は低木があるので身体を寄せて
稜線から落ちないように注意

細い稜線は雨風の強い日や雪なら
更に怖さは倍増するに違いない

くわばら くわばら

とうとう念願の山頂に


登りに費やした7時間半

実に大変な山であった

誰もいない山頂

二人で登れた喜びを分かち合う


気が付けば こんなに高い場所

難山として渋っていた山のピークに
今立つことができた

で 景色はどうなの?

ガスに負けた

ガスがなければ360度の大パノラマの
はずなんだけどね・・・
本来なら第二高点経由で下山したいけど
時間的にも体力的にも これが限界


いいんですぅ ここまでで


まだまだ遊んでいたい所だけど
下山にも時間がかかるので
そろそろおいとますることに


ピークを下り始めると ガスのヤローは
意地悪にも山頂付近から通過していった


すきっと出た青空と景色を楽しみながら
角兵衛沢ノ頭に戻る




さ~てと

大変なガレ場を今度は下らなきゃいかん


足をおけば崩れすっこける


こーゆー場合は三点確保ではなく
お尻も含めて五点確保


下から登ってくる登山者がいないことを
確認しながらゆっくりと下るしかない


それでも容赦なく岩はラークし
恐ろしい音をたてながらゴロゴロと落ちていくのだ


ちょっと気を抜けば
まるでガレ場のすべり台みたいなことになる


ヤバい ヤバい


口から出るのはこの言葉のみ


ガレ場の脇に生えている木も
申し訳ないが利用させてもらう


それでも留まることを知らないガレ場

ガラ ガラ ガラ


ガレ場の傾斜が落ち着いたころ
ようやく立って歩くことができた


大岩から 暗い樹林帯に突入


朝 必死で登った道は
ガレ場を下った後の足に優しかった

それでも延々と下る登山道は尋常なく長く
下っても下っても時間がかかる

4時をまわったころ ようやく戸台川に出た

川岸ではテントを張った登山者が数名

ひとちがが下って行くと
これから帰るの?
日帰り?
よくやるねー

と一言

帰りの渉渡ポイントは浅瀬を選んで
一気に渡ることにした


ちがこさん?
ジャブジャブ


川を渡って一息


登った山を下から眺めた


ここまででも 十分ヘロヘロだったけど
歩かにゃ帰れん ということで
河原を延々と歩いたよ


陽も沈みかけたころ
駐車場まで歩ききることができた

山梨百名山・三難山
すべて登頂


山や壁が与えられると
つい嬉しくなる
これを乗り越えたら
どんな幸せが待っているのかと
答えは 達成感

幸せってこのことかな?
ひとりで心の中で笑った

 この日の立ち寄り湯はこちら
この日の立ち寄り湯はこちら
高遠温泉 さくらの湯
ちょっとカルキ臭いけど泉質は悪くない温泉だよ

翌日・・・
笊の時よりはマシだけど


筋肉痛で 変な動きになってる ひとちががいた

2014年07月17日
中年の証明♪ Ⅱ
2014/07/12
大変な山歩き第二弾!
笹山 (黒河内岳)
(赤石山脈南部エリア)
全山行 416回

 笹山(黒河内岳)の情報はこちら
笹山(黒河内岳)の情報はこちら
 大変な山歩き第一弾はこちら
大変な山歩き第一弾はこちら
標高 南峰 2717.6m 北峰 2733m
天気 晴れ
晴れ
山行時間 11時間30分
*内、山頂で倒れていた時間 1時間30分
〈コース〉自宅(2:00)-奈良田温泉駐車場(4:30)-吊橋-トンネル通過(迷)-
第二発電所登山口(5:00)-ダイレクト尾根へ-水場/1603m(7:00)-テン場/2300m-
南峰-(9:30-9:40)-北峰(9:50-11:30)-ピストンで駐車場(4:00)
4年ぶりに髪を切った
腰丈ほどの長さ
伸びた髪にハサミが入る
バサ
髪が床に落ちた瞬間
暑い夏の扉が開いた
ひとちがの持っている2009年版の「山と高原地図」には
ダイレクト尾根コースの記載がない
現在の地図には破線ルートとして記載はあるが
破線ルートゆえ コースタイムの記載もない

これじゃ
役立たずぢゃん
こーゆー場合 山友たちの記録を
参考にに登るしかないわけで
コースタイムって 個人差あるよね
あまり参考になるとは思えないけど
まぁね
果たして日没までに
下山できるのか ひとちが?
奈良田温泉の駐車場に到着
2007年の夏 白根三山を縦走した時に
車を停めた場所だ
バカに混んでますね
連休ともなれば混雑していても
何の不思議もない
今日はフツーの土曜日
特に天気もすこぷるいいってわけでもない
おかしいですね
でも車停められてよかった
横で出発準備をしている おじさんが教えてくれた
昨日の台風で芦安の林道が崩れて
広河原へは奈良田側からしか入れないからだよ
へぇー
そうなんですかぁー
妙に納得
ひとちがは ウハウハだった
何故ならば
本日登るお山は
バスに乗らなくてもいい
奈良田湖の真ん中にかかる吊橋を渡り

ちがこさんが 一度はヨロけて
足を突っ込むであろう渉渡地点

私先に行きますね
そう言うと ひとしさんはピョンピョンと
石の上を軽やかに渡って行く
あれ ひとち行っちゃったよ
ちがこさんは行かないの?
え゛?
行く! 行く!

ここは 過去 〇むちゃんが落ちたという
伝説の渉渡地点
だよね 〇むちゃん?
ちがこさんも落ちない保障はない
落ちるかも・・・
落ちるかも・・・
バクバク高鳴る鼓動
自分に言い聞かせた
笊の沢よりマシじゃん
そう そう

渡りきるとトンネルが目の前にある

ここを通過すればいいんですか?
いつものごとく 何の山調べもしていない
ノーテンキな ひとしさん
入口には鎖が張られ「立ち入り禁止」の
赤い看板がぶらさがっている
黒くブキミに口を開けたトンネル
ありゃ? トンネルを通過するなんて
誰かの記録にあったっけかな?
まったく記憶にない
ふと横を見ると
こんなもの

あ~
「電気つけろ」ってことね
じゃ 進もうかっ!
ちがこさん ちがこさん
本当に通過していいの?
「立ち入り禁止」だよ
いいの! いいの!
 パチン
パチン
スイッチを入れると
更に気味悪いトンネル

速足で通過
ポンと出た場所は

なんじゃい
これじゃ せっかく渡った湖を
また渡り返しちゃったじゃん
横には 額に怒りマークの
浮き出た ひとしさん
「立ち入り禁止」って看板があるんだから
違うんじゃないかと言ったのに
まぁ まぁ

Uターン
正規ルートのある第二発電所の横から
ちょっと暗い登山口に向かった

ここからが勝負
登山口の標高は750mほど
山頂の標高は2700mちょいだから
2000m近く登り続けるってことになる
山頂まで どれほどの時間で
到達できるんだろ
大丈夫? ひとちが?
全然大丈夫じゃないですぅー
ちがこさんのノロノロ歩きで
日没までに本当に下山できるのか?

山の中腹にある発電所施設の最高点までは
植林帯に鉄の手すりがジグザグにつけられている
それでも急登に変わりはない

暗い植林帯を登りきると
すてきな緑の山が待っていた
いいじゃん♪

うかれポンチキで登っていく
この先 瀕死の状態になることを
ちがこさんは まだ知らない

すっかり尾根らしくなった明るい登山道を
所々にある赤テープを確認しながら登る
ボトボトと尋常なく汗が落ちる
暑いねぇー
通常 暑くてもあまり汗をかかない
ちがこさんだが 今日は違う
滝のような汗
しばらく登っていくと
事態が急変した
先を歩く ちがこさんの様子が
なんだかおかしい

あれ? どうしたんですか?
もう疲れたんですか?
覗き込むように
ひとしさんが声をかけた
ん
なんか 心臓バクバクするし
息も苦しいし
ヤバくない ひとち!
出だしから こんなんじゃ
ハァ ハァ
ハァ ハァ
ハァ
1603mの第一ポイントの
水場入口に到着

ここまで2時間
山頂はまだまだ遠い
これじゃ ちがこさん登りきれないよ
敗退したほうがいいんじゃない?
どうしましょう
ペースが遅い上 少し歩いては立ち止まり
すぐに休憩したがる ちがこさん

止まらないで進んで下さい
足取りの重い ちがこさんを前に
イライラする ひとしさん
夏の暑い太陽がサンサンと樹林帯の中に照りつけ
気温はどんどん上昇していく

あぢぃ~
水分をとって下さい
熱中症になるといけないですから
ハァ ハァ
ハァ ハァ
ハァ
2100mの赤テープまで登った

なんでそんなに苦しいんですか?
お酒の呑みすぎです
休肝日を作りましょう
なんでお酒のせいにするかな
お酒のせいじゃないもん
ブツブツ・・・
納得のいかない ちがこさん
少し歩いては休み
また止まっては水分補給

いつになったら山頂に到達できるんだろ?
イラ イラ イラ イラ
右手側の尾根は 農鳥岳に続く
大唐松尾根

雲がかかっているのは
きっと北岳だよね

いつもなら どんなに大変でも
辛くっても 楽しい登り
山頂からのすばらしい景色を想像して
ワクワクする気持ちを抑えきれない貴重な時間
しかぁ~し
今日は違う
たった100mの標高を上げるのも苦痛で
地面とひたすらにらめっこ
はぁ。。。

ちがこさん 大丈夫?
もうヤメたら?
うるさい
登るよ
強情な

標高が上がるとガスが山を覆った
もしかして展望ダメかもしれませんね
体調が悪い上 無理してまで登ろうっていうのに
景色までダメだったら頭にくる
テンション下がりまくり

かすかに山鈴の音が聞こえた
山頂から下ってきた おじいちゃん
本日初めてすれ違う 貴重な登山者
山頂はガスですか?
いや いいよ
南峰はダメだけど 北峰はいいよ
すっごくいい
ひゃぁ~
そうなんですか
がんばろっと
シャクナゲが出てきたら
あと20分くらいで山頂だよ
がんばってね
テンションアップ
とはいえ 登山道はどんどん狭くなり
倒木も多く登りにくい

体調は回復するどころか
めまいはするし ヨロけて倒れそう
ヤバい ヤバい
しっかりしなくっちゃ
後方から あまりのノロさに
ひとしさんがブウたれる
お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです
お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです
お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです
とうとう ちがこさんがキレた
う うるさいな
週に二回 休肝日入れるよ
うじゃうじゃ言わないで
お酒ヤメる気はないんだね
じゃ 今週から月・木で
ブツブツ。。。
ハァ ハァ
ハァ ハァ
ハァ

ガスから出た
とたんに ギラギラした太陽が照りつける
ピンクのイワカガミが群生
山頂はもう近い

青空が眩しい南峰に到着
周囲は背丈ほどの木で囲まれていた

よかったですぅー
ここまで5時間半で登れました
不調の割に早い時間に到達できたので
ひとしさんは ルンルン
あれ?
ちがこさんは?

あらあら 座りこんじゃって
ゲボゲボ
おえーっ
でたぁーっ!
ひとちの十八番
って 今日は ちがこさんかい
少しは楽になりましたか?
まぁね
まったく最悪だよ これって笠ヶ岳に登った時と
大して変わんないくらい悲惨な感じ
再び立ち上がると ヨロヨロしながら
今度は北峰に向かった

居心地よさげな山頂のテン場を通過
展望のいい北峰に

先に到着した ひとしさん
ご満悦

ひとち
景色見せてよ
わかりましたぁ~




スゴいでしょ!

もしかしなくて
あの死体みたいなの?
そうですぅ
汗臭いタオルを地面に敷くと
ゴロリと横になった
もう動けましぇん

あ゛―
悲惨だね
ダウンしたのは仕方ないとしても
実は もっと悲惨なことがあったのだ
この時期山頂には ハエとアリがいっぱいいた
ちがこさんを襲ったのは
集団ヤロー人噛みアリ

クロヤマアリ
亜高山帯の陽当りのいい場所に生息
黒い影は敵とみなし攻撃する。
本日来ている服は黒
敵と判断されても仕方ないか

やつらは容赦なく 倒れている
ちがこさんの服の隙間から侵入
瀕死状態で動けないことをいいことに
噛みたい放題
噛まれ続けること1時間半
噛み跡は 赤くふくれ かゆいのなんの
まるで麻疹みたいじゃん
悪かったね
前年まで ブユ・山ヒル・山ダニの餌食
そして今年は 人噛みアリの餌食となった
ここまでアリに噛まれたのは初体験
そー考えると
ブランコ毛虫は見た目はどうであれ
無害でしたね
そーゆーことじゃなくって
で ちがこさんが攻撃されてる間
ひとちは何してたの?
えっ えっ
えっ
かっちょいい私の撮影ですぅ~
見せましょうか?
い いいよ
見たいでしょ?
べ 別に
じゃ~ん

きたぁ~っ

かっちょいい

まだまだぁーっ

とりゃぁーっ

あれ?
もういいんですか?
山頂に誰もいなくてよかったね
間違いなく変人だと思われてたと思うよ
1時間半後
ようやく ちがこさんが起き上った

下山できますか?
うん
歩けるし 帰るよ

南峰に別れを告げ
一気に2000m近い標高を下る
よかったね ちがこさん
元気になって
うん

忘れないで下さいよ
私との約束 休肝日!
わかってるしぃー
登りの時は苦しくて
周囲を見回す気力もなかった

下山時にみつけた
ナラッシー

白いランデブーしているひとたちを
眺めながら下った

足の裏が痛くなるころ
登山口の第二発電所に到着

夏の扉が開いたとたん
辛く苦しい山歩きとなってしまった
それでも
ヨレた中年でもやる気さえあればなんとかなる
ということを証明できたような気がする・・・
by ちがこさん
沢の水で 汗ダクの顔を
ジャブジャブ洗う
さっぱりしましたぁ~

いい顔してるよ ひとち
 この日の立ち寄り湯はこちら
この日の立ち寄り湯はこちら
奈良田温泉 女帝の湯
田舎の農家のような レトロな雰囲気の温泉です
源泉を飲むこともできるよ
大変な山歩き第二弾!
笹山 (黒河内岳)
(赤石山脈南部エリア)
全山行 416回

 笹山(黒河内岳)の情報はこちら
笹山(黒河内岳)の情報はこちら
 大変な山歩き第一弾はこちら
大変な山歩き第一弾はこちら
標高 南峰 2717.6m 北峰 2733m
天気
 晴れ
晴れ山行時間 11時間30分
*内、山頂で倒れていた時間 1時間30分
〈コース〉自宅(2:00)-奈良田温泉駐車場(4:30)-吊橋-トンネル通過(迷)-
第二発電所登山口(5:00)-ダイレクト尾根へ-水場/1603m(7:00)-テン場/2300m-
南峰-(9:30-9:40)-北峰(9:50-11:30)-ピストンで駐車場(4:00)
4年ぶりに髪を切った

腰丈ほどの長さ
伸びた髪にハサミが入る

バサ
髪が床に落ちた瞬間
暑い夏の扉が開いた

ひとちがの持っている2009年版の「山と高原地図」には
ダイレクト尾根コースの記載がない

現在の地図には破線ルートとして記載はあるが
破線ルートゆえ コースタイムの記載もない


これじゃ
役立たずぢゃん

こーゆー場合 山友たちの記録を
参考にに登るしかないわけで

コースタイムって 個人差あるよね

あまり参考になるとは思えないけど

まぁね

果たして日没までに
下山できるのか ひとちが?
奈良田温泉の駐車場に到着

2007年の夏 白根三山を縦走した時に
車を停めた場所だ

バカに混んでますね

連休ともなれば混雑していても
何の不思議もない

今日はフツーの土曜日
特に天気もすこぷるいいってわけでもない

おかしいですね

でも車停められてよかった

横で出発準備をしている おじさんが教えてくれた

昨日の台風で芦安の林道が崩れて
広河原へは奈良田側からしか入れないからだよ

へぇー
そうなんですかぁー

妙に納得

ひとちがは ウハウハだった

何故ならば
本日登るお山は
バスに乗らなくてもいい

奈良田湖の真ん中にかかる吊橋を渡り


ちがこさんが 一度はヨロけて
足を突っ込むであろう渉渡地点


私先に行きますね

そう言うと ひとしさんはピョンピョンと
石の上を軽やかに渡って行く

あれ ひとち行っちゃったよ

ちがこさんは行かないの?
え゛?
行く! 行く!

ここは 過去 〇むちゃんが落ちたという
伝説の渉渡地点
だよね 〇むちゃん?
ちがこさんも落ちない保障はない

落ちるかも・・・
落ちるかも・・・
バクバク高鳴る鼓動

自分に言い聞かせた

笊の沢よりマシじゃん

そう そう


渡りきるとトンネルが目の前にある


ここを通過すればいいんですか?
いつものごとく 何の山調べもしていない
ノーテンキな ひとしさん

入口には鎖が張られ「立ち入り禁止」の
赤い看板がぶらさがっている

黒くブキミに口を開けたトンネル

ありゃ? トンネルを通過するなんて
誰かの記録にあったっけかな?
まったく記憶にない

ふと横を見ると
こんなもの


あ~

「電気つけろ」ってことね

じゃ 進もうかっ!
ちがこさん ちがこさん
本当に通過していいの?
「立ち入り禁止」だよ

いいの! いいの!
 パチン
パチン
スイッチを入れると
更に気味悪いトンネル


速足で通過

ポンと出た場所は


なんじゃい

これじゃ せっかく渡った湖を
また渡り返しちゃったじゃん

横には 額に怒りマークの
浮き出た ひとしさん

「立ち入り禁止」って看板があるんだから
違うんじゃないかと言ったのに

まぁ まぁ

Uターン

正規ルートのある第二発電所の横から
ちょっと暗い登山口に向かった


ここからが勝負

登山口の標高は750mほど

山頂の標高は2700mちょいだから
2000m近く登り続けるってことになる

山頂まで どれほどの時間で
到達できるんだろ

大丈夫? ひとちが?
全然大丈夫じゃないですぅー

ちがこさんのノロノロ歩きで
日没までに本当に下山できるのか?

山の中腹にある発電所施設の最高点までは
植林帯に鉄の手すりがジグザグにつけられている

それでも急登に変わりはない


暗い植林帯を登りきると
すてきな緑の山が待っていた

いいじゃん♪

うかれポンチキで登っていく

この先 瀕死の状態になることを
ちがこさんは まだ知らない


すっかり尾根らしくなった明るい登山道を
所々にある赤テープを確認しながら登る

ボトボトと尋常なく汗が落ちる

暑いねぇー

通常 暑くてもあまり汗をかかない
ちがこさんだが 今日は違う

滝のような汗

しばらく登っていくと
事態が急変した

先を歩く ちがこさんの様子が
なんだかおかしい


あれ? どうしたんですか?
もう疲れたんですか?
覗き込むように
ひとしさんが声をかけた

ん
なんか 心臓バクバクするし
息も苦しいし

ヤバくない ひとち!
出だしから こんなんじゃ

ハァ
 ハァ
ハァ ハァ
ハァ
1603mの第一ポイントの
水場入口に到着


ここまで2時間
山頂はまだまだ遠い

これじゃ ちがこさん登りきれないよ

敗退したほうがいいんじゃない?
どうしましょう

ペースが遅い上 少し歩いては立ち止まり
すぐに休憩したがる ちがこさん


止まらないで進んで下さい

足取りの重い ちがこさんを前に
イライラする ひとしさん

夏の暑い太陽がサンサンと樹林帯の中に照りつけ
気温はどんどん上昇していく


あぢぃ~

水分をとって下さい

熱中症になるといけないですから

ハァ
 ハァ
ハァ ハァ
ハァ
2100mの赤テープまで登った


なんでそんなに苦しいんですか?
お酒の呑みすぎです

休肝日を作りましょう

なんでお酒のせいにするかな

お酒のせいじゃないもん

ブツブツ・・・
納得のいかない ちがこさん

少し歩いては休み
また止まっては水分補給


いつになったら山頂に到達できるんだろ?
イラ イラ イラ イラ
右手側の尾根は 農鳥岳に続く
大唐松尾根


雲がかかっているのは
きっと北岳だよね


いつもなら どんなに大変でも
辛くっても 楽しい登り

山頂からのすばらしい景色を想像して
ワクワクする気持ちを抑えきれない貴重な時間

しかぁ~し
今日は違う
たった100mの標高を上げるのも苦痛で
地面とひたすらにらめっこ

はぁ。。。

ちがこさん 大丈夫?
もうヤメたら?
うるさい
登るよ

強情な


標高が上がるとガスが山を覆った

もしかして展望ダメかもしれませんね

体調が悪い上 無理してまで登ろうっていうのに
景色までダメだったら頭にくる

テンション下がりまくり


かすかに山鈴の音が聞こえた

山頂から下ってきた おじいちゃん
本日初めてすれ違う 貴重な登山者

山頂はガスですか?
いや いいよ
南峰はダメだけど 北峰はいいよ

すっごくいい

ひゃぁ~
そうなんですか

がんばろっと

シャクナゲが出てきたら
あと20分くらいで山頂だよ
がんばってね

テンションアップ

とはいえ 登山道はどんどん狭くなり
倒木も多く登りにくい


体調は回復するどころか
めまいはするし ヨロけて倒れそう

ヤバい ヤバい
しっかりしなくっちゃ

後方から あまりのノロさに
ひとしさんがブウたれる

お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです
お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです
お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです
とうとう ちがこさんがキレた

う うるさいな

週に二回 休肝日入れるよ
うじゃうじゃ言わないで

お酒ヤメる気はないんだね

じゃ 今週から月・木で

ブツブツ。。。
ハァ
 ハァ
ハァ ハァ
ハァ

ガスから出た

とたんに ギラギラした太陽が照りつける

ピンクのイワカガミが群生

山頂はもう近い


青空が眩しい南峰に到着

周囲は背丈ほどの木で囲まれていた


よかったですぅー
ここまで5時間半で登れました

不調の割に早い時間に到達できたので
ひとしさんは ルンルン

あれ?
ちがこさんは?

あらあら 座りこんじゃって

ゲボゲボ
おえーっ

でたぁーっ!
ひとちの十八番

って 今日は ちがこさんかい

少しは楽になりましたか?
まぁね

まったく最悪だよ これって笠ヶ岳に登った時と
大して変わんないくらい悲惨な感じ

再び立ち上がると ヨロヨロしながら
今度は北峰に向かった


居心地よさげな山頂のテン場を通過
展望のいい北峰に


先に到着した ひとしさん
ご満悦


ひとち
景色見せてよ

わかりましたぁ~





スゴいでしょ!

もしかしなくて
あの死体みたいなの?
そうですぅ

汗臭いタオルを地面に敷くと
ゴロリと横になった

もう動けましぇん


あ゛―
悲惨だね

ダウンしたのは仕方ないとしても
実は もっと悲惨なことがあったのだ

この時期山頂には ハエとアリがいっぱいいた

ちがこさんを襲ったのは
集団ヤロー人噛みアリ

クロヤマアリ
亜高山帯の陽当りのいい場所に生息
黒い影は敵とみなし攻撃する。
本日来ている服は黒
敵と判断されても仕方ないか


やつらは容赦なく 倒れている
ちがこさんの服の隙間から侵入

瀕死状態で動けないことをいいことに
噛みたい放題

噛まれ続けること1時間半

噛み跡は 赤くふくれ かゆいのなんの

まるで麻疹みたいじゃん

悪かったね

前年まで ブユ・山ヒル・山ダニの餌食
そして今年は 人噛みアリの餌食となった

ここまでアリに噛まれたのは初体験

そー考えると
ブランコ毛虫は見た目はどうであれ
無害でしたね

そーゆーことじゃなくって

で ちがこさんが攻撃されてる間
ひとちは何してたの?
えっ
 えっ
えっ
かっちょいい私の撮影ですぅ~

見せましょうか?
い いいよ

見たいでしょ?
べ 別に

じゃ~ん

きたぁ~っ


かっちょいい


まだまだぁーっ


とりゃぁーっ


あれ?
もういいんですか?
山頂に誰もいなくてよかったね

間違いなく変人だと思われてたと思うよ

1時間半後
ようやく ちがこさんが起き上った


下山できますか?
うん
歩けるし 帰るよ


南峰に別れを告げ
一気に2000m近い標高を下る

よかったね ちがこさん
元気になって
うん


忘れないで下さいよ
私との約束 休肝日!
わかってるしぃー

登りの時は苦しくて
周囲を見回す気力もなかった


下山時にみつけた
ナラッシー


白いランデブーしているひとたちを
眺めながら下った


足の裏が痛くなるころ
登山口の第二発電所に到着


夏の扉が開いたとたん
辛く苦しい山歩きとなってしまった

それでも
ヨレた中年でもやる気さえあればなんとかなる
ということを証明できたような気がする・・・
by ちがこさん
沢の水で 汗ダクの顔を
ジャブジャブ洗う

さっぱりしましたぁ~


いい顔してるよ ひとち

 この日の立ち寄り湯はこちら
この日の立ち寄り湯はこちら
奈良田温泉 女帝の湯
田舎の農家のような レトロな雰囲気の温泉です

源泉を飲むこともできるよ

2014年07月04日
しらびそ高原へ♪ 後編
2014/06/29
しらびそ峠を挟んで北側の山へ♪
奥茶臼山
(赤石山脈南部エリア)
全山行 415回

 奥茶臼山の情報はこちら
奥茶臼山の情報はこちら
 前編の山歩きはこちら
前編の山歩きはこちら
標高 前尾高山 2089m 尾高山 2212.4m 奥尾高山 2266m
岩本山 2269m 奥茶臼山 2473.9m
天気 晴れのち
晴れのち 曇り
曇り
山行時間 8時間45分
〈コース〉しらびそ峠(6:30)- 前尾高山-尾高山-奥尾高山-岩本山-
奥茶臼山(10:30-11:00)-北側展望地-ピストンでしらびそ峠(2:45)
雨上がりの山はすてき
しっとりとした森
苔むした原生林
命の息吹きを感じる山
後編
朝だぁー
夜半から早朝にかけて まるでスコールのような
雨が車のボンネットに叩きつける音で目が覚めた
(ひゃぁ~っ )
)
時刻は4時半
どうする?
こんなじゃ山に登れないよね
どうしますぅ?
このまま敗退しますか?
うじゃうじゃとシュラフの中で
テンションが下がる ひとちが
外に出たくても 雨が強くてドアを開ければ
びちょ濡れになりそうなほど
5時半
ピタリと雨が上がった
恐る恐る外に出て峠の柵の先を眺めてみれば
雲海の中から南アルプスの山々が顔を出している
(わ~お )
)

行けるじゃん!
いこう! いこう!

雨上がりを待っていたかのように
峠には登山者たちが次々と到着
いそげ! いそげ!
マケジと峠から出発♪

まだ霧の残る幻想的な森に入っていく

登り始めると霧が晴れた
とたんに美しい緑の森が目の前に
きゃぁ~
きれい

しとった森は 雨上がりの匂いがする

尾高山まではハイキングコースなので
とてもよく整備されていた

少し進むと道が二手にわかれる
ビューポイントコースに進むと
東側の景色を楽しむことができるのだ
目の前には南アルプス南部の山々
右端には ハイランドしらびその赤い屋根

きれいですねぇ~
1時間ほどで 前尾高山の山頂に到着
樹林帯の中なので展望はない

コースは奥茶臼山まで
尾根伝いに4つの山を越えてく
標高差はそれほどないとはいえ
登ったり下ったりとアップダウンは避けられない
(はぁ。。。)
展望はきかないけれど
苔むした森はやっぱりすてき
なんてきれい

思わず何度も足が止まる
昨日の雨で山は洗われ
たくさんのキノコがにょきにょきと
朽ち落ちた倒木の苔の中から顔を出していた

光が差し込む不思議な空間

展望のきく場所に出た
青空に南アルプスを眺めることができる
数少ないポイントのひとつ

一般的なハイキング道のゴールは尾高山
ごつごつとした岩の上に山頂標識

この先は奥茶臼までの登山道
ハイキング道のようなわけにはいかない
赤テープに導かれ
シダのジャングルをズンズン進む

30分ほどで奥尾高山のピークに達した
ここも樹林帯の中
(ぶぅ。)

黒ゴマと塩を混ぜただけのおむすびも
山で食べると美味しいもんだ
ご飯が硬くて アゴが疲れます
でっかしぃー

ブツブツ・・・
悪かったね
次回は水加減間違えないから
すぐ先には奥茶臼山が見える場所がある
シラビソ峠からは深すぎて見えないのだ
手前に見えるのが岩本山

所々につけられた奥茶臼山までの距離を示す看板は
文字が欠け古さを感じさせる

ゆるやかに下っていくと
森の中に小さな池

ようやく終盤の岩本山

岩本山を過ぎると雰囲気が一転
平坦な明るい尾根 それも広い
登山道はクネクネと蛇行している

その先は

いやぁー
まいった まいった

なんでこんなに倒れているんだよー と
文句を言いたくなるほど道は倒木で塞がれていた
(ぬぉーっ )
)

前進するためには
イヤでも木を乗り越えなきゃ進めん
この辺りは地図上で 「迷いマーク」 がつけられている場所
「迷う」 というより 「倒木ひどし」 の方がピッタリだと思った

それでもしっかり赤テープを追わないと
道迷いし兼ねないので要注意
ここは南アルプス前衛の山
赤石岳の近くともなると石も赤い

陽当りのいい草地に出た
ようやく目的の奥茶臼山が目の前に

ひと登りすると山頂に到着
ここもまた 思いっきり樹林帯の中だ
(ぶぅ。)

先を歩いていた登山者が休憩中
スパッツを脱ぎ 荷物は散乱
ここまで随分時間かかったでしょ
もう少し早く着けると思ったんだけどな
そういえば
出発時峠の案内板見てたっけ
おじさんは地図を持参していないようだ
あのぉー
この先に展望が開けた場所があるみたいですよ
5分も進めば 快適であろう展望地
お疲れのおじさんにはどうでもいいみたいだ
もういいや
無理やりおすすめするのも何なんで
踏み跡がある北方向の展望地に向かう

またかい
伐採された山斜面の下には
作業小屋でもあったのだろうか?
北側に位置する前茶臼山が
じーっとこっちを見ていた

下まで下るより
ここの方が景色がよさそうですね
そう言うと ひとしさんはドカっと
山斜面の安定のいい石に腰をかけた
じゃぁ 下まで行って
ちょっと探検してくるね
私はここで待ってます
ちがこさんは
今日も懲りずに冒険に出かける

足場の悪い山斜面を下ると案の定
そこには小屋の廃材が

作業小屋跡の廃材は長い年月で
ボロボロに風化しつつある

それれも自然に返らない物もたくさん散乱したまま

せっかくの展望地からの景色も
感動が半分になってしまったような気がした
(はぁ。。。)

シラビソ峠からの登山道ができるまで
奥茶臼山に登るためには 青木林道を10キロ以上
歩いて登山道にとりつくコース
もしくは 栂村山・前茶臼山経由ルートのどちらか
新しく整備された登山道って
ホントありがたい
森に戻れば緑が待っている

あまり眺望を得ることができない尾根道も
こんなステキな緑の回廊

またいつの日か歩いてみたい
雨上がりの匂いのする心地よい山を
 この日の立ち寄り湯はこちら
この日の立ち寄り湯はこちら
道の駅 遠山郷 遠山温泉郷 かぐらの湯
とてもきれいな施設で泉質もいい温泉です♪ お試しあれ
しらびそ峠を挟んで北側の山へ♪
奥茶臼山
(赤石山脈南部エリア)
全山行 415回

 奥茶臼山の情報はこちら
奥茶臼山の情報はこちら
 前編の山歩きはこちら
前編の山歩きはこちら
標高 前尾高山 2089m 尾高山 2212.4m 奥尾高山 2266m
岩本山 2269m 奥茶臼山 2473.9m
天気
 晴れのち
晴れのち 曇り
曇り山行時間 8時間45分
〈コース〉しらびそ峠(6:30)- 前尾高山-尾高山-奥尾高山-岩本山-
奥茶臼山(10:30-11:00)-北側展望地-ピストンでしらびそ峠(2:45)
雨上がりの山はすてき

しっとりとした森
苔むした原生林
命の息吹きを感じる山

後編
朝だぁー

夜半から早朝にかけて まるでスコールのような
雨が車のボンネットに叩きつける音で目が覚めた

(ひゃぁ~っ
 )
)時刻は4時半

どうする?
こんなじゃ山に登れないよね

どうしますぅ?
このまま敗退しますか?
うじゃうじゃとシュラフの中で
テンションが下がる ひとちが

外に出たくても 雨が強くてドアを開ければ
びちょ濡れになりそうなほど

5時半
ピタリと雨が上がった

恐る恐る外に出て峠の柵の先を眺めてみれば
雲海の中から南アルプスの山々が顔を出している

(わ~お
 )
)
行けるじゃん!
いこう! いこう!

雨上がりを待っていたかのように
峠には登山者たちが次々と到着

いそげ! いそげ!
マケジと峠から出発♪

まだ霧の残る幻想的な森に入っていく


登り始めると霧が晴れた

とたんに美しい緑の森が目の前に

きゃぁ~
きれい


しとった森は 雨上がりの匂いがする


尾高山まではハイキングコースなので
とてもよく整備されていた


少し進むと道が二手にわかれる

ビューポイントコースに進むと
東側の景色を楽しむことができるのだ

目の前には南アルプス南部の山々

右端には ハイランドしらびその赤い屋根


きれいですねぇ~

1時間ほどで 前尾高山の山頂に到着

樹林帯の中なので展望はない


コースは奥茶臼山まで
尾根伝いに4つの山を越えてく

標高差はそれほどないとはいえ
登ったり下ったりとアップダウンは避けられない

(はぁ。。。)
展望はきかないけれど
苔むした森はやっぱりすてき

なんてきれい


思わず何度も足が止まる

昨日の雨で山は洗われ
たくさんのキノコがにょきにょきと
朽ち落ちた倒木の苔の中から顔を出していた


光が差し込む不思議な空間


展望のきく場所に出た

青空に南アルプスを眺めることができる
数少ないポイントのひとつ


一般的なハイキング道のゴールは尾高山
ごつごつとした岩の上に山頂標識


この先は奥茶臼までの登山道
ハイキング道のようなわけにはいかない

赤テープに導かれ
シダのジャングルをズンズン進む


30分ほどで奥尾高山のピークに達した

ここも樹林帯の中

(ぶぅ。)

黒ゴマと塩を混ぜただけのおむすびも
山で食べると美味しいもんだ

ご飯が硬くて アゴが疲れます

でっかしぃー


ブツブツ・・・
悪かったね

次回は水加減間違えないから

すぐ先には奥茶臼山が見える場所がある
シラビソ峠からは深すぎて見えないのだ

手前に見えるのが岩本山


所々につけられた奥茶臼山までの距離を示す看板は
文字が欠け古さを感じさせる


ゆるやかに下っていくと
森の中に小さな池


ようやく終盤の岩本山


岩本山を過ぎると雰囲気が一転
平坦な明るい尾根 それも広い

登山道はクネクネと蛇行している


その先は


いやぁー
まいった まいった


なんでこんなに倒れているんだよー と
文句を言いたくなるほど道は倒木で塞がれていた

(ぬぉーっ
 )
)
前進するためには
イヤでも木を乗り越えなきゃ進めん

この辺りは地図上で 「迷いマーク」 がつけられている場所
「迷う」 というより 「倒木ひどし」 の方がピッタリだと思った


それでもしっかり赤テープを追わないと
道迷いし兼ねないので要注意

ここは南アルプス前衛の山
赤石岳の近くともなると石も赤い


陽当りのいい草地に出た

ようやく目的の奥茶臼山が目の前に


ひと登りすると山頂に到着
ここもまた 思いっきり樹林帯の中だ

(ぶぅ。)

先を歩いていた登山者が休憩中
スパッツを脱ぎ 荷物は散乱

ここまで随分時間かかったでしょ
もう少し早く着けると思ったんだけどな

そういえば
出発時峠の案内板見てたっけ

おじさんは地図を持参していないようだ

あのぉー
この先に展望が開けた場所があるみたいですよ

5分も進めば 快適であろう展望地
お疲れのおじさんにはどうでもいいみたいだ

もういいや

無理やりおすすめするのも何なんで
踏み跡がある北方向の展望地に向かう


またかい

伐採された山斜面の下には
作業小屋でもあったのだろうか?
北側に位置する前茶臼山が
じーっとこっちを見ていた


下まで下るより
ここの方が景色がよさそうですね

そう言うと ひとしさんはドカっと
山斜面の安定のいい石に腰をかけた

じゃぁ 下まで行って
ちょっと探検してくるね

私はここで待ってます

ちがこさんは
今日も懲りずに冒険に出かける


足場の悪い山斜面を下ると案の定
そこには小屋の廃材が


作業小屋跡の廃材は長い年月で
ボロボロに風化しつつある


それれも自然に返らない物もたくさん散乱したまま


せっかくの展望地からの景色も
感動が半分になってしまったような気がした

(はぁ。。。)

シラビソ峠からの登山道ができるまで
奥茶臼山に登るためには 青木林道を10キロ以上
歩いて登山道にとりつくコース
もしくは 栂村山・前茶臼山経由ルートのどちらか

新しく整備された登山道って
ホントありがたい

森に戻れば緑が待っている


あまり眺望を得ることができない尾根道も
こんなステキな緑の回廊


またいつの日か歩いてみたい
雨上がりの匂いのする心地よい山を

 この日の立ち寄り湯はこちら
この日の立ち寄り湯はこちら
道の駅 遠山郷 遠山温泉郷 かぐらの湯
とてもきれいな施設で泉質もいい温泉です♪ お試しあれ

2014年07月02日
しらびそ高原へ♪ 前編
2014/06/28
しらびそ峠を挟んで南側の山へ♪
御池山
(赤石山脈南部エリア)
全山行 414回

標高 御池山 1905m
天気 曇りのち
曇りのち 霧雨
霧雨
山行時間 5時間
〈コース〉ハイランドしらびそ(11:30)- 丘の上展望台-クレーター駐車場-
分岐-御池山-中郷のお池-分岐-ピストンでハイランドしらびそ(4:30)
梅雨時期のお天気は気まぐれ
土曜は雨 日曜はビミョーな晴れ雲
どっちにしてもあまりいいお天気ぢゃない
さ~てと どうしよっかな?
前編
テン泊を計画していたものの
雨山行じゃ気乗りがしない
それじゃ車泊で と
と
向かった先は南信の遠山郷
アクセス時間が長く
峠付近に到着したのはお昼少し前
ラッキーなことに雨は降っていない
南アルプスの峰々はガスがかかっている
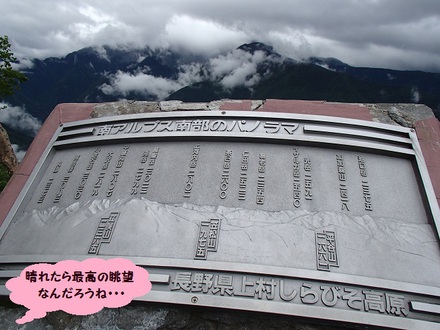
初日は短時間
ハイキング登山
余裕じゃん
とはいえ いつ降ってくるかわからない雨
カッパを着こんでいざ出発
(よっしゃー )
)

トイレの横の高台に登れば
そこからは尾根のハイキングコース
南方向ってことは 標高を下げていくってこと
なんといっても ここは峠だから

尾根に出ると 展望の良い東屋
丁度お昼となりました
東屋前の展望ってどうなの?
こんなだよ

お天気がよければ素晴らしい景色を
眺めることができるはず
右側にはハイランドしらびその建物と
北方向に続く山の稜線

まあ いいさ!
雨が本格的に降り出す前に
戻ってきましょう

広く刈り採られた笹尾根は快適で
ほとんどアップダウンもないと
ストックなしでハイキング
(うは! うは!)
木々の間から東側の南アルプスが並んで見える

峠は標高2000mくらいなので
麓よりはずっと涼しいのだ
とはいっても 歩き始めると
カッパが蒸し暑い
素直に脱ぎましょう

尾根歩き と高をくくってストックを
車に置き去りにしてきたのが仇となった
意外とアップダウンがある

尾根道は快適なものの
しばらく歩くと単調で飽きてきた

と

淡い緑のカーテンのように垂れ下がった
サルオガセ
サルオガセって寄生植物でしょ?
サルオガセに巻き付かれた木は
養分を吸い取られて枯れてしまうのだ
工作材料頂き!
にゃはは!!
尾根道に並行して走っている南アルプスエコーラインを横断
丘の上展望台に到着
(きゃほー )
)

ここからは御池山クレーター跡を
上から眺められる場所
 御池山クレーター跡の情報はこちら
御池山クレーター跡の情報はこちら
でわ 前進してクレーターを
覗いてみることにする

直径約900mというクレーター跡は
あまりに規模が大きすぎて展望台から見える範囲は
クレーターを覗く
というより
山から谷を見下ろす
といった方が正しい
2~3万年前の物だから 長い間に成長した樹木に埋め尽くされ
クレーター跡と言われなければ気づくこともないだろう
いわゆる
何を見ているのか
よくわからない

クレーターの説明が書かれている看板によれば
これから進む御池山への稜線がクレーターの縁
といわれても
イマイチ ピンとこない

まあ いいです
クレーターの縁に沿って尾根道を
ずんずん歩いていく
うが うが
うが うが
うが

どこまで行っても広い尾根道

展望台からよくわからなかったクレーター跡
尾根道からはこんな風に見える

やっぱりよくわからない
夏の蝶が群れを成して飛んでいた

御池山への最後の登り?
危険個所もほとんどないハイキングコース

岩の山頂に到着
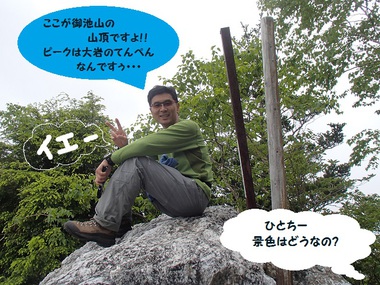
見たいですか?
では じゃ~ん

岩のてっぺんからは南東方向の山々が
今日は残念なことに山には雲
それでも美しい緑の稜線が伸びる尾根は
すてき
この尾根の先は下栗の里に続いている
もうひとつ行かなきゃならない場所がある
御池山というんだから池があるわけ
通過してきた尾根の分岐からの
池に通じる道はこんな

赤テープもあるし
行けるでしょ
行くんですか?
行くよ
やっぱり
快適な広い尾根道から外れ
中郷のお池まで下る

水場が近づくと 枯葉の腐葉土の中から
たくさんのひとが顔を出していた

池のほとりには ほこら
一周100m程の小さな池

虫がバカ多い
ここで わたすげネット登場
さっそく ひとしさんがかぶる

それに この窓のビニールは
内側からだとクリアに見えません
ゆがんで目が回りそうですぅ

これは去年 ちがこさんが使った時
イタい目に会ったのでおすすめできない

これじゃー
虫に刺されたい放題で邪魔なだけですぅ

隕石の落ちたクレーターに住んでいる
宇宙人がいたら こんな会話になっていたかも

宇宙人制作:きょうこちゃん
まあ まあ

ちがこさんが虫に刺されるじゃん

わたすげネットが使いにくいから
結局買っちゃったわけよ
で ひとち行き?
そうなんですぅ
ゲロゲロ
モリアオガエルの合唱が聞こえる

池の周囲を一周し ピストンで戻ることに
尾根に戻ると天候は急変

ハイランドしらびそ に戻る
立ち寄り湯があるので便利な施設
今夜の車泊場所に向かった

一年ぶりに初使用の前室
小雨が降ってはいるものの 虫はいないわけじゃなく
風はなく 広い前室の中は快適な空間
(いいねぇー )
)
レースのカーテン素材なので
ほどよく空気が通る

雨が強くなったら 外側からブルーシートを
かぶせれば雨も気にならないってわけ
車に積み込んできた食材を並べ
キャンプのような夕食を楽しむことができた

山のちいさな喫茶店で購入したお鍋 も初使用

やや固めのごはんが炊けちゃったけど
やっぱ山ごはんは最高
明日は北側の山に登る
どんな山歩きだったのかは次回のブログで
 後編の山歩きはこちら
後編の山歩きはこちら 
しらびそ峠を挟んで南側の山へ♪
御池山
(赤石山脈南部エリア)
全山行 414回

標高 御池山 1905m
天気
 曇りのち
曇りのち 霧雨
霧雨山行時間 5時間
〈コース〉ハイランドしらびそ(11:30)- 丘の上展望台-クレーター駐車場-
分岐-御池山-中郷のお池-分岐-ピストンでハイランドしらびそ(4:30)
梅雨時期のお天気は気まぐれ

土曜は雨 日曜はビミョーな晴れ雲

どっちにしてもあまりいいお天気ぢゃない

さ~てと どうしよっかな?
前編
テン泊を計画していたものの
雨山行じゃ気乗りがしない

それじゃ車泊で
 と
と向かった先は南信の遠山郷

アクセス時間が長く
峠付近に到着したのはお昼少し前

ラッキーなことに雨は降っていない

南アルプスの峰々はガスがかかっている

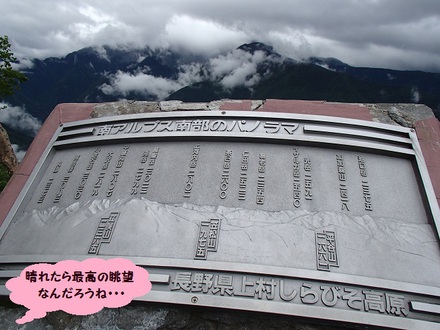
初日は短時間
ハイキング登山

余裕じゃん

とはいえ いつ降ってくるかわからない雨

カッパを着こんでいざ出発

(よっしゃー
 )
)
トイレの横の高台に登れば
そこからは尾根のハイキングコース

南方向ってことは 標高を下げていくってこと
なんといっても ここは峠だから


尾根に出ると 展望の良い東屋
丁度お昼となりました

東屋前の展望ってどうなの?
こんなだよ


お天気がよければ素晴らしい景色を
眺めることができるはず

右側にはハイランドしらびその建物と
北方向に続く山の稜線


まあ いいさ!
雨が本格的に降り出す前に
戻ってきましょう


広く刈り採られた笹尾根は快適で
ほとんどアップダウンもないと
ストックなしでハイキング

(うは! うは!)
木々の間から東側の南アルプスが並んで見える


峠は標高2000mくらいなので
麓よりはずっと涼しいのだ

とはいっても 歩き始めると
カッパが蒸し暑い

素直に脱ぎましょう


尾根歩き と高をくくってストックを
車に置き去りにしてきたのが仇となった

意外とアップダウンがある


尾根道は快適なものの
しばらく歩くと単調で飽きてきた


と

淡い緑のカーテンのように垂れ下がった
サルオガセ

サルオガセって寄生植物でしょ?
サルオガセに巻き付かれた木は
養分を吸い取られて枯れてしまうのだ

工作材料頂き!
にゃはは!!
尾根道に並行して走っている南アルプスエコーラインを横断
丘の上展望台に到着

(きゃほー
 )
)
ここからは御池山クレーター跡を
上から眺められる場所

 御池山クレーター跡の情報はこちら
御池山クレーター跡の情報はこちら
でわ 前進してクレーターを
覗いてみることにする


直径約900mというクレーター跡は
あまりに規模が大きすぎて展望台から見える範囲は
クレーターを覗く
というより
山から谷を見下ろす
といった方が正しい

2~3万年前の物だから 長い間に成長した樹木に埋め尽くされ
クレーター跡と言われなければ気づくこともないだろう

いわゆる
何を見ているのか
よくわからない


クレーターの説明が書かれている看板によれば
これから進む御池山への稜線がクレーターの縁

といわれても
イマイチ ピンとこない


まあ いいです

クレーターの縁に沿って尾根道を
ずんずん歩いていく

うが
 うが
うが うが
うが

どこまで行っても広い尾根道


展望台からよくわからなかったクレーター跡
尾根道からはこんな風に見える


やっぱりよくわからない

夏の蝶が群れを成して飛んでいた


御池山への最後の登り?
危険個所もほとんどないハイキングコース


岩の山頂に到着

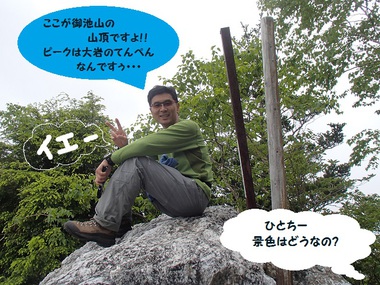
見たいですか?
では じゃ~ん

岩のてっぺんからは南東方向の山々が

今日は残念なことに山には雲

それでも美しい緑の稜線が伸びる尾根は
すてき

この尾根の先は下栗の里に続いている

もうひとつ行かなきゃならない場所がある

御池山というんだから池があるわけ

通過してきた尾根の分岐からの
池に通じる道はこんな


赤テープもあるし
行けるでしょ

行くんですか?
行くよ

やっぱり

快適な広い尾根道から外れ
中郷のお池まで下る


水場が近づくと 枯葉の腐葉土の中から
たくさんのひとが顔を出していた


池のほとりには ほこら
一周100m程の小さな池


虫がバカ多い

ここで わたすげネット登場

さっそく ひとしさんがかぶる


それに この窓のビニールは
内側からだとクリアに見えません
ゆがんで目が回りそうですぅ


これは去年 ちがこさんが使った時
イタい目に会ったのでおすすめできない


これじゃー
虫に刺されたい放題で邪魔なだけですぅ


隕石の落ちたクレーターに住んでいる
宇宙人がいたら こんな会話になっていたかも


宇宙人制作:きょうこちゃん
まあ まあ

ちがこさんが虫に刺されるじゃん


わたすげネットが使いにくいから
結局買っちゃったわけよ

で ひとち行き?
そうなんですぅ

ゲロゲロ
モリアオガエルの合唱が聞こえる


池の周囲を一周し ピストンで戻ることに

尾根に戻ると天候は急変


ハイランドしらびそ に戻る

立ち寄り湯があるので便利な施設

今夜の車泊場所に向かった


一年ぶりに初使用の前室

小雨が降ってはいるものの 虫はいないわけじゃなく
風はなく 広い前室の中は快適な空間

(いいねぇー
 )
)レースのカーテン素材なので
ほどよく空気が通る


雨が強くなったら 外側からブルーシートを
かぶせれば雨も気にならないってわけ

車に積み込んできた食材を並べ
キャンプのような夕食を楽しむことができた


山のちいさな喫茶店で購入したお鍋 も初使用


やや固めのごはんが炊けちゃったけど
やっぱ山ごはんは最高

明日は北側の山に登る

どんな山歩きだったのかは次回のブログで

 後編の山歩きはこちら
後編の山歩きはこちら 
2014年06月30日
しらびそ高原へ♪ 予告編
2014/06/28
峠のむこうには日本の原風景が今もある
遠山郷

読んで字のごとし
遠山は遠かった
予告編
今週わー
信州と静岡の境に位置する
南信州 遠山郷に向かった
ここは 知る人ぞ知る
人情と癒しの谷
だそうだ
しらびそ高原の場所はこちら
自宅から4時間半
目的地の しらびそ峠付近に到着したのは
すでにお昼近く
あ゛―
長い道のりだった
信州と静岡の境なのに
やたら遠い
そりゃ 遠山だから
あ~
そうー
最初に向かったのは
宿泊施設 ハイランドしらびそ

ここからは東に南アルプス南部の山々
西に中央アルプス・御嶽山と
大パノラマを楽しめる
雨予報だったものの 雨は降ることなく
アルプスの峰には雲がかかり景色はビミョー
そんでも 雨じゃないだけマシ と
いつ落ちてきてもおかしくない
雨を気にしながらの山歩き
初日に向かった山で見たものは

虫の多いこの時期
去年 使わずじまいだった
まるで宇宙服の一部のような・・・

なんかもありマス
どうせ遠くまで来たんだから
ということで 車泊

峠からも素晴らしい景色

そして
見た人は思わず引くであろう蚊帳のような・・・

もありマス
二日目はこ~んな雨上がりの
きれいな山を歩くこと9時間近く

山あり谷ありのロングコース
夕日が沈むころには
こんな場所へも

駐車場から山の中を往復1キロ歩く
観光客泣かせ?の絶景地へ
2日間遊びまくり
次回は初日の山歩き
お楽しみにぃ~っ
 前編はこちら
前編はこちら
 後編はこちら
後編はこちら 
峠のむこうには日本の原風景が今もある
遠山郷
読んで字のごとし
遠山は遠かった

予告編
今週わー
信州と静岡の境に位置する
南信州 遠山郷に向かった

ここは 知る人ぞ知る
人情と癒しの谷
だそうだ

しらびそ高原の場所はこちら

自宅から4時間半

目的地の しらびそ峠付近に到着したのは
すでにお昼近く

あ゛―
長い道のりだった

信州と静岡の境なのに
やたら遠い

そりゃ 遠山だから

あ~
そうー

最初に向かったのは
宿泊施設 ハイランドしらびそ


ここからは東に南アルプス南部の山々
西に中央アルプス・御嶽山と
大パノラマを楽しめる

雨予報だったものの 雨は降ることなく
アルプスの峰には雲がかかり景色はビミョー

そんでも 雨じゃないだけマシ と
いつ落ちてきてもおかしくない
雨を気にしながらの山歩き

初日に向かった山で見たものは


虫の多いこの時期
去年 使わずじまいだった

まるで宇宙服の一部のような・・・

↑ クイックしてね

なんかもありマス

どうせ遠くまで来たんだから
ということで 車泊


峠からも素晴らしい景色


そして
見た人は思わず引くであろう蚊帳のような・・・

↑ クイックしてね

もありマス

二日目はこ~んな雨上がりの
きれいな山を歩くこと9時間近く


山あり谷ありのロングコース

夕日が沈むころには
こんな場所へも


駐車場から山の中を往復1キロ歩く
観光客泣かせ?の絶景地へ

2日間遊びまくり

次回は初日の山歩き
お楽しみにぃ~っ

 前編はこちら
前編はこちら
 後編はこちら
後編はこちら 
2014年06月06日
結末と教訓・・・
2014/06/06
遭難の報告・・・
悲しい現実
亡くなられた登山者の方のご冥福をお祈り致します

 笊ヶ岳の情報はこちら
笊ヶ岳の情報はこちら
まずは みなさんにお詫びしたいことがある
笊ヶ岳には登山ポストは
ちゃ~んとあった
*老平ゲートの右にあるそうです
登山届は必ず提出を
 笊ヶ岳 初日の様子
笊ヶ岳 初日の様子 
 笊ヶ岳 二日目の様子
笊ヶ岳 二日目の様子 
遭難事件のあらまし
GW一日前5月2日(金)
一足早く笊ヶ岳に入山した
前日に笊に入山した登山者は2名
どちらも単独の若い登山者であった
桧横手山の手前辺りの急坂を
死にもの狂いで登っている時 すれ違う
当日 布引山までテントを上げたのは
ひとちがと単独登山者の男性のみ
翌朝3日笊の山頂までピストン
テントをたたんだ
下山時 先行して歩く単独登山者の後を追い
正規ルートから大きく外れ 遭難しかけた
先行した男性は夜になっても登山口には戻らず
遭難を疑い警察に通報
2日後 この男性は自力で下山したことが判明
ほっとした矢先・・・
新たな遭難事件発生
ひとちがが下山した3日のことだ
当日 笊ヶ岳に向けて登っていた登山者は
12名ほどだったと思う
その中のひとりと思われたが
詳しい情報がなくなすすべもない
そして昨日 登山者の方から
コメントをいただいた
内容は
こんにちは。桧横手の下ですれ違った単独行者です。
本当に迷いやすいルートでしたよね。無事で何よりでした。
残念ながら桧横手に幕営された犬連れの単独行者は、
先週末になって釣り師に発見されました。
ところで老平の登山ポストはゲートの右脇にあります。
先週も登りに行きましたが、布引山まで夏道が出ていました。
もう迷う人はないと思いますが、尾根の分岐のあたりなど、
もう少し道標が欲しいところですよね
 コメントを下さった ほしさんのHP山行の記録
コメントを下さった ほしさんのHP山行の記録
*後にわかったことですが ほしさんは初日に下山してきた
若い登山者のひとりでした
そういえば・・・
山を下って行くとき 確かに犬を連れた
単独の登山者とすれ違ったっけ
カーブ地点付近だったから3時半をまわっていたはず
登山道脇に所々テントが張られていた
この時点では かなり時間が押していたのと
疲労とで すれ違う登山者と会話もなかった
人間でも大変なのに 犬もさぞかし大変だろうな
それにしても これからどこまで登るんだろう と
見送ったことを思い出した
情報によれば 桧横手にテントを張ったとのこと
たぶん5時ころに到着だったはずだ
遭難した方のその後の行動は不明だが
9日の朝日新聞にはこのような記事
東京の50代男性 笊ケ岳で遭難か
南部署は9日、静岡県境にある早川町の笊ケ岳(ざるがたけ)で、
東京都新宿区の50代の会社員男性が遭難した疑いがあると発表した。
県警ヘリコプターが上空から捜索したが見つからなかった。
署によると、早川町雨畑の無料駐車場に車が1週間近くとまっていたため、
近くの住民が遭難を疑って通報した。
男性は登山愛好家で、2日ごろに家族に
「連休明けには戻る」と連絡をしていたという。
10日は署員と男性の登山仲間も加わり、登山道周辺を捜索する
実際 この時 こむちゃん が笊に登って
捜索隊に遭遇した
これらの事柄を整理すると
遭難した日から ほぼ1ヶ月後
ようやく遭難者は発見されたことになる
ご家族の方も眠れない日々を送ってきたことだろう
見つけた人は釣り師とのことなので
沢の近くで発見されたか?
ひとちがが遭難しそうになった時のことを
もう一度振り返ってみよう
これが道間違えしてコース修正したルート

地図をごらんいただいてわかると思うが
左側に布引大崩から続く稲又谷(登山道には合流できない)
右には老平方向の登山道に沿う奥沢谷がある
どちらの沢方向に向かっても当然道はなく
深い樹林帯 迷宮の世界だったはず
道間違いしてトレースをつけてしまったポイントは二ヶ所
小ピークと2300m降下地点
ということは 遭難者はこのどちらかのトレースを
追っかけて道間違いしたのではないか?
ご存じかと思われるが 雪のある時期の笊ヶ岳は
ともかく不明瞭で 道標・赤テープは少ない
特にその付近は道間違えしやすく
毎年のように遭難さわぎがあるそうだ
それでなくても少ないトレース
小ピークから間違え下ったポイントには
少なくとも3人分のトレースがついていた
小ピークから 下向きの靴跡を追っかけて
正規ルートと判断して下ってしまったのか?
2300m降下地点には 修正して這い登ってきた
ひとちが2人分の上向きのトレースがあったはず
登りの登山者のトレースと間違えて
老平に下る正規ルートと判断してしまったのか?
いずれにしても ついたばかりのトレースだから
たどる=正規ルート
と思われても仕方ない
二ヶ所のポイントのどちらかで 間違ったトレースを追い
深い樹林帯に迷い込んでしまったとしたら・・・
そう考えると心が痛む
下山時 かなりタイムロスしたのと疲労で
すれ違う登山者の方にも適切なアドバイスできなかった
(数名の方には下山時 道間違えしないようにお話しましたが )
)
今は夏道となり 迷うことも少なくはなっているとは思う
しかし侮ってはいけない
GWより少し後に別ルートから登頂した
モリちゃんの記録
こちらもかなり壮絶です・・・
モリちゃんからは 遭難者に関する違う情報も頂いた
山梨トピックス6/1より
2014年06月01日(日)
南部署が31日、早川町雨畑の堤防で倒れている男性の遺体を発見し、
県警のヘリコプターが収容。
5月9日から同所の笊ヶ岳(ざるがたけ)(2629メートル)に出かけたまま
行方不明になっている東京都新宿区の50代の
会社員男性の可能性があるとみて、身元の確認へ。
う~ん
雨畑の堤防ってことは
やはり右の沢方向に進んだのか?
どちらにしても生還し 下山できなかったことは
とても残念なこと
今年の冬には また雪は降る
そして笊ヶ岳に登る登山者は必ずいる
トレースがあっても信用しないで
自分でコースを探り判断すること
もし道間違えしたら 絶対に先には進まないで
確実にわかるポイントまで引き返す勇気が必要
冒険しよう
でも危険はダメ
自分の技量に合った山選択を
追記として ほしさんからコメントが届いた
発見個所は稲又谷の堤防ということです。
C2400かC2350を直進して下ったか
西側崩落地を滑落したかのどちらかかと思います。
ほしさんの笊ヶ岳道迷い検証
*遭難された方の詳しい道迷いの分析をしてくれています
そうか・・・
右側の布引大崩の先の沢で発見されたんだ
それにしても道迷いの検証のために
笊にまた登るなんてスゴい人だ
その後の ほしさんとメールでのやりとり
☆ちがこさんから☆
ひとちがです。
じっくり検証を読ませて頂きました。
私がブログにアップした地図は正確な物ではありませんが
ほしさんの地図を見させて頂く限り まさに迷った場所であると確信しました。
検証して下さった通り、あの時のC2400からは腐れ雪の深い急斜面で
ややトラバースしながら恐ろしい思いで下ったことを思い出しました。
当初は「下る」という意識しかなく 道を外していることにも気づかず
雪のない時期なら下るのは到底無理ではかなったかと。
(雪のない時期なら斜面から転がり落ちそうでした。)
延々と下り雪も消えかけた2000m付近で道間違えであることに気づきました。
右に布引大崩と青薙山方向の稜線が見えたときは仰天し あたふた・・・
大急ぎでC2264に向かって尾根を登り返しました。
運がよかったのはC2400の小ピークが見えたことです。
時間がかかろうとわかる場所まで確実に戻ろうと決めました。
尾根に出るまでは雪のない場所は急な上、ヤブで足場のよい場所を
選んで這い登り、尾根に出てからはC2350の分岐についた赤テープを
必死に探し ようやく見つけた時は正規ルートに戻ったことを確信
ホットしたことを思い出しました。
ほしさんの検証を読む限り やはり遭難した方は私たちがつけた
トレースを追ってしまったのではないかということです。
2000m付近から先は雪が消え下り続けることは トレースなしのヤブの
迷宮路だったはずです。
この遭難事件前の 私たちが遭難と早とちりした登山者の情報は
警察に地図上で細かく説明しました。
(道迷いしたポイント等も 3日下山後夜半)
正規ルートに戻ってからは時間の焦りの方が大きく、余裕もなく
登ってくる登山者の方にすべて「道迷いの注意」をすることもできませんでした。
遭難で命を落としてしまった登山者の方とすれ違った時もそうでした。
一言「ルートから外れているトレースがあるので追わないように」と
アドバイスできていたなら遭難は起こらなかったかもしれません。
私達も今回の山歩きで学ぶことがたくさんありました。
ほしさんのようにキャリアもなく知識や技術にも欠けている登山者ではありますが
これからもアンテナを張ってしっかり山を歩きたいと思います。
ほしさんのHP、リンクさせていただきました。
これから笊ヶ岳に登頂される登山者の参考になってもらえれば嬉しいと思っています。
本当にありがとうございました。
ちがこさんより
☆ほしさんから届いたお返事☆
ひとちがさま
メールありがとうございます。
遭難者の発見場所から、尾根の分岐で迷ったと推察されますが、
仮に3人分の間違いトレースが道迷いのきっかけになったにせよ、
雪がない所まで下ってヤブであればお二方のように登り返す手立てはあったのですから、
遭難の原因は、遭難者本人の問題(地図を確認せずトレース頼みで進んだ、
登り返す体力がなかった、ビバークできる非常食を持ってなかった
等が考えられます)と思います。
今後、同じ道迷いが発生しないようにという、お二方の真摯な姿勢に感銘を受けました。
笊ヶ岳に登ろうとする人にはぜひこの事例を教訓にしてほしいですね。
捜索に当たられた都岳連の方からは、当日の目撃情報なし、とのことでしたが、
実際には同日に12名くらい登られていたとの事、
警察からその方々の登山届の連絡先へ問い合わせして何かわかっていれば、
あるいは、今回の様なネットワークが早い段階でできていれば、
初期捜索で見つけることができたかもということを考えます。
5/1は私も登山届は出さずに登りましたが(5/31は出しました)、
自分のためだけではなく、人のためにも出す意味があるんだと初めて認識しました。
お二方はかなり歩かれていらっしゃるようですので、
いずれどこかの山でまたお会いする日もあろうかと思います。
お互い事故の無いように山を楽しみましょう!
星征雅
私達のメールのやりとりを読んだ
みなさんはどのように感じただろうか?
山に入ることは どのような場合でも
危険と隣り合わせ
だということを忘れてはいけない
GWの笊ヶ岳遭難事件をきっかけに 同時期に登頂した人たちの
声や情報を得ることができた
これは警察や共に捜索した仲間たち意外にも
身近に協力者となり得る山ヤがいるという事実
遭難は悲しいこと
山は好きでも 遭難したら 家族や友人悲しむ人がいることを
忘れずに慎重に行動しましょう
声を上げよう
遭難は一刻を争う場合が多い
ひとつでも多くの情報が寄せられれば
最悪の状況を回避できる時もあるかもしれないのだから
遭難の報告・・・
悲しい現実
亡くなられた登山者の方のご冥福をお祈り致します


 笊ヶ岳の情報はこちら
笊ヶ岳の情報はこちら
まずは みなさんにお詫びしたいことがある

笊ヶ岳には登山ポストは
ちゃ~んとあった

*老平ゲートの右にあるそうです

登山届は必ず提出を

 笊ヶ岳 初日の様子
笊ヶ岳 初日の様子 
 笊ヶ岳 二日目の様子
笊ヶ岳 二日目の様子 
遭難事件のあらまし
GW一日前5月2日(金)
一足早く笊ヶ岳に入山した

前日に笊に入山した登山者は2名
どちらも単独の若い登山者であった

桧横手山の手前辺りの急坂を
死にもの狂いで登っている時 すれ違う

当日 布引山までテントを上げたのは
ひとちがと単独登山者の男性のみ

翌朝3日笊の山頂までピストン

テントをたたんだ

下山時 先行して歩く単独登山者の後を追い
正規ルートから大きく外れ 遭難しかけた

先行した男性は夜になっても登山口には戻らず
遭難を疑い警察に通報

2日後 この男性は自力で下山したことが判明

ほっとした矢先・・・
新たな遭難事件発生

ひとちがが下山した3日のことだ

当日 笊ヶ岳に向けて登っていた登山者は
12名ほどだったと思う

その中のひとりと思われたが
詳しい情報がなくなすすべもない

そして昨日 登山者の方から
コメントをいただいた

内容は
こんにちは。桧横手の下ですれ違った単独行者です。
本当に迷いやすいルートでしたよね。無事で何よりでした。
残念ながら桧横手に幕営された犬連れの単独行者は、
先週末になって釣り師に発見されました。
ところで老平の登山ポストはゲートの右脇にあります。
先週も登りに行きましたが、布引山まで夏道が出ていました。
もう迷う人はないと思いますが、尾根の分岐のあたりなど、
もう少し道標が欲しいところですよね
 コメントを下さった ほしさんのHP山行の記録
コメントを下さった ほしさんのHP山行の記録*後にわかったことですが ほしさんは初日に下山してきた
若い登山者のひとりでした

そういえば・・・

山を下って行くとき 確かに犬を連れた
単独の登山者とすれ違ったっけ

カーブ地点付近だったから3時半をまわっていたはず

登山道脇に所々テントが張られていた

この時点では かなり時間が押していたのと
疲労とで すれ違う登山者と会話もなかった

人間でも大変なのに 犬もさぞかし大変だろうな
それにしても これからどこまで登るんだろう と
見送ったことを思い出した

情報によれば 桧横手にテントを張ったとのこと
たぶん5時ころに到着だったはずだ

遭難した方のその後の行動は不明だが
9日の朝日新聞にはこのような記事

東京の50代男性 笊ケ岳で遭難か
南部署は9日、静岡県境にある早川町の笊ケ岳(ざるがたけ)で、
東京都新宿区の50代の会社員男性が遭難した疑いがあると発表した。
県警ヘリコプターが上空から捜索したが見つからなかった。
署によると、早川町雨畑の無料駐車場に車が1週間近くとまっていたため、
近くの住民が遭難を疑って通報した。
男性は登山愛好家で、2日ごろに家族に
「連休明けには戻る」と連絡をしていたという。
10日は署員と男性の登山仲間も加わり、登山道周辺を捜索する
実際 この時 こむちゃん が笊に登って
捜索隊に遭遇した

これらの事柄を整理すると
遭難した日から ほぼ1ヶ月後
ようやく遭難者は発見されたことになる

ご家族の方も眠れない日々を送ってきたことだろう

見つけた人は釣り師とのことなので
沢の近くで発見されたか?
ひとちがが遭難しそうになった時のことを
もう一度振り返ってみよう

これが道間違えしてコース修正したルート

地図をごらんいただいてわかると思うが
左側に布引大崩から続く稲又谷(登山道には合流できない)
右には老平方向の登山道に沿う奥沢谷がある

どちらの沢方向に向かっても当然道はなく
深い樹林帯 迷宮の世界だったはず

道間違いしてトレースをつけてしまったポイントは二ヶ所
小ピークと2300m降下地点
ということは 遭難者はこのどちらかのトレースを
追っかけて道間違いしたのではないか?
ご存じかと思われるが 雪のある時期の笊ヶ岳は
ともかく不明瞭で 道標・赤テープは少ない

特にその付近は道間違えしやすく
毎年のように遭難さわぎがあるそうだ

それでなくても少ないトレース

小ピークから間違え下ったポイントには
少なくとも3人分のトレースがついていた

小ピークから 下向きの靴跡を追っかけて
正規ルートと判断して下ってしまったのか?
2300m降下地点には 修正して這い登ってきた
ひとちが2人分の上向きのトレースがあったはず

登りの登山者のトレースと間違えて
老平に下る正規ルートと判断してしまったのか?
いずれにしても ついたばかりのトレースだから
たどる=正規ルート
と思われても仕方ない

二ヶ所のポイントのどちらかで 間違ったトレースを追い
深い樹林帯に迷い込んでしまったとしたら・・・
そう考えると心が痛む

下山時 かなりタイムロスしたのと疲労で
すれ違う登山者の方にも適切なアドバイスできなかった

(数名の方には下山時 道間違えしないようにお話しましたが
 )
)今は夏道となり 迷うことも少なくはなっているとは思う

しかし侮ってはいけない

GWより少し後に別ルートから登頂した
モリちゃんの記録
こちらもかなり壮絶です・・・

モリちゃんからは 遭難者に関する違う情報も頂いた

山梨トピックス6/1より
2014年06月01日(日)
南部署が31日、早川町雨畑の堤防で倒れている男性の遺体を発見し、
県警のヘリコプターが収容。
5月9日から同所の笊ヶ岳(ざるがたけ)(2629メートル)に出かけたまま
行方不明になっている東京都新宿区の50代の
会社員男性の可能性があるとみて、身元の確認へ。
う~ん

雨畑の堤防ってことは
やはり右の沢方向に進んだのか?
どちらにしても生還し 下山できなかったことは
とても残念なこと

今年の冬には また雪は降る

そして笊ヶ岳に登る登山者は必ずいる

トレースがあっても信用しないで
自分でコースを探り判断すること

もし道間違えしたら 絶対に先には進まないで
確実にわかるポイントまで引き返す勇気が必要

冒険しよう
でも危険はダメ

自分の技量に合った山選択を

追記として ほしさんからコメントが届いた

発見個所は稲又谷の堤防ということです。
C2400かC2350を直進して下ったか
西側崩落地を滑落したかのどちらかかと思います。
ほしさんの笊ヶ岳道迷い検証
*遭難された方の詳しい道迷いの分析をしてくれています

そうか・・・
右側の布引大崩の先の沢で発見されたんだ

それにしても道迷いの検証のために
笊にまた登るなんてスゴい人だ

その後の ほしさんとメールでのやりとり

☆ちがこさんから☆
ひとちがです。
じっくり検証を読ませて頂きました。
私がブログにアップした地図は正確な物ではありませんが
ほしさんの地図を見させて頂く限り まさに迷った場所であると確信しました。
検証して下さった通り、あの時のC2400からは腐れ雪の深い急斜面で
ややトラバースしながら恐ろしい思いで下ったことを思い出しました。
当初は「下る」という意識しかなく 道を外していることにも気づかず
雪のない時期なら下るのは到底無理ではかなったかと。
(雪のない時期なら斜面から転がり落ちそうでした。)
延々と下り雪も消えかけた2000m付近で道間違えであることに気づきました。
右に布引大崩と青薙山方向の稜線が見えたときは仰天し あたふた・・・
大急ぎでC2264に向かって尾根を登り返しました。
運がよかったのはC2400の小ピークが見えたことです。
時間がかかろうとわかる場所まで確実に戻ろうと決めました。
尾根に出るまでは雪のない場所は急な上、ヤブで足場のよい場所を
選んで這い登り、尾根に出てからはC2350の分岐についた赤テープを
必死に探し ようやく見つけた時は正規ルートに戻ったことを確信
ホットしたことを思い出しました。
ほしさんの検証を読む限り やはり遭難した方は私たちがつけた
トレースを追ってしまったのではないかということです。
2000m付近から先は雪が消え下り続けることは トレースなしのヤブの
迷宮路だったはずです。
この遭難事件前の 私たちが遭難と早とちりした登山者の情報は
警察に地図上で細かく説明しました。
(道迷いしたポイント等も 3日下山後夜半)
正規ルートに戻ってからは時間の焦りの方が大きく、余裕もなく
登ってくる登山者の方にすべて「道迷いの注意」をすることもできませんでした。
遭難で命を落としてしまった登山者の方とすれ違った時もそうでした。
一言「ルートから外れているトレースがあるので追わないように」と
アドバイスできていたなら遭難は起こらなかったかもしれません。
私達も今回の山歩きで学ぶことがたくさんありました。
ほしさんのようにキャリアもなく知識や技術にも欠けている登山者ではありますが
これからもアンテナを張ってしっかり山を歩きたいと思います。
ほしさんのHP、リンクさせていただきました。
これから笊ヶ岳に登頂される登山者の参考になってもらえれば嬉しいと思っています。
本当にありがとうございました。
ちがこさんより
☆ほしさんから届いたお返事☆
ひとちがさま
メールありがとうございます。
遭難者の発見場所から、尾根の分岐で迷ったと推察されますが、
仮に3人分の間違いトレースが道迷いのきっかけになったにせよ、
雪がない所まで下ってヤブであればお二方のように登り返す手立てはあったのですから、
遭難の原因は、遭難者本人の問題(地図を確認せずトレース頼みで進んだ、
登り返す体力がなかった、ビバークできる非常食を持ってなかった
等が考えられます)と思います。
今後、同じ道迷いが発生しないようにという、お二方の真摯な姿勢に感銘を受けました。
笊ヶ岳に登ろうとする人にはぜひこの事例を教訓にしてほしいですね。
捜索に当たられた都岳連の方からは、当日の目撃情報なし、とのことでしたが、
実際には同日に12名くらい登られていたとの事、
警察からその方々の登山届の連絡先へ問い合わせして何かわかっていれば、
あるいは、今回の様なネットワークが早い段階でできていれば、
初期捜索で見つけることができたかもということを考えます。
5/1は私も登山届は出さずに登りましたが(5/31は出しました)、
自分のためだけではなく、人のためにも出す意味があるんだと初めて認識しました。
お二方はかなり歩かれていらっしゃるようですので、
いずれどこかの山でまたお会いする日もあろうかと思います。
お互い事故の無いように山を楽しみましょう!
星征雅
私達のメールのやりとりを読んだ
みなさんはどのように感じただろうか?
山に入ることは どのような場合でも
危険と隣り合わせ
だということを忘れてはいけない

GWの笊ヶ岳遭難事件をきっかけに 同時期に登頂した人たちの
声や情報を得ることができた

これは警察や共に捜索した仲間たち意外にも
身近に協力者となり得る山ヤがいるという事実

遭難は悲しいこと

山は好きでも 遭難したら 家族や友人悲しむ人がいることを
忘れずに慎重に行動しましょう

声を上げよう

遭難は一刻を争う場合が多い
ひとつでも多くの情報が寄せられれば
最悪の状況を回避できる時もあるかもしれないのだから

2014年05月14日
中年の証明♪ 後編
2014/05/03
勝手な解釈?
笊ヶ岳
(赤石山脈南部エリア)
全山行 409回
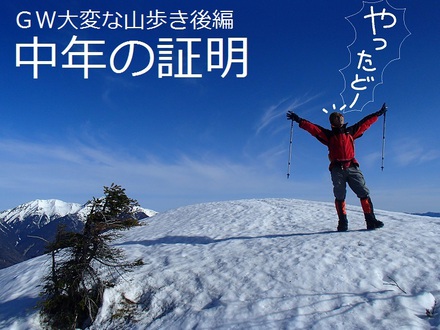
 笊ヶ岳の情報はこちら
笊ヶ岳の情報はこちら
 布引山の情報はこちら
布引山の情報はこちら
 前編はこちら
前編はこちら 
標高 布引山 2583.7m 笊ヶ岳 2629.0m
天気 晴れ
晴れ
山行時間 合計14時間30分
*布引山から登山口までは無積雪期通常のコースタイムであれば
5時間程度で下山できる。
今回は残雪期+道迷いのため9時間半かかった。(約2倍)
〈コース〉布引山テント(5:00)-笊ヶ岳山頂(6:50-7:20)-
布引山テント(9:00-10:00)-2000mf付近まで降下(11:20-11:30)-
小ピーク下2300m地点まで登る(1:30)-桧横手山(2:20-2:30)-
カーブ地点(3:30)-山の神(4:30-4:45)-広河原(5:30-5:40)-
廃屋(6:50)-林道終点(7:00)-老平(7:30)
山に入ることは自己責任
コースは自己の体力と技術を考慮し
無理のないルートを選ぶこと
進む以上は 最後まで自分の足で歩き
他人に頼らず迷惑をかけないこと
これが山ヤの鉄則
後 編
 夜 半
夜 半 
聞いたことのないような声で
動物が鳴いている
あ゛―
動物がテントに近寄ってきたみたいです
なんだろ? コワいですぅー
クマじゃないから別にいいじゃん
でもぉー
気になって
zzzzzz
いつのまにか 瀑睡
 朝だぁー
朝だぁー 
テントから顔を出すと
オレンジ色の太陽

ほぼ雪山装備のテン泊のため荷物は多けれど
足りない物・忘れ物もほとんどなく
快適な朝を迎えることができた
(うはは。)
おかげで ひとちはザックが重くて
ここまで大変だったんだもんねぇー
そうなんですぅー
それにしても今朝は 超元気
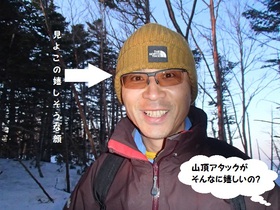
アタックザックだから軽くって
楽ちんですぅーっ!
あっ そう
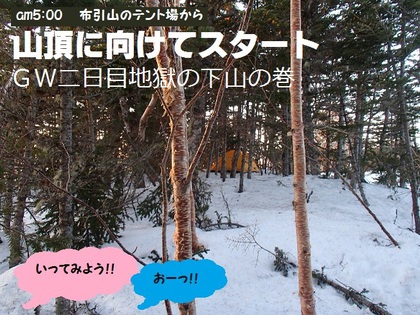
布引山付近は森林限界
鞍部までは東西両側の景色を随所で堪能できる
(うは! うは!)
東側の景色は 今まさにご来光を迎えた
我がホームグラウンド富士山
きれいですねぇ~

森林限界とはいえ 全く木々がないわけでなく
木々の間に残る深い雪の稜線は歩きにくい
(ぶぅ )
)

ひとちががテントを張った布引山のピークの
少し先に単独者のテントが張られていた
同じように彼も 「いざ笊の山頂に向けて出発」
というタイミング
見れば足元はスノーシュー
自由にアイゼンとスノーシューを分離できる
便利なコンパクトタイプだ
こんなに雪が深くて
ズボズボだと思わなかったよね
まったくですぅ

ひとちがといえば 8本歯のアイゼンに
夏用ストック ピッケルなし
ありゃ ダメじゃん
おかげで ウマる 転ぶ は当たり前
スマートにスノーシューで山頂方向に向かっている
彼とはエラい違いだ
あ~ぁ
わかってたら せめてワカン持ってくれば
よかったよねぇー

山はそんなに甘くない
鞍部に向かって歩いているうちに
すっかり陽が昇った

目の前には笊の姿

今日も快晴
午後には天気は曇り予報なので
できるだけ早く下山したい所
西側は このような景色
南アルプス南部の山々が勢揃い
こんな間近で見たのは初めてだ
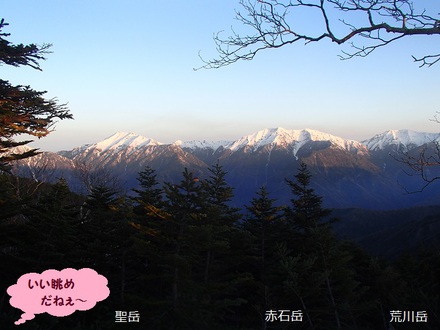
東西の山を交互に見ていると
すぐ先に 先行した彼が立ち止まり
やっぱり山を眺めている

そうなんだよねぇー
歩けば転び 進めばくすがり
ズボって ハマって
もー た~いへん


遊んでないし
気をつけてるつもりだしぃー
鞍部までたどりつくと
益々山の姿が大きくなった
(おぉ )
)

鞍部から先は急登
雪は見上げるような壁と化し
右は急な山斜面 左は絶壁なので
這い登って進むしかない

ぬぉーっ
なんとか這い登ったぞ
と ちょっと優越感に浸った
その先を見れば 手すりのない
スベリ台みたいな雪斜面
(げっ )
)
左右どちらに滑り落ちても
滑落死か?

登るのはいいとして
下る時は倍増の怖さかもね
こーゆー場合
アイゼンをきせて登りたい所
 雪はユルユル
雪はユルユル 
雪にアイゼンは刺さらず足が
ズルズルと滑る
(ひゃぁー )
)

無積雪期なら もっと簡単に
ピークを踏めるのかな?
登ったことないんだから
わかるわけないじゃん
あ そうか
とうとう念願だった笊ヶ岳の山頂

残念なことに 楽しみにしていた
山頂標識は雪の下
でわ お待たせの景色を
ご覧いただこう
じゃ~ん

これぞ 特級品の富士山の眺望
今まで眺めた富士山の中でも
ダントツ一番だ と思った
そしてこちらは南側
テン泊した布引山

笊ヶ岳がメインみたいな気もするけど
実はこの布引山までの登りが大変なのだ
笊ヶ岳はオマケかい?
そーじゃないけどね
そして こちらが南西から北西に向かって続く
南アルプス南部の山々



自分達が がんばって登ったことに
大満足
山頂で合流した単独の彼としばしお話した
彼は オールシーズン日本アルプスを登り
経験豊富な実力ある山ヤだ と正直思った
その勝手な思い込みが後に仇となる
テン場までの帰路はピストンとはいえ
ウマる ハマる ことに変わりはない
(ぶぅ。)

無積雪期なら3時間程度で往復できるコースタイムも
4時間と 大幅に足が出てしまい 悪戦苦闘

どんなに大変でも嬉しかったのは
富士山がいつも横にいること

さぁ テン場は近いよ
がんばろっか!

振り返ると だんだん遠くなる笊兄弟

またねぇ~♪
再度この山を登る日がくるのだろうか?
たぶん しばらくはこないと思うけど
バカ大変だもんね
置き去りにしたテントをたたみ
布引山にも別れを告げる

今出発すれば登山口に
3時すぎには到着できますね
雪があるから多少時間がかかっても
5時までには十分下れるはずです
うん
余裕だね

布引山のピークのすぐ先は
「布引大崩れ」と呼ばれるガレ場

ここを起点に帰路の桧横手山方向と
青薙山方向に道は分岐している

いつものように 自分の目で赤テープを確認し
山の下山方向を見定めて進路をとれば
道間違いすることはなかったはず

ところが
山頂でお話した単独の彼 下山時もほぼ
ひとちがと同時出発で先行していた
登山者は前々日入った単独の二人のみ
トレースはあまりあてにならない
そこで 踏んだばかりの
彼のトレースを追っかけることにしたのだ
経験豊富な彼の後なら安心だね
赤テープ探さなくてもいいし
道迷いの心配もないもんね
勝手な思い込み

後方では いつものように ちがこさんを
信じてついてくる ひとしさんがいる

ちゃんと足跡ありますか?
あるよー
まだ靴底の模様が消えない新しいのだから
見落すわけないじゃん
油断した
あれよ あれよと言う間に
トレースは急斜面を下っていく
疑うことなく追う ひとちが

ん?
途中で異変に気付いた
こんな場所通ったかな?
斜めにトラバースして登った覚えないけど
もっと左に下らなきゃ変だよね?
どこでも同じように見えるもんです
でもおかしいですね
南西に下ってる気がします

だよね
地図だと尾根を東にカーブしながら下るはず
曲がるポイントがあるはずなんだけどな・・・
あれ?
尾根が右上に見えますよ
何か変だな
でもさー 先行者もここを確実に下ってるし
登り返したトレースもなし
もしかして東に山を周り込むつもりかな?

うじゃうじゃ討論するものの
やっぱり不安は隠しきれない
げっ
あれ見て
とんでもない物を見つけてしまった
左方向に大きな崩れ場
その上には たぶん青薙山方向へ
向かうであろう稜線が見えた

ということは・・・
思いっきり正規ルートとは違う
別斜面を下ってしまっているってこと?
そうみたいですぅ
慌てて地図を出し正置してみる
見上げると 本来通過しなきゃいけない
小ピークのとんがりが見えた
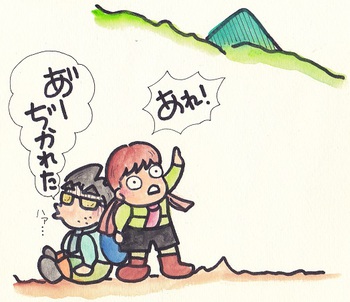
や やっぱ違うよ
山の反対側に下ってる
トレースを探した
さっきまで雪の上にくっきりついていたトレースは
標高を下げると雪と共に消え見当たらない
恐ろしいほどの急斜面を無理やり下ってしまったのだから
今更登り返すってわけにもいかない

どうしよう
どうします?
やっぱ尾根に戻ろうよ
登れそうな場所を選んで小ピーク方向に
登っていくしかないよ
え゛―
この荷物背負って
また登らなきゃいけないんですか?
もう限界ですぅー
仕方ないよ
このままトラバースして正規ルートに戻ろうとしても
果たして歩けるような場所があるかわかんないしぃ
決断したら登る
アイゼンを外し 雪のなくなった踏まれていない
フカフカの山斜面を必死に登っていく
ハァ ハァ
ハァ ハァ
ハァ
バリバリとヤブを押しのけ 尾根に向かって
ひたすら登っていくしかない
どのくらい時間が過ぎたのか?
すっかり気持ちが萎えてしまったのか
ひとしさんの足取りは重く
なかなか ちがこさんに追いつけない
ようやく尾根らしき場所に出た
このまま戻れば 正規ルートに戻れるはず
ファイトー!
自信があった
必ず赤テープはある
ねぇ がんばって登ろ
「信用ならぬ」といった顔でノロノロと
言葉なくひたすら登る ひとしさん
あったぁー
木についている赤テープ発見
正規ルートに戻れた

*ちなみにこれは ひとちがが道迷いしたルートです・・・
戻れる
時間はかかるだろうけど
必ず登山口へ下山できる

心配だったのは 道間違えして
樹林帯方向へ下ってしまった単独の彼のこと
登り返すこともせず そのまま深い森に
入って迷ってしまってはいないのか?
ともかく 今自分達にできることは
登山口までどんなに時間がかかろうと歩ききり
この状況を誰かに伝えることだけ


時間が押しています
暗くなる前に下山できるでしょうか?
時計を見ながら ひとしさんが
ボソっとつぶやいた
休んでる間があったら少しでも下ろう

下っていく途中
数名の登山者とすれ違う
「すれ違う」っていう表現は間違っていた
彼らは山の神までの急登でテントを上げることを断念し
登山道の途中でテントを張っていたのだから

午後3時をすぎれば
山の夕暮れは早い
無理して布引山までテントを運ぶより
途中でビバーグする方がずっと利口な判断
山の神で手を併せた
正規ルートに戻れた感謝と
単独の彼の無事を祈る

下りやすいジグザグの急坂も
単なる枯葉が積もった足元の悪い道
ハァ ハァ
ハァ ハァ
ハァ
広河原付近にも同じように
ビバーグで夜を迎えようといている
登山者たちがテントを張る
ドカドカとスゴい勢いで下山する
ひとちがを テントの入口から見物
彼らは山頂の情報を少しでも聞きたいと
声をかけようと思ったのかもしれない
でもね 一刻も早く下山しなければ
山の夕暮れは待ってくれないのだ
ハァ ハァ
ハァ ハァ
ハァ
広河原の渡渉地点に来ると驚いた
前日より水が更に増水している

渡渉時 水面に出ていた岩は
深い流れの中にあり 渡渉は困難を極めた
それでも渡らなきゃ
時間が押している
コワいなんて
言ってる場合ぢゃない
渡渉地点を決め 一か八かで沢の流れに
ザボっ と両足突っ込んだ

ぬぉーっ
つ つめたい
相変わらず ひとしさんは身軽に反対岸へ
ひとしさんにサポートしてもらい
なんとか 渡渉成功
上陸した山靴の中は まるで水槽のようで
歩くたび ぐちゃぐちゃ と楽器みたいだ
それでも先に進まねばならん
時刻は5時半
もう薄暗い
ここから先の道には ガレ場などの
危険地帯があったはず
躊躇しているヒマはない
一刻を要する
見えにくくなっていく危ない登山道
それでもピッチを落とさず必死に歩いた
まだ危険な場所はありましたっけ?
危険地帯を通過するたびに
ひとしさんが声を上げる
たしか あの先にヤバい橋が・・・
行きに渡った危険な橋は確実に通過するため
帰路は崩れた橋の下に一端下りガレ場を登り返した
急がば回れ

足はフラフラ
鉄梯子・鉄の橋をクリアして
最後の吊り橋を渡った

ようやく廃屋に到着
時刻は6時50分
林道までどのくらいですか?
あと10分

すっかり闇夜になった
ヘッデン装着で林道終点まで下る
この先は平坦な林道 危ない箇所はない
暗やみの林道を大急ぎで歩く
午後7時半登山口
ゴール
駐車場に戻ると 単独の彼の車が
予想通りポツンと残っている
やっぱり下山できなかったんだ
大丈夫かな?
あのまま樹林帯の奥深くに迷い込んだら
出てこれませんね
どうします?
携帯電話がつながらない
大急ぎで近くの宿泊施設に飛びこんだ
緊急事態発生
警察に電話 単独の彼の状況を話した
とても疲れていた
それ以上に戻ってこない彼の事が心配だった
翌々日 警察に確認の電話を入れてみる
昨日 本人から電話がありましてね
ビバーグして登り返し下山したそうです
よかったぁー
単独の彼は経験豊富な山ヤだ
もしかして警察に電話なんかしたのは
余計なおせっかいだったかも
いいじゃん
彼は無事に下山できたんだから
まあね
笊ヶ岳の老平には登山ポストがない
もし道迷いしたり 事故に巻き込まれても
誰にも連絡がつかなければ遭難になってしまう
今回の山歩きで どんなに大変な山も
「がんばれば登れる」ってことを証明した

もうひとつ 思い込みによる「勝手な解釈」は
危険だっていうこと
そして 万が一を想定して連絡がつくような
準備を万端にしなければいけないことも同時に痛感した
*GW中 その後同じように笊ヶ岳で遭難した方がいます。(50代・男性)
5月15日現在まだ行方不明、捜索活動が続いているそうです。
一日も早く発見、救助されることを願っています。
笊ヶ岳に登山予定のある方は下山する際 道迷い に十分注意して下さい。
遭難した方のその後はこちら
GW大変な山歩き終了
翌日から3日間 筋肉痛で変な生き物のように
なっている ひとちがであった
(あはは。。。)

勝手な解釈?
笊ヶ岳
(赤石山脈南部エリア)
全山行 409回
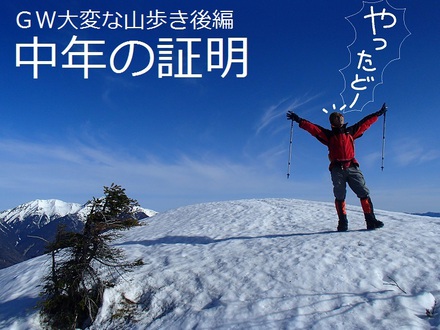
 笊ヶ岳の情報はこちら
笊ヶ岳の情報はこちら
 布引山の情報はこちら
布引山の情報はこちら
 前編はこちら
前編はこちら 
標高 布引山 2583.7m 笊ヶ岳 2629.0m
天気
 晴れ
晴れ山行時間 合計14時間30分
*布引山から登山口までは無積雪期通常のコースタイムであれば
5時間程度で下山できる。
今回は残雪期+道迷いのため9時間半かかった。(約2倍)
〈コース〉布引山テント(5:00)-笊ヶ岳山頂(6:50-7:20)-
布引山テント(9:00-10:00)-2000mf付近まで降下(11:20-11:30)-
小ピーク下2300m地点まで登る(1:30)-桧横手山(2:20-2:30)-
カーブ地点(3:30)-山の神(4:30-4:45)-広河原(5:30-5:40)-
廃屋(6:50)-林道終点(7:00)-老平(7:30)
山に入ることは自己責任

コースは自己の体力と技術を考慮し
無理のないルートを選ぶこと

進む以上は 最後まで自分の足で歩き
他人に頼らず迷惑をかけないこと

これが山ヤの鉄則

後 編
 夜 半
夜 半 
聞いたことのないような声で
動物が鳴いている

あ゛―
動物がテントに近寄ってきたみたいです

なんだろ? コワいですぅー

クマじゃないから別にいいじゃん

でもぉー
気になって

zzzzzz
いつのまにか 瀑睡

 朝だぁー
朝だぁー 
テントから顔を出すと
オレンジ色の太陽


ほぼ雪山装備のテン泊のため荷物は多けれど
足りない物・忘れ物もほとんどなく
快適な朝を迎えることができた

(うはは。)
おかげで ひとちはザックが重くて
ここまで大変だったんだもんねぇー

そうなんですぅー

それにしても今朝は 超元気

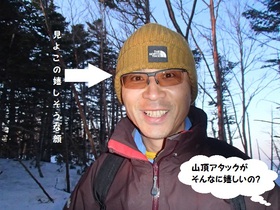
アタックザックだから軽くって
楽ちんですぅーっ!
あっ そう

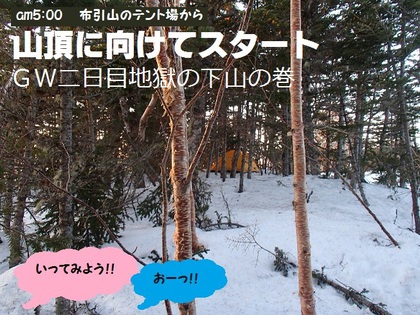
布引山付近は森林限界

鞍部までは東西両側の景色を随所で堪能できる

(うは! うは!)
東側の景色は 今まさにご来光を迎えた
我がホームグラウンド富士山

きれいですねぇ~


森林限界とはいえ 全く木々がないわけでなく
木々の間に残る深い雪の稜線は歩きにくい

(ぶぅ
 )
)
ひとちががテントを張った布引山のピークの
少し先に単独者のテントが張られていた

同じように彼も 「いざ笊の山頂に向けて出発」
というタイミング

見れば足元はスノーシュー

自由にアイゼンとスノーシューを分離できる
便利なコンパクトタイプだ

こんなに雪が深くて
ズボズボだと思わなかったよね

まったくですぅ


ひとちがといえば 8本歯のアイゼンに
夏用ストック ピッケルなし

ありゃ ダメじゃん

おかげで ウマる 転ぶ は当たり前

スマートにスノーシューで山頂方向に向かっている
彼とはエラい違いだ

あ~ぁ
わかってたら せめてワカン持ってくれば
よかったよねぇー


山はそんなに甘くない
鞍部に向かって歩いているうちに
すっかり陽が昇った


目の前には笊の姿


今日も快晴

午後には天気は曇り予報なので
できるだけ早く下山したい所

西側は このような景色

南アルプス南部の山々が勢揃い

こんな間近で見たのは初めてだ

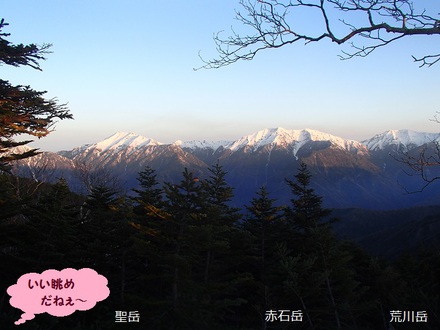
東西の山を交互に見ていると
すぐ先に 先行した彼が立ち止まり
やっぱり山を眺めている


そうなんだよねぇー

歩けば転び 進めばくすがり
ズボって ハマって
もー た~いへん



遊んでないし
気をつけてるつもりだしぃー

鞍部までたどりつくと
益々山の姿が大きくなった

(おぉ
 )
)
鞍部から先は急登

雪は見上げるような壁と化し
右は急な山斜面 左は絶壁なので
這い登って進むしかない


ぬぉーっ

なんとか這い登ったぞ

と ちょっと優越感に浸った

その先を見れば 手すりのない
スベリ台みたいな雪斜面

(げっ
 )
)左右どちらに滑り落ちても
滑落死か?

登るのはいいとして
下る時は倍増の怖さかもね

こーゆー場合
アイゼンをきせて登りたい所

 雪はユルユル
雪はユルユル 
雪にアイゼンは刺さらず足が
ズルズルと滑る

(ひゃぁー
 )
)
無積雪期なら もっと簡単に
ピークを踏めるのかな?
登ったことないんだから
わかるわけないじゃん

あ そうか

とうとう念願だった笊ヶ岳の山頂


残念なことに 楽しみにしていた
山頂標識は雪の下

でわ お待たせの景色を
ご覧いただこう

じゃ~ん

これぞ 特級品の富士山の眺望

今まで眺めた富士山の中でも
ダントツ一番だ と思った

そしてこちらは南側
テン泊した布引山


笊ヶ岳がメインみたいな気もするけど
実はこの布引山までの登りが大変なのだ

笊ヶ岳はオマケかい?
そーじゃないけどね

そして こちらが南西から北西に向かって続く
南アルプス南部の山々




自分達が がんばって登ったことに
大満足

山頂で合流した単独の彼としばしお話した

彼は オールシーズン日本アルプスを登り
経験豊富な実力ある山ヤだ と正直思った

その勝手な思い込みが後に仇となる

テン場までの帰路はピストンとはいえ
ウマる ハマる ことに変わりはない

(ぶぅ。)

無積雪期なら3時間程度で往復できるコースタイムも
4時間と 大幅に足が出てしまい 悪戦苦闘


どんなに大変でも嬉しかったのは
富士山がいつも横にいること


さぁ テン場は近いよ
がんばろっか!

振り返ると だんだん遠くなる笊兄弟


またねぇ~♪
再度この山を登る日がくるのだろうか?
たぶん しばらくはこないと思うけど

バカ大変だもんね

置き去りにしたテントをたたみ
布引山にも別れを告げる


今出発すれば登山口に
3時すぎには到着できますね

雪があるから多少時間がかかっても
5時までには十分下れるはずです

うん
余裕だね


布引山のピークのすぐ先は
「布引大崩れ」と呼ばれるガレ場


ここを起点に帰路の桧横手山方向と
青薙山方向に道は分岐している


いつものように 自分の目で赤テープを確認し
山の下山方向を見定めて進路をとれば
道間違いすることはなかったはず


ところが

山頂でお話した単独の彼 下山時もほぼ
ひとちがと同時出発で先行していた

登山者は前々日入った単独の二人のみ
トレースはあまりあてにならない

そこで 踏んだばかりの
彼のトレースを追っかけることにしたのだ

経験豊富な彼の後なら安心だね

赤テープ探さなくてもいいし
道迷いの心配もないもんね

勝手な思い込み


後方では いつものように ちがこさんを
信じてついてくる ひとしさんがいる


ちゃんと足跡ありますか?
あるよー
まだ靴底の模様が消えない新しいのだから
見落すわけないじゃん

油断した

あれよ あれよと言う間に
トレースは急斜面を下っていく

疑うことなく追う ひとちが


ん?
途中で異変に気付いた

こんな場所通ったかな?
斜めにトラバースして登った覚えないけど
もっと左に下らなきゃ変だよね?
どこでも同じように見えるもんです

でもおかしいですね

南西に下ってる気がします


だよね

地図だと尾根を東にカーブしながら下るはず

曲がるポイントがあるはずなんだけどな・・・
あれ?
尾根が右上に見えますよ

何か変だな

でもさー 先行者もここを確実に下ってるし
登り返したトレースもなし
もしかして東に山を周り込むつもりかな?

うじゃうじゃ討論するものの
やっぱり不安は隠しきれない

げっ
あれ見て

とんでもない物を見つけてしまった

左方向に大きな崩れ場

その上には たぶん青薙山方向へ
向かうであろう稜線が見えた


ということは・・・
思いっきり正規ルートとは違う
別斜面を下ってしまっているってこと?
そうみたいですぅ

慌てて地図を出し正置してみる

見上げると 本来通過しなきゃいけない
小ピークのとんがりが見えた

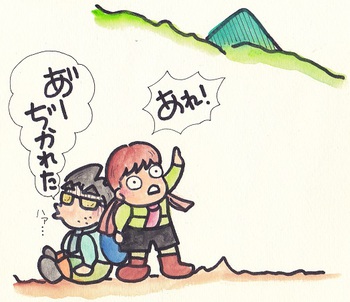
や やっぱ違うよ
山の反対側に下ってる

トレースを探した

さっきまで雪の上にくっきりついていたトレースは
標高を下げると雪と共に消え見当たらない

恐ろしいほどの急斜面を無理やり下ってしまったのだから
今更登り返すってわけにもいかない


どうしよう

どうします?
やっぱ尾根に戻ろうよ

登れそうな場所を選んで小ピーク方向に
登っていくしかないよ

え゛―
この荷物背負って
また登らなきゃいけないんですか?
もう限界ですぅー

仕方ないよ

このままトラバースして正規ルートに戻ろうとしても
果たして歩けるような場所があるかわかんないしぃ

決断したら登る

アイゼンを外し 雪のなくなった踏まれていない
フカフカの山斜面を必死に登っていく

ハァ
 ハァ
ハァ ハァ
ハァ
バリバリとヤブを押しのけ 尾根に向かって
ひたすら登っていくしかない

どのくらい時間が過ぎたのか?
すっかり気持ちが萎えてしまったのか
ひとしさんの足取りは重く
なかなか ちがこさんに追いつけない

ようやく尾根らしき場所に出た

このまま戻れば 正規ルートに戻れるはず

ファイトー!
自信があった

必ず赤テープはある

ねぇ がんばって登ろ

「信用ならぬ」といった顔でノロノロと
言葉なくひたすら登る ひとしさん

あったぁー

木についている赤テープ発見

正規ルートに戻れた


*ちなみにこれは ひとちがが道迷いしたルートです・・・

戻れる

時間はかかるだろうけど
必ず登山口へ下山できる


心配だったのは 道間違えして
樹林帯方向へ下ってしまった単独の彼のこと

登り返すこともせず そのまま深い森に
入って迷ってしまってはいないのか?
ともかく 今自分達にできることは
登山口までどんなに時間がかかろうと歩ききり
この状況を誰かに伝えることだけ



時間が押しています

暗くなる前に下山できるでしょうか?
時計を見ながら ひとしさんが
ボソっとつぶやいた

休んでる間があったら少しでも下ろう


下っていく途中
数名の登山者とすれ違う

「すれ違う」っていう表現は間違っていた

彼らは山の神までの急登でテントを上げることを断念し
登山道の途中でテントを張っていたのだから


午後3時をすぎれば
山の夕暮れは早い

無理して布引山までテントを運ぶより
途中でビバーグする方がずっと利口な判断

山の神で手を併せた

正規ルートに戻れた感謝と
単独の彼の無事を祈る


下りやすいジグザグの急坂も
単なる枯葉が積もった足元の悪い道

ハァ
 ハァ
ハァ ハァ
ハァ
広河原付近にも同じように
ビバーグで夜を迎えようといている
登山者たちがテントを張る

ドカドカとスゴい勢いで下山する
ひとちがを テントの入口から見物

彼らは山頂の情報を少しでも聞きたいと
声をかけようと思ったのかもしれない

でもね 一刻も早く下山しなければ
山の夕暮れは待ってくれないのだ

ハァ
 ハァ
ハァ ハァ
ハァ
広河原の渡渉地点に来ると驚いた

前日より水が更に増水している


渡渉時 水面に出ていた岩は
深い流れの中にあり 渡渉は困難を極めた

それでも渡らなきゃ

時間が押している

コワいなんて
言ってる場合ぢゃない

渡渉地点を決め 一か八かで沢の流れに
ザボっ と両足突っ込んだ


ぬぉーっ

つ つめたい

相変わらず ひとしさんは身軽に反対岸へ

ひとしさんにサポートしてもらい
なんとか 渡渉成功

上陸した山靴の中は まるで水槽のようで
歩くたび ぐちゃぐちゃ と楽器みたいだ

それでも先に進まねばならん

時刻は5時半
もう薄暗い

ここから先の道には ガレ場などの
危険地帯があったはず

躊躇しているヒマはない
一刻を要する

見えにくくなっていく危ない登山道

それでもピッチを落とさず必死に歩いた

まだ危険な場所はありましたっけ?
危険地帯を通過するたびに
ひとしさんが声を上げる

たしか あの先にヤバい橋が・・・
行きに渡った危険な橋は確実に通過するため
帰路は崩れた橋の下に一端下りガレ場を登り返した

急がば回れ

足はフラフラ

鉄梯子・鉄の橋をクリアして
最後の吊り橋を渡った


ようやく廃屋に到着

時刻は6時50分

林道までどのくらいですか?
あと10分

すっかり闇夜になった

ヘッデン装着で林道終点まで下る

この先は平坦な林道 危ない箇所はない

暗やみの林道を大急ぎで歩く

午後7時半登山口

ゴール

駐車場に戻ると 単独の彼の車が
予想通りポツンと残っている

やっぱり下山できなかったんだ
大丈夫かな?
あのまま樹林帯の奥深くに迷い込んだら
出てこれませんね

どうします?
携帯電話がつながらない

大急ぎで近くの宿泊施設に飛びこんだ

緊急事態発生
警察に電話 単独の彼の状況を話した

とても疲れていた

それ以上に戻ってこない彼の事が心配だった

翌々日 警察に確認の電話を入れてみる

昨日 本人から電話がありましてね

ビバーグして登り返し下山したそうです

よかったぁー

単独の彼は経験豊富な山ヤだ

もしかして警察に電話なんかしたのは
余計なおせっかいだったかも

いいじゃん
彼は無事に下山できたんだから

まあね

笊ヶ岳の老平には登山ポストがない
もし道迷いしたり 事故に巻き込まれても
誰にも連絡がつかなければ遭難になってしまう

今回の山歩きで どんなに大変な山も
「がんばれば登れる」ってことを証明した


もうひとつ 思い込みによる「勝手な解釈」は
危険だっていうこと

そして 万が一を想定して連絡がつくような
準備を万端にしなければいけないことも同時に痛感した

*GW中 その後同じように笊ヶ岳で遭難した方がいます。(50代・男性)
5月15日現在まだ行方不明、捜索活動が続いているそうです。
一日も早く発見、救助されることを願っています。
笊ヶ岳に登山予定のある方は下山する際 道迷い に十分注意して下さい。
遭難した方のその後はこちら
GW大変な山歩き終了
翌日から3日間 筋肉痛で変な生き物のように
なっている ひとちがであった

(あはは。。。)

2014年05月12日
中年の証明♪ 前編
2014/05/02
テン泊始まる!
笊ヶ岳
(赤石山脈南部エリア)
全山行 409回

 笊ヶ岳の情報はこちら
笊ヶ岳の情報はこちら
 布引山の情報はこちら
布引山の情報はこちら
標高 布引山 2583.7m
天気 晴れ
晴れ
山行時間 9時間
〈コース〉初日:老平駐車場(7:30)-林道終点(8:15)-廃屋-
広河原(9:25-9:30)-山の神(10:45-10:55)-カーブ地点(12:25)-
桧横手山(1:45)-小ピーク(3:30)-布引山山頂(4:30)
GWが始まった
今年はサブい雪山が終わったら
「大変な山を選んで登る」
という目標を立てていた
いよいよ春山シーズン到来
前 編
これまで 日本百名山・山梨百名山・信州百名山・
甲信越百名山 などを せっせと登ってきたが
それぞれが残り1/4程度となった
残っている山たちといえば 簡単に登れそうな山
もしくは 大変で背を向けたくなるような山
今だから登れる
今じゃなければ登れない
ということで あえて今年は大変な山 を
チョイスして登ることにする
あーぁ 無理しちゃって
ヤメた方がいいんじゃない?
うるさいな
「中年の証明」 として
身体にムチ打ってがんばってみよう
大変初っ端 ちがこさんが選んだのは
なんと笊ヶ岳
笊?
ってあの笊?
そう あの笊
このお山 山頂まで行程が長い上
水場もなく テン場もなく
もちろん小屋もあるわけない
登れる自信がありません
不安で歪む顔の ひとしさんをなだめすかし
登山口のある老平に車を走らせた
(あはは。。。)
先着はすでに3台

GWといっても 「一筋縄では登れない山」
というだけあって登山者の数も少ないようだ
スタート前からザックを背負った ひとしさん
すでにこのような状態

それでも登らにゃ
山頂にはつけん
が がんばります
民家の横を通過しゲートをくぐる

林道は平坦で 勢いよく流れる奥沢谷を左手に
山に向かって続いていた

荷物が重いですぅ
ひとしさんは ちがこさんの前を
無言で歩いていく

こーゆー時ってさ
ひとち ヤバいよね
いつもじゃ うじゃうじゃ話しながら歩く
余裕の林道も今日は静かなもんだ
あんまり楽しくない
見た目は大きいものの 中身は軽い
ちがこさんのザック
(うは! うは!)
ザックの重さにあえぐ ひとしさんを前に
沢沿いに咲く花たちの撮影に余念ない


今日は ちがこさんが撮影隊
えへ
ちがこさんも もう少し
ひとちの荷物持ってあげたら?
いいの!
首と腰がヘルニアだから
先生が「重たいもの持っちゃダメ」
って言ったもん
ふ~ん
ひとち がんばってね
はい がんばりますぅ
白く浮き出るような気持ち悪いトンネルが現れた
数年前に崩れたらしい

恐々通過
青空と新緑に今日の目的地
布引山のピークが高い
山頂付近はまだ残雪

新緑は益々美しさを増し
芽吹いて開いたばかりの柔らかそうな葉が
木漏れ陽となってワクワクする

秋になれば赤く色づく葉っぱも
こんなステキな薄みどり

林道終点からいよいよ山道が始まった

10分ほど登ると昔懐かしい農家の廃屋

林道終点から廃屋までは おもいっきり山道で
電燈もなけりゃ 細くて険しい
この家に住んでた人は
日常が山登りだったわけね
それほど崩壊が進んでいるわけでもなく
まだ人が十分に住めそうな家
たぶん住む人はいないと思うけど
廃屋のすぐ先の大木の下には
小さな石塔がひとつ
静かに手を併せ
今回の山行の無事を祈る

タケ沢との合流付近はガレ場で
足場も悪く慎重に通過していく

振り返るとすっかり里から離れ
緑の山に囲まれていた

岩壁につけられた梯子には
最大総重量が記載
荷物が重くても
100キロは越えないから大丈夫だね

沢を横断する大きな吊橋登場

この吊橋 両サイドのロープがぐにゃぐにゃの
太いホース状のものでできているため
つかまってもコワいばかりで意外と役立たず
なるべ~く つかまないように
バランスをとって橋を渡るっきゃない
ひやぁ~っ

鉄の橋が続き どんどん道幅が狭くなる

岩壁の下に噴き出した水を得て
水場に咲く花たちが目を引く


ほぼ水平の道は沢沿いをずっと続く
所々崩壊しそうな危険なガレ場がたびたび出現

そのたびに 歩くペースは遅くなり
沢に転がり落ちるよりマシか と
慎重に通過しざるを得ない

鉄の橋やら岩壁が終わった
その先は道幅もまあまあ広く
ペースを上げて歩けるかと思いきや
いきなり現れたのは

山崩れした上部から木が倒れのしかかり
重みを少しかければ折れた橋は落下しかねない
先は這い登るような登り
どうすりゃいいの?
しばし立ち止まって うじゃうじゃ対策
この橋渡っても
落っこちないよね?
微妙な感じですね
上部には巻き道もないし
下に踏み跡みたいのがあるけど
崩れに一端降りて通過する?
や
行けますよ
そう言うと ひとしさんは果敢にも
折れて崩壊寸前の橋を渡り始めた

心の中で思った
これって あの時 みたいだ

危ない場所は ちがこさんが先に行くべきだ
ひとしさんが落っこちたら助けられない
今度は雪がないから
落ちたら怪我するよ
そうだよね
考えている間に ひとしさんは
橋の反対側付近まで到達
あの時は橋から落ちた
でも今度は違う
た 助けてくださぁ~い

う うごけませぇ~ん
倒木にザックが引っかかって
先に進めない
慌てて ひとしさんを追って
ちがこさんも折れた橋の上
ぎゃ
橋が壊れてふたりとも落ちるかも
緊張が走る
(なんとか ひとしさん救出成功 )
)
と
今度は ちがこさんが引っかかった
あたしも うごけないーっ

緊張が走る
(なんとか ちがこさん救出成功 )
)
あ゛―
コワかった
その先も

そして見つけたこの看板

最初に「水場はない」と記載したけど
広河原で水は汲むことができる
しかぁ~し 荷物をおろし
ザックを解体してまで水を汲むってのもねー
ということで 重いこと承知で
水は詰め込んできた
結果 ひとしさんのザックは
尋常なく重い

広河原に降りると そこには恐ろしげな
景色が広がっていた

鉄砲水のごとく流れる雪解け水
それって大げさじゃない?
いいの
ちがこさんにはそう見えたんだから
探ってみても
どこから渡ればいいのかわからない
渡るべきか?
渡らぬべきか?

渡らなきゃ
山頂には行けないよ
そうですね
意を決して ひとしさんが宙を舞う
びよよ~ん

ザックは重くとも火事場のバカ力
見事に岩に張りつき ひとしさんは対岸へ
やるじゃん
ひとち!
えへ
反して ちがこさんといえば
あまりのコワさに飛び移る勇気がない

どうしよっかな?
ザブンと足をつっこめば渡れるかな?
無理 無理 絶対無理!
微妙に遠い対岸の岩
鈍い ちがこさんには飛びつけない
渡れない
でも 渡らなきゃ

私が引っ張りますから
飛んで下さい
さあ 手を出して
つかんだら 放さないでよ
絶対だよ
意を決して ちがこさん飛んだ

え゛

放さないって言ったじゃん
ヤバかったね
危うくひっくり返って
流される寸前に見えたよ
うるさい
とりあえず今日の危険個所は
ほぼクリアできたと思う
しかぁ~し これからが大変なのだ
目の前には見上げるような急登

登れ! 登れ!
必死に登ろうとはするものの
ひとしさんのザックは重く
足元がおぼつかない

地図には「歩きやすいジグザグの道」と記載
ダマされちゃいけない
歩きやすくとも 急登は急登 だ

この辺りに咲いていたのはこの花

緑の中に薄紫が目立つ
落ちた花は まるで茶色の枯葉のジュータンに
ピンクの水玉模様のようだ
がんがん登っていく

くそー くそー
ペースの上がらない ひとしさんを前に
撮影隊の ちがこさん
枯葉の中に かわいい子み~っけ
まだ ちょっと早いね
もう少し枯葉のお布団の中にいてね

ひとしさんが言った
荷物のバランスが悪いじゃないですか?
やたら大変で ちっとも登れません

それって ちがこさんに
「荷物持て」 ってこと?
ひとしさんのザックから 3キロの荷物が
ちがこさんの背中に移動した
たかが3キロ
されど3キロ
ようやく山の神まできた

 心はすでに遠い世界へ
心はすでに遠い世界へ
放心状態

どんなに大変でも
登らにゃ山頂にはつけん
わかってるよぉーっ
ヒィ ヒィ
ヒィ

今度は ちがこさんの足が進まない
3キロの荷物でバランスが崩れた
1キロ持ちますよ
ちがこさんの背中から
1キロ分の荷物がなくなった

たかが1キロ
されど1キロ

あ~
楽ちん♪
ガレ場を通過

がんばって登った分 景色はいい

少し先に進むと
不法投棄された廃材が目に付く



昔 山の仕事をした人たちが
そのまんまにしていったんだね
あまり気持ちいいもんじゃないですね
こんなに高い場所に こんなにたくさん
自然じゃないものが残されたままになっている
麓から見えた残雪地帯に突入

まだ雪の残る春山の笊には
踏み入った登山者は少ないらしく
トレースはほとんどない
ズボズボの上 急登だから
登りにくいったらありゃしない

座る場所もないので休憩することもなく
ひたすら登り続ける
ハァ ハァ
ハァ ハァ
ハァ

この山の登りハンパぢゃない
登った人だけしかわからない
そういう割には楽しんでない?
えへへ
まぁね

広い尾根状の桧横手山のピークを通過

次の小ピークはでは更に辛い登り
な なんて大変なんだ・・・

足がフラフラになってきた
もうこれ以上登れないと思った
と
ポンと出た

こーなると俄然元気だね
どのピークかは定かでないけど
青薙山が見えているはず

さっきまで瀕死状態だった
ひとしさんも この笑顔

このガレ場を登りきれば
目的地の布引山

よくここまで がんばったね
あと少しだから気を抜かないで

南アルプス南部の山々が
ずら~っと並ぶ感動の景色

ガスが出始め 少し暗くなり始めた

最後の力を振り絞って
とうとう布引山までザックを上げた
尋常ない達成感

誰もいないピークの奥に
風邪に飛ばされないようお家を建てる

静かなる山の夕暮れ
*この日 布引山まで登りきったのは
ひとちがと単独の登山者 合計3名であった

明日は早朝ピークハント
どんな景色を見ることができたのか?
次回のブログをお楽しみに~

後編はこちら
テン泊始まる!
笊ヶ岳
(赤石山脈南部エリア)
全山行 409回

 笊ヶ岳の情報はこちら
笊ヶ岳の情報はこちら
 布引山の情報はこちら
布引山の情報はこちら
標高 布引山 2583.7m
天気
 晴れ
晴れ山行時間 9時間
〈コース〉初日:老平駐車場(7:30)-林道終点(8:15)-廃屋-
広河原(9:25-9:30)-山の神(10:45-10:55)-カーブ地点(12:25)-
桧横手山(1:45)-小ピーク(3:30)-布引山山頂(4:30)
GWが始まった

今年はサブい雪山が終わったら
「大変な山を選んで登る」
という目標を立てていた

いよいよ春山シーズン到来

前 編
これまで 日本百名山・山梨百名山・信州百名山・
甲信越百名山 などを せっせと登ってきたが
それぞれが残り1/4程度となった

残っている山たちといえば 簡単に登れそうな山
もしくは 大変で背を向けたくなるような山

今だから登れる

今じゃなければ登れない

ということで あえて今年は大変な山 を
チョイスして登ることにする

あーぁ 無理しちゃって

ヤメた方がいいんじゃない?
うるさいな

「中年の証明」 として
身体にムチ打ってがんばってみよう

大変初っ端 ちがこさんが選んだのは
なんと笊ヶ岳

笊?
ってあの笊?
そう あの笊

このお山 山頂まで行程が長い上
水場もなく テン場もなく
もちろん小屋もあるわけない

登れる自信がありません

不安で歪む顔の ひとしさんをなだめすかし
登山口のある老平に車を走らせた

(あはは。。。)
先着はすでに3台


GWといっても 「一筋縄では登れない山」
というだけあって登山者の数も少ないようだ

スタート前からザックを背負った ひとしさん
すでにこのような状態


それでも登らにゃ
山頂にはつけん

が がんばります

民家の横を通過しゲートをくぐる


林道は平坦で 勢いよく流れる奥沢谷を左手に
山に向かって続いていた


荷物が重いですぅ

ひとしさんは ちがこさんの前を
無言で歩いていく


こーゆー時ってさ
ひとち ヤバいよね

いつもじゃ うじゃうじゃ話しながら歩く
余裕の林道も今日は静かなもんだ

あんまり楽しくない

見た目は大きいものの 中身は軽い
ちがこさんのザック

(うは! うは!)
ザックの重さにあえぐ ひとしさんを前に
沢沿いに咲く花たちの撮影に余念ない



今日は ちがこさんが撮影隊

えへ

ちがこさんも もう少し
ひとちの荷物持ってあげたら?
いいの!
首と腰がヘルニアだから
先生が「重たいもの持っちゃダメ」
って言ったもん

ふ~ん

ひとち がんばってね

はい がんばりますぅ

白く浮き出るような気持ち悪いトンネルが現れた

数年前に崩れたらしい


恐々通過

青空と新緑に今日の目的地
布引山のピークが高い

山頂付近はまだ残雪


新緑は益々美しさを増し
芽吹いて開いたばかりの柔らかそうな葉が
木漏れ陽となってワクワクする


秋になれば赤く色づく葉っぱも
こんなステキな薄みどり

林道終点からいよいよ山道が始まった


10分ほど登ると昔懐かしい農家の廃屋


林道終点から廃屋までは おもいっきり山道で
電燈もなけりゃ 細くて険しい

この家に住んでた人は
日常が山登りだったわけね

それほど崩壊が進んでいるわけでもなく
まだ人が十分に住めそうな家

たぶん住む人はいないと思うけど

廃屋のすぐ先の大木の下には
小さな石塔がひとつ

静かに手を併せ
今回の山行の無事を祈る


タケ沢との合流付近はガレ場で
足場も悪く慎重に通過していく


振り返るとすっかり里から離れ
緑の山に囲まれていた


岩壁につけられた梯子には
最大総重量が記載

荷物が重くても
100キロは越えないから大丈夫だね


沢を横断する大きな吊橋登場


この吊橋 両サイドのロープがぐにゃぐにゃの
太いホース状のものでできているため
つかまってもコワいばかりで意外と役立たず

なるべ~く つかまないように
バランスをとって橋を渡るっきゃない

ひやぁ~っ


鉄の橋が続き どんどん道幅が狭くなる


岩壁の下に噴き出した水を得て
水場に咲く花たちが目を引く



ほぼ水平の道は沢沿いをずっと続く

所々崩壊しそうな危険なガレ場がたびたび出現


そのたびに 歩くペースは遅くなり
沢に転がり落ちるよりマシか と
慎重に通過しざるを得ない


鉄の橋やら岩壁が終わった

その先は道幅もまあまあ広く
ペースを上げて歩けるかと思いきや

いきなり現れたのは


山崩れした上部から木が倒れのしかかり
重みを少しかければ折れた橋は落下しかねない

先は這い登るような登り

どうすりゃいいの?
しばし立ち止まって うじゃうじゃ対策

この橋渡っても
落っこちないよね?
微妙な感じですね

上部には巻き道もないし

下に踏み跡みたいのがあるけど
崩れに一端降りて通過する?
や

行けますよ

そう言うと ひとしさんは果敢にも
折れて崩壊寸前の橋を渡り始めた


心の中で思った

これって あの時 みたいだ


危ない場所は ちがこさんが先に行くべきだ

ひとしさんが落っこちたら助けられない

今度は雪がないから
落ちたら怪我するよ

そうだよね

考えている間に ひとしさんは
橋の反対側付近まで到達

あの時は橋から落ちた

でも今度は違う

た 助けてくださぁ~い


う うごけませぇ~ん

倒木にザックが引っかかって
先に進めない

慌てて ひとしさんを追って
ちがこさんも折れた橋の上

ぎゃ

橋が壊れてふたりとも落ちるかも

緊張が走る

(なんとか ひとしさん救出成功
 )
)と
今度は ちがこさんが引っかかった

あたしも うごけないーっ


緊張が走る

(なんとか ちがこさん救出成功
 )
)あ゛―
コワかった

その先も


そして見つけたこの看板


最初に「水場はない」と記載したけど
広河原で水は汲むことができる

しかぁ~し 荷物をおろし
ザックを解体してまで水を汲むってのもねー

ということで 重いこと承知で
水は詰め込んできた

結果 ひとしさんのザックは
尋常なく重い


広河原に降りると そこには恐ろしげな
景色が広がっていた


鉄砲水のごとく流れる雪解け水

それって大げさじゃない?
いいの

ちがこさんにはそう見えたんだから

探ってみても
どこから渡ればいいのかわからない

渡るべきか?
渡らぬべきか?

渡らなきゃ
山頂には行けないよ

そうですね

意を決して ひとしさんが宙を舞う

びよよ~ん

ザックは重くとも火事場のバカ力

見事に岩に張りつき ひとしさんは対岸へ

やるじゃん
ひとち!
えへ

反して ちがこさんといえば
あまりのコワさに飛び移る勇気がない


どうしよっかな?
ザブンと足をつっこめば渡れるかな?
無理 無理 絶対無理!
微妙に遠い対岸の岩
鈍い ちがこさんには飛びつけない

渡れない

でも 渡らなきゃ


私が引っ張りますから
飛んで下さい

さあ 手を出して

つかんだら 放さないでよ

絶対だよ

意を決して ちがこさん飛んだ


え゛


放さないって言ったじゃん

ヤバかったね

危うくひっくり返って
流される寸前に見えたよ

うるさい

とりあえず今日の危険個所は
ほぼクリアできたと思う

しかぁ~し これからが大変なのだ
目の前には見上げるような急登


登れ! 登れ!
必死に登ろうとはするものの
ひとしさんのザックは重く
足元がおぼつかない


地図には「歩きやすいジグザグの道」と記載

ダマされちゃいけない
歩きやすくとも 急登は急登 だ


この辺りに咲いていたのはこの花


緑の中に薄紫が目立つ

落ちた花は まるで茶色の枯葉のジュータンに
ピンクの水玉模様のようだ

がんがん登っていく


くそー くそー
ペースの上がらない ひとしさんを前に
撮影隊の ちがこさん
枯葉の中に かわいい子み~っけ

まだ ちょっと早いね
もう少し枯葉のお布団の中にいてね


ひとしさんが言った

荷物のバランスが悪いじゃないですか?
やたら大変で ちっとも登れません


それって ちがこさんに
「荷物持て」 ってこと?
ひとしさんのザックから 3キロの荷物が
ちがこさんの背中に移動した

たかが3キロ
されど3キロ

ようやく山の神まできた


 心はすでに遠い世界へ
心はすでに遠い世界へ
放心状態

どんなに大変でも
登らにゃ山頂にはつけん

わかってるよぉーっ

ヒィ
 ヒィ
ヒィ

今度は ちがこさんの足が進まない

3キロの荷物でバランスが崩れた

1キロ持ちますよ

ちがこさんの背中から
1キロ分の荷物がなくなった


たかが1キロ
されど1キロ


あ~
楽ちん♪
ガレ場を通過


がんばって登った分 景色はいい


少し先に進むと
不法投棄された廃材が目に付く




昔 山の仕事をした人たちが
そのまんまにしていったんだね

あまり気持ちいいもんじゃないですね

こんなに高い場所に こんなにたくさん
自然じゃないものが残されたままになっている

麓から見えた残雪地帯に突入


まだ雪の残る春山の笊には
踏み入った登山者は少ないらしく
トレースはほとんどない

ズボズボの上 急登だから
登りにくいったらありゃしない


座る場所もないので休憩することもなく
ひたすら登り続ける

ハァ
 ハァ
ハァ ハァ
ハァ

この山の登りハンパぢゃない

登った人だけしかわからない

そういう割には楽しんでない?
えへへ
まぁね


広い尾根状の桧横手山のピークを通過


次の小ピークはでは更に辛い登り

な なんて大変なんだ・・・

足がフラフラになってきた

もうこれ以上登れないと思った

と
ポンと出た


こーなると俄然元気だね

どのピークかは定かでないけど
青薙山が見えているはず


さっきまで瀕死状態だった
ひとしさんも この笑顔


このガレ場を登りきれば
目的地の布引山


よくここまで がんばったね
あと少しだから気を抜かないで


南アルプス南部の山々が
ずら~っと並ぶ感動の景色


ガスが出始め 少し暗くなり始めた


最後の力を振り絞って
とうとう布引山までザックを上げた

尋常ない達成感


誰もいないピークの奥に
風邪に飛ばされないようお家を建てる


静かなる山の夕暮れ
*この日 布引山まで登りきったのは
ひとちがと単独の登山者 合計3名であった


明日は早朝ピークハント

どんな景色を見ることができたのか?
次回のブログをお楽しみに~


後編はこちら
2011年08月31日
アルプスの虹♪ 2
2011/8/28・29
雄大なアルプスを歩き抜け!
荒川三山・赤石岳
(赤石山脈南部エリア)
全山行 250回

 前日の山歩きはこちら
前日の山歩きはこちら
標高 千枚岳 2879.8m 丸山 3032m 東岳 3141m 中岳 3083.2m
前岳 3068m 小赤石岳 3081m 赤石岳 3120.1m
天気 晴れ・
晴れ・ ガス
ガス
山行時間 28日:9時間30分 29日:2時間30分
〈コース〉28日:千枚小屋(5:00)-千枚岳-丸山-東岳-中岳-前岳-荒川小屋-大聖寺平-小赤石岳-赤石岳-富士見平-赤石小屋(2:30)
29日:赤石小屋(5:00)-樺段-椹島ロッジ(7:30-8:00)-バスで移動-畑薙ダム駐車場(9:00)
どこまでも続く美しい稜線・・・
そこわぁー、奥深い雄大な南アルプスを満喫できるパラダイスロード♪
アルプスからの予期せぬプレゼント、それは?
虹♪
真夜中の 小屋のトタン屋根に落ちる賑やかな雨粒の音にもマケズ 今日も元気に目覚めた
ひとちが
(うはは!)
ぶぉぉぉぉーーーーっ!
よく寝たぞぉ~っ!!
早朝4:00に電気がついた
うっすらと窓から花畑が浮かび上がっている。
「もう雨上がったかなぁー?」
ずりぃーっ
窓を開けて手を出す ちがこさん。
「うは!雨降ってないしぃ~、こりゃお天気いいかもよ♪」

昨夜はちょいと心配だったお天気も おかげさまでなんとかなりそうだ。
(うひひひ。。。)
次々と出発を始める登山者たち、ひとちがも5:00スタート
小屋付近の花畑を一気に登る。
建設中の小屋が どんどん小さくなっていく

お世話になりましたぁーっ♪
 森林限界であ~る
森林限界であ~る
去年は暑さのためにカレカレだった ナナカマドの葉っぱも今年は青々、露に濡れて嬉しそう
色づき始めた実が 紅葉を期待させてくれるねぇー
紅葉を期待させてくれるねぇー


さぁ~てと、
いよいよ稜線に突入だぁーっ!
千枚岳までの岩場の稜線、そこはマツムシソウの花畑
薄紫の大輪が秋を感じさせてくれる
わぁ~ぉ♪
超キレイじゃん!!


ちがこさんは夢中だ
後方にせまってくる登山者など気にすることなく 立ち止まっては花を眺め ちょいと進んではまた止まる
狭い稜線 = 花見物 = 大迷惑

ひとしさんがムッとしている
何故かって?
混雑してるから 後先を歩く登山者が気になって仕方ないのであ~る。
その上、賑やかなおぢさんのスペシャルトーク付ときた
列を成して歩く=間隔が狭い=
いやでも声が聞こえる
 そう・・・
そう・・・
誰にも邪魔されず マイペースに静かに歩きたいわけ。
それじゃなくても 横には騒々しく ひとりしゃべりまくる ちがこさんがいるわけだから音はいらない
(うはははは!)
千枚岳に到着。
(よっしゃ )
)
さえぎるもののない大パノラマにしばし圧倒され言葉も出ない。

あっ! 虹が!
ひとしさんが指さした方向、これから進むべき赤石岳に虹がかかっている
朝日が山にあたり虹は七色に 輝く
輝く
奥深い南部のこの稜線まで がんばって登ってきた登山者にプレゼントなのか?

ひとちが 大感激♪

納得できる名前の丸山に向かう。
ホントまん丸いハゲ山であ~る
マツムシソウとトリカブト、そしてタカネビランジの花畑をゴキゲンで行進する


すっかり日が昇り、これから向かう悪沢岳は ゴツゴツと奇怪な山頂を覗かせ、遥か彼方 たどりつけるか不安な赤石岳も雲が切れ どでかい山容を見せていた。

悪沢岳

赤石岳
振り返ると富士山♪

いいねぇーっ!!
右を向いても 左を向いても山ばっか
大抵の山は裾に村や建物が見えたりするけど ここは山しかない。
(うん、うん )
)

まさに 山のオンパレード!

ずんずん登ろう 先は長いのだ
丸山に到着、賑やかなおぢさんを追い抜き間隔を空けたい所

ひとしさんが憧れていた悪沢岳は もう目の前に迫っている。
バランスをとりながら岩をピョンピョン飛び越え山頂に向かおう

荒々しい岩場の山頂、ついに南アルプス南部の最高峰に到着♪
(やったね )
)

スゴイ! スゴすぎる!!
ひとしさん うるうる・・・



同じ稜線上の山とは思えないような荒々しい景色が広がっていた
のんびりはしていられない、先を急ごう!

ザレた急坂を下り お花畑をちらちら見ながら中岳へ。
てっぺんにあるのは 中岳避難小屋。
小屋には管理人さんが無線中、大きな小屋とは違いボロボロじゃん
(あらら )
)


中岳を越え、分岐にザックをデポして前岳に向かってみた。

山頂の標識は・・・
あと少しで山から落っこちそうなのだ
何故かって?
山が半分崩れちゃってるからだよ!

中岳の大崩落、覗くだけでも恐ろしい
たぶん・・・
何年か先には この山頂標識はないと思う
ってうか、大きな地震でもあったら明日にでも標識は崩れに飲み込まれてしまうに違いない

荒川小屋に向けて一気に高度を下げる。
山の斜面はガレ場が続き、鹿の食害から花を守るためのネットが張られている。
ネットの前には入口があり、登山道はその中を通過しなければいけない。
ネットの扉の開け閉め→登山道→ネットの扉の開け閉め→登山道
→ネットの扉の開け閉め→登山道→ネットの扉の開け閉め

と繰り返すこと数回、九十九折になっているから仕方ないとはいえ 面倒くさいルートであった
(あはははは、、、)
赤い屋根発見♪
荒川小屋であ~る

快適そうな小屋、振り返れば ここから眺める荒川三山は素晴らしい。
次の機会には是非小屋を利用してみたいものであ~る。
(うん、うん )
)

小屋からは下った分だけ急な登り。
小屋が小さくなっていく


さすがに疲労し始めた足にはキツイ登りだよね ひとしさん
チングルマの綿毛が風に揺れていた
花も綺麗だけど ちがこさんは綿毛のチングルマの方が好きかな。

あっ♪
綺麗なちょうちょ!!

 キタベリタテハが花畑を舞っていた。
キタベリタテハが花畑を舞っていた。
何故だか ひとしさんが好きらしくズボンから離れようとしない蝶。
恋する相手が違いませんか?
(うはは。。。)
振り返ると荒川三山岳が笑っていたよ

再び 森林限界を抜け大聖寺平のトラバース道に突入
森林限界を抜け大聖寺平のトラバース道に突入

きゃぁーっ♪
超キレイ!!

ここわぁー、最高です♪
まるで童話のハイジの世界
ペーターっ!!

思わず大声でヤギを追うペーターを探してしまう ちがこさん
振り返ると自分たちの歩いてきた道が一望。

うぉぉぉぉぉーーーーっ!
目の前に でっかい山が立ちふさがっている
赤石岳ぢゃない、そう、まだ手前に でっかい山があった
小赤石岳であ~る
これ登るんかいな・・・

思わず見上げて溜息をつく ひとちが
天気もガスが出始めたこの時間帯、急がねば赤石岳はガスガスになりそうな予感
トウヤクリンドウの花畑が広がる


いっそげぇーっ!!
 うが
うが  うが
うが  うが
うが  うが
うが
はぁ、はぁ はぁ、はぁ・・・
 うが
うが  うが
うが  うが
うが  うが
うが
はぁ、はぁ はぁ、はぁ・・・
苦しくともジグザグの坂道を必死で登るっきゃない
どんどん上がる標高・・・
どんどん疲労してく ひとちが
(へろん へろん
へろん )
)

ようやく小赤石岳の肩を通過、なんとか山頂にたどりついた

同じように山頂でへたばっている登山者たち。
皆さん声を揃えて言った言葉。
まだ 赤石岳ぢゃない・・・
 そう。。。
そう。。。
生半可ぢゃない、このルートを二泊三日で歩くってのは大変なことなのだ
ともかく先を急ごう。
(うりゃ )
)
分岐から またもやザックをデポして正真正銘の赤石岳の山頂に向かう。
案の定、山頂はすっかりガスに覆われ景色もへったくりもなかった

ぶぅぅぅぅぅーーーっ↓
残念。。。
いいんです、一日歩いてるわけだから仕方ないよ
ここまでゴキゲンな山歩きを満喫できたわけだから 赤石の展望は次回に持ち越すことにするっきゃないのだ。
山頂からは聖岳に続く稜線が 赤石避難小屋を越えて繋がっているのが見えた。
ひとちが 満足!
さぁ~てと下りますよぉ~っ
ラクダの背を慎重に下る。
お花畑を通過すると棧道のトラバース、疲れた足がもつれ転びそうになる



足元に気をつけなはれや!
益々ガスは悪化し、富士見平も真っ白け、展望なし ずんずん進む
小屋はまだか・・・
ガスが雨に変わり始めたころようやく赤石小屋に到着。
すでに団体さんで賑わっている小屋に今夜はお世話になることに

ここの小屋番さんは女性です
それも すっごく可愛い若き女性なのだよ。

小屋のいたる所で女性ならではの細かい気配りが感じられ、
山小屋 = むさくるしい
といったイメージは全くなかった。
寝具もよく手入れされ快適、離れたトイレまでの道のりには 電燈が足元に設置されているのでほとんどヘッデンもいらない。
電燈が足元に設置されているのでほとんどヘッデンもいらない。
(素晴らしい )
)

夕食は焼き肉定食、朝食は干物定食と まずまずでしたな。
ゴチ♪


今夜も爆睡!!
翌朝、ご来光を待たずに出発、たくさんの登山者が同時に山を下る混雑を避けたいためであ~る
しばらくすると朝日が昇り始めた。

きっともっさりとした樹林帯と違い小屋の前からの赤石岳・聖岳の景色は最高だろう。

ずんずん下る。
木々の間から朝日が差し込みロマンチック♪

そのうち欲がでてきた ひとしさん。
計画では椹島を10:30に出るバスに乗る予定だった。
ところが・・・
小屋泊の登山者が同時に下山→
同じバスに乗る→コミコミ
→立ち寄り湯もご一緒
な、なんとしても避けたい
じゃどうする?
走りますよ!
 へっ?
へっ?
も、もしかして ト、トレラン?
 またですか・・・
またですか・・・
去年 聖の帰りでトレラン、死にそうになったトラウマの記憶が蘇る。
ちがこさんは 生死に関わる場合とお金が関わらないと走ることは絶対にしないのだよ。
(あはは。)
ちらりと ひとしさんを見る
・・・・
走れってことね↓

それからわぁー、ひたすら 走る
走る  走る
走る  走る
走る  走る・・・
走る・・・
ヌルヌルした木の根っこに けっつまずきながら 足場の悪い石の上、ずっこけそうになりながら ひたすら走る。
足元に気をつけなはれや!

ずるりんこ!
やっぱり! やっちゃいました みごとに ちがこさん転がる
尻餅つかないように手でカバーしたのが悪かった。
両腕を石で擦りむき負傷・・・

(長袖・グローブをしていたので大事には至りませんでした )
)
ようやく登山口の鉄梯子にぃ~っ♪

椹島ロッジにはコースタイム3時間半を大幅にカット、2時間半でゴール
余裕で一番の8:00のバスに乗車することができた。

二泊三日でかいた汗の量はハンパじゃなかった
無敵な臭さ・・・
いいのだ ひとちがだけじゃない、バスの乗客は全員悪臭を放っているのだから
やったね ひとちが!!
またいつの日か この素晴らしいお山を歩きたい
充実した面白いコースだったね ひとしさん♪
 今回同じコースを歩いた謎の若いカップル
今回同じコースを歩いた謎の若いカップル
コンタカさん&クマキミさん

またどこかでお会いしましょう♪
雄大なアルプスを歩き抜け!
荒川三山・赤石岳
(赤石山脈南部エリア)
全山行 250回
 前日の山歩きはこちら
前日の山歩きはこちら
標高 千枚岳 2879.8m 丸山 3032m 東岳 3141m 中岳 3083.2m
前岳 3068m 小赤石岳 3081m 赤石岳 3120.1m
天気
 晴れ・
晴れ・ ガス
ガス山行時間 28日:9時間30分 29日:2時間30分
〈コース〉28日:千枚小屋(5:00)-千枚岳-丸山-東岳-中岳-前岳-荒川小屋-大聖寺平-小赤石岳-赤石岳-富士見平-赤石小屋(2:30)
29日:赤石小屋(5:00)-樺段-椹島ロッジ(7:30-8:00)-バスで移動-畑薙ダム駐車場(9:00)
どこまでも続く美しい稜線・・・
そこわぁー、奥深い雄大な南アルプスを満喫できるパラダイスロード♪
アルプスからの予期せぬプレゼント、それは?
虹♪
真夜中の 小屋のトタン屋根に落ちる賑やかな雨粒の音にもマケズ 今日も元気に目覚めた
ひとちが

(うはは!)
ぶぉぉぉぉーーーーっ!
よく寝たぞぉ~っ!!
早朝4:00に電気がついた

うっすらと窓から花畑が浮かび上がっている。
「もう雨上がったかなぁー?」
ずりぃーっ
窓を開けて手を出す ちがこさん。
「うは!雨降ってないしぃ~、こりゃお天気いいかもよ♪」
昨夜はちょいと心配だったお天気も おかげさまでなんとかなりそうだ。
(うひひひ。。。)
次々と出発を始める登山者たち、ひとちがも5:00スタート

小屋付近の花畑を一気に登る。
建設中の小屋が どんどん小さくなっていく

お世話になりましたぁーっ♪
 森林限界であ~る
森林限界であ~る
去年は暑さのためにカレカレだった ナナカマドの葉っぱも今年は青々、露に濡れて嬉しそう

色づき始めた実が
 紅葉を期待させてくれるねぇー
紅葉を期待させてくれるねぇー

さぁ~てと、
いよいよ稜線に突入だぁーっ!
千枚岳までの岩場の稜線、そこはマツムシソウの花畑

薄紫の大輪が秋を感じさせてくれる

わぁ~ぉ♪
超キレイじゃん!!
ちがこさんは夢中だ

後方にせまってくる登山者など気にすることなく 立ち止まっては花を眺め ちょいと進んではまた止まる

狭い稜線 = 花見物 = 大迷惑
ひとしさんがムッとしている

何故かって?
混雑してるから 後先を歩く登山者が気になって仕方ないのであ~る。
その上、賑やかなおぢさんのスペシャルトーク付ときた

列を成して歩く=間隔が狭い=
いやでも声が聞こえる
 そう・・・
そう・・・誰にも邪魔されず マイペースに静かに歩きたいわけ。
それじゃなくても 横には騒々しく ひとりしゃべりまくる ちがこさんがいるわけだから音はいらない

(うはははは!)
千枚岳に到着。
(よっしゃ
 )
)さえぎるもののない大パノラマにしばし圧倒され言葉も出ない。
あっ! 虹が!
ひとしさんが指さした方向、これから進むべき赤石岳に虹がかかっている

朝日が山にあたり虹は七色に
 輝く
輝く
奥深い南部のこの稜線まで がんばって登ってきた登山者にプレゼントなのか?
ひとちが 大感激♪
納得できる名前の丸山に向かう。
ホントまん丸いハゲ山であ~る

マツムシソウとトリカブト、そしてタカネビランジの花畑をゴキゲンで行進する

すっかり日が昇り、これから向かう悪沢岳は ゴツゴツと奇怪な山頂を覗かせ、遥か彼方 たどりつけるか不安な赤石岳も雲が切れ どでかい山容を見せていた。
悪沢岳
赤石岳
振り返ると富士山♪
いいねぇーっ!!
右を向いても 左を向いても山ばっか

大抵の山は裾に村や建物が見えたりするけど ここは山しかない。
(うん、うん
 )
)まさに 山のオンパレード!
ずんずん登ろう 先は長いのだ

丸山に到着、賑やかなおぢさんを追い抜き間隔を空けたい所

ひとしさんが憧れていた悪沢岳は もう目の前に迫っている。
バランスをとりながら岩をピョンピョン飛び越え山頂に向かおう

荒々しい岩場の山頂、ついに南アルプス南部の最高峰に到着♪
(やったね
 )
)スゴイ! スゴすぎる!!
ひとしさん うるうる・・・

同じ稜線上の山とは思えないような荒々しい景色が広がっていた

のんびりはしていられない、先を急ごう!
ザレた急坂を下り お花畑をちらちら見ながら中岳へ。
てっぺんにあるのは 中岳避難小屋。
小屋には管理人さんが無線中、大きな小屋とは違いボロボロじゃん

(あらら
 )
)中岳を越え、分岐にザックをデポして前岳に向かってみた。
山頂の標識は・・・
あと少しで山から落っこちそうなのだ

何故かって?
山が半分崩れちゃってるからだよ!
中岳の大崩落、覗くだけでも恐ろしい

たぶん・・・
何年か先には この山頂標識はないと思う

ってうか、大きな地震でもあったら明日にでも標識は崩れに飲み込まれてしまうに違いない

荒川小屋に向けて一気に高度を下げる。
山の斜面はガレ場が続き、鹿の食害から花を守るためのネットが張られている。
ネットの前には入口があり、登山道はその中を通過しなければいけない。
ネットの扉の開け閉め→登山道→ネットの扉の開け閉め→登山道
→ネットの扉の開け閉め→登山道→ネットの扉の開け閉め
と繰り返すこと数回、九十九折になっているから仕方ないとはいえ 面倒くさいルートであった

(あはははは、、、)
赤い屋根発見♪
荒川小屋であ~る

快適そうな小屋、振り返れば ここから眺める荒川三山は素晴らしい。
次の機会には是非小屋を利用してみたいものであ~る。
(うん、うん
 )
)小屋からは下った分だけ急な登り。
小屋が小さくなっていく

さすがに疲労し始めた足にはキツイ登りだよね ひとしさん

チングルマの綿毛が風に揺れていた

花も綺麗だけど ちがこさんは綿毛のチングルマの方が好きかな。
あっ♪
綺麗なちょうちょ!!
 キタベリタテハが花畑を舞っていた。
キタベリタテハが花畑を舞っていた。何故だか ひとしさんが好きらしくズボンから離れようとしない蝶。
恋する相手が違いませんか?
(うはは。。。)
振り返ると荒川三山岳が笑っていたよ

再び
 森林限界を抜け大聖寺平のトラバース道に突入
森林限界を抜け大聖寺平のトラバース道に突入
きゃぁーっ♪
超キレイ!!
ここわぁー、最高です♪
まるで童話のハイジの世界

ペーターっ!!
思わず大声でヤギを追うペーターを探してしまう ちがこさん

振り返ると自分たちの歩いてきた道が一望。
うぉぉぉぉぉーーーーっ!
目の前に でっかい山が立ちふさがっている

赤石岳ぢゃない、そう、まだ手前に でっかい山があった

小赤石岳であ~る

これ登るんかいな・・・
思わず見上げて溜息をつく ひとちが

天気もガスが出始めたこの時間帯、急がねば赤石岳はガスガスになりそうな予感

トウヤクリンドウの花畑が広がる

いっそげぇーっ!!
 うが
うが  うが
うが  うが
うが  うが
うが
はぁ、はぁ はぁ、はぁ・・・
 うが
うが  うが
うが  うが
うが  うが
うがはぁ、はぁ はぁ、はぁ・・・
苦しくともジグザグの坂道を必死で登るっきゃない

どんどん上がる標高・・・
どんどん疲労してく ひとちが

(へろん
 へろん
へろん )
)ようやく小赤石岳の肩を通過、なんとか山頂にたどりついた

同じように山頂でへたばっている登山者たち。
皆さん声を揃えて言った言葉。
まだ 赤石岳ぢゃない・・・
 そう。。。
そう。。。生半可ぢゃない、このルートを二泊三日で歩くってのは大変なことなのだ

ともかく先を急ごう。
(うりゃ
 )
)分岐から またもやザックをデポして正真正銘の赤石岳の山頂に向かう。
案の定、山頂はすっかりガスに覆われ景色もへったくりもなかった

ぶぅぅぅぅぅーーーっ↓
残念。。。
いいんです、一日歩いてるわけだから仕方ないよ

ここまでゴキゲンな山歩きを満喫できたわけだから 赤石の展望は次回に持ち越すことにするっきゃないのだ。
山頂からは聖岳に続く稜線が 赤石避難小屋を越えて繋がっているのが見えた。
ひとちが 満足!
さぁ~てと下りますよぉ~っ

ラクダの背を慎重に下る。
お花畑を通過すると棧道のトラバース、疲れた足がもつれ転びそうになる

足元に気をつけなはれや!
益々ガスは悪化し、富士見平も真っ白け、展望なし ずんずん進む

小屋はまだか・・・
ガスが雨に変わり始めたころようやく赤石小屋に到着。
すでに団体さんで賑わっている小屋に今夜はお世話になることに

ここの小屋番さんは女性です

それも すっごく可愛い若き女性なのだよ。
小屋のいたる所で女性ならではの細かい気配りが感じられ、
山小屋 = むさくるしい
といったイメージは全くなかった。
寝具もよく手入れされ快適、離れたトイレまでの道のりには
 電燈が足元に設置されているのでほとんどヘッデンもいらない。
電燈が足元に設置されているのでほとんどヘッデンもいらない。(素晴らしい
 )
)夕食は焼き肉定食、朝食は干物定食と まずまずでしたな。
ゴチ♪
今夜も爆睡!!
翌朝、ご来光を待たずに出発、たくさんの登山者が同時に山を下る混雑を避けたいためであ~る

しばらくすると朝日が昇り始めた。
きっともっさりとした樹林帯と違い小屋の前からの赤石岳・聖岳の景色は最高だろう。
ずんずん下る。
木々の間から朝日が差し込みロマンチック♪
そのうち欲がでてきた ひとしさん。
計画では椹島を10:30に出るバスに乗る予定だった。
ところが・・・
小屋泊の登山者が同時に下山→
同じバスに乗る→コミコミ
→立ち寄り湯もご一緒
な、なんとしても避けたい

じゃどうする?
走りますよ!

 へっ?
へっ?も、もしかして ト、トレラン?
 またですか・・・
またですか・・・去年 聖の帰りでトレラン、死にそうになったトラウマの記憶が蘇る。
ちがこさんは 生死に関わる場合とお金が関わらないと走ることは絶対にしないのだよ。
(あはは。)
ちらりと ひとしさんを見る

・・・・
走れってことね↓
それからわぁー、ひたすら
 走る
走る  走る
走る  走る
走る  走る・・・
走る・・・ヌルヌルした木の根っこに けっつまずきながら 足場の悪い石の上、ずっこけそうになりながら ひたすら走る。
足元に気をつけなはれや!
ずるりんこ!
やっぱり! やっちゃいました みごとに ちがこさん転がる

尻餅つかないように手でカバーしたのが悪かった。
両腕を石で擦りむき負傷・・・
(長袖・グローブをしていたので大事には至りませんでした
 )
)ようやく登山口の鉄梯子にぃ~っ♪
椹島ロッジにはコースタイム3時間半を大幅にカット、2時間半でゴール

余裕で一番の8:00のバスに乗車することができた。
二泊三日でかいた汗の量はハンパじゃなかった

無敵な臭さ・・・
いいのだ ひとちがだけじゃない、バスの乗客は全員悪臭を放っているのだから

やったね ひとちが!!
またいつの日か この素晴らしいお山を歩きたい

充実した面白いコースだったね ひとしさん♪
 今回同じコースを歩いた謎の若いカップル
今回同じコースを歩いた謎の若いカップル
コンタカさん&クマキミさん
またどこかでお会いしましょう♪
2011年08月30日
アルプスの虹♪ 1
2011/8/27
忍耐登り!
荒川三山・赤石岳
(南アルプス南部エリア)
全山行 250回

標高 千枚小屋 2500m
天気 晴れ・
晴れ・ ガス・
ガス・ 雨
雨
山行時間 6時間
〈コース〉自宅(3:15)-畑薙ダム駐車場(7:30-8:00)-東海フォレストバスで移動-椹島ロッジ(9:00-9:20)-滝見橋-小石下-清水平-千枚小屋(3:20)
一昨年わぁー、茶臼・光岳。
去年わぁー、聖岳。
ふんじゃぁ 今年わぁー、 もちろん荒川三山&赤石岳っきゃない!
うはははは!
お贅沢な小屋泊で
南部のお山を縦走しよう♪
 何故だか南部のお山の山歩きはキビシー上に 毎年天候不順に悩まされ 一筋縄ではいかなかった現実
何故だか南部のお山の山歩きはキビシー上に 毎年天候不順に悩まされ 一筋縄ではいかなかった現実
込み合うお盆は避けたものの、近づいている台風と競争しあいながら 今年もまたチャレンジすることにした。
それにしても畑薙ダムの駐車場までの道のりは長い
ウネウネと曲がりくねった道のりを走ること3時間、あと一息という所でハプニングはやってきた。
何かって?
ナビに表示された ×マーク?
「げっ これって通行止めだよね
これって通行止めだよね 」
」
いきなり通せんぼですか・・・
ムカつく ひとしさん
「どうします? もうここまできたら今更引き返すなんてできませんよ、通行止めだったら諦めるしかありませんね・・・」
 へっ?
へっ?
諦める?
冗談ぢゃない!
 まぁ、まぁ 落ち着いて 落ち着いて!
まぁ、まぁ 落ち着いて 落ち着いて!
現場まで行ってみなきゃわかんないじゃん
(そう そう )
)
不安になりながらも車を走らせる。
×マークの地点であ~る。
?
何もない、フツーに通れた
よかったぁー・・・
と またもやナビ上に×マーク
げっ↓
「今度もきっと何にもないから先行って 」
」
案の定、×マーク地点は何もない。
(よかった よかった )
)
ラッキー♪
*後の情報で 金曜日の午後遅くまで道は通れなかった模様、ひとちがは土曜の早朝でしたので問題なかったわけです。
駐車場に到着、車も少なくお盆に比べて人影もまばらなのが現実


うへへへへ!
これゃ 静かな山歩きが楽しめそうな予感♪
(わく わく )
)
さっそく朝一番の8:00発のバスに乗り込むことに
乗車の際、運転手のおじさんが 予定を確認。
「どこまで行かれますか?」
嬉しそうに答える ひとしさん。
二枚小屋!
「に、二枚小屋?」
そんなのあったっけ?
おじさん びっくり
ひとしさんの中では 二軒小屋と千枚小屋が一緒になってしまった模様
あはははは!
それにしても二枚小屋とは
慌てて 千枚小屋です と訂正
 バスに乗車、登山基地 椹島へ向かう。
バスに乗車、登山基地 椹島へ向かう。
凸凹した道のりをバスに揺られて1時間、空は青く秋に近づいているのがよくわかる。

ダム湖に溜まった水は モスグリーン♪
秋の紅葉はさぞかし綺麗なんだろうな
椹島ロッジに到着、トイレでもたもたしている ちがこさんのおかげで またもやどん尻の出発であ~る
(いつものことですが・・・)

神社で今回の山歩きの無事を祈る。
お盆に同じコースを歩いている こむちゃんが怪我をしたらしい写真を見ていた ちがこさんとしては ちょいと恐怖だったのだ
そ、そんなに危険な山なわけ?
怪我は絶対しないで 無事下山する!
心に誓い神頼み
(結果的に怪我しましたが・・・)

よっしゃぁーっ!
気合入れは十分!!
お参りをしている間に若いカップルが勢いよく登山道を登っていくのが見えた。
南部のお山は年齢層が高く 山ボーイ&山ガールはあんまり見かけないもんねぇー
さぁ~てと ひとちがも がんばりますかぁー!
(うりゃ )
)

舗装路から千枚小屋へのルートに突入、橋の上からは大井川の源流が涼しげに流れている。


滝見橋を渡る。
ひとちが二人が乗っかっても 150キロの制限重量の橋は びくともしない。


大好きな吊り橋を渡ろう♪

急な登りではないものの、出発時間が遅いので気温も上昇 尋常でない汗が出始めた
あぢぃーーーーーっ↓

いつもなら 後方の ひとしさんが びとんびとんになっているわけだが 今回は違った。
先頭を行く ちがこさんが振り返る。
「な、なんですか その汗わ 」
」
ひとしさん びっくり仰天、水玉模様の顔の ちがこさんが笑っている

ねっ!
スゴイ汗でしょ!
*この汗が乾くと更に恐ろしいことになりマス。最悪ですな・・・
水玉模様→塩大福
「大丈夫ですか? 具合悪いわけじゃありませんよね?」
 へっ?
へっ?
どっこも悪くないってば
暑いだけだしぃー
そういう ひとしさんだって負けちゃいない
(うはははは!)

ようやく鉄塔に出た
忍耐の登りであ~る

林道と交差するポイントには アサギマダラが飛び交っていた。
鉄梯子に恋したのか 花には目もくれず 蝶は手すりにキスしている

あはは!
相手が違うんぢゃない?

鉄梯子を登り まだ若い美しい 樹林帯を登っていく。
樹林帯を登っていく。

 うが
うが  うが
うが  うが
うが  うが
うが
横目でちらちら登山道と沿っている林道を恨めしそうに眺める
 うが
うが  うが
うが  うが
うが  うが
うが
まだ先は長い
今日は展望のない樹林歩きと覚悟は決めてきたものの 怪しくなり始めた天気、いつものごとくのカッパ隊となると やっぱりテンションは下がってくるもんであ~る
うほ♪
キノコ発見!!


 秋が近づいている証拠?
秋が近づいている証拠?
食べられるのか 食べられないのか よくわかんないけど芸術的な キノコが
キノコが  ニョキ
ニョキ ニョキと顔を出している。
ニョキと顔を出している。
交差している林道沿いの展望地に到着。
もちろぉ~んガスガスですからね 展望なしです
ここで ちがこさん不思議なもの発見
林道脇に小さな小屋?
 そうさねぇー、畳 2畳っていったところ。
そうさねぇー、畳 2畳っていったところ。
簡易トイレかな?

鍵がかかっている様子もない
人間、こーいうのを見ると開けてみたくなるもんです。
(ちがこさんだけだって?)
さっそく覗いてみましょう!
オ~プン!!
?
???
何もない・・・

床です、でも中身はありません。
これって避難小屋なんでしょうか?
結局、よくわかんないまんま その場を去ることにぃー
(どなたか これが何であるのか わかる方がいたら教えて下さい。)
小石下を登り、清水平(水場)を通過、ズンズン先を急ぐ
どんどん悪化していく天候

あまりの暑さゆえ、カッパのフードをかぶることもできず そんでもひたすら前に進むっきゃない
がんばれぇーっ!!
随分たくさんの登山者を追い抜いた

駒鳥池に到着。
倒木が静かに浮かぶ 青々した藻がなんとも幻想的♪
きゃぁ~っ!!
す・て・きぃ~っ♪

今まで見た池の中でも5本の指に入る池
きっと霧がかかっていたのも ステキに見えた理由のひとつかも!
こ~いうの見ると 雨やガスの山歩きも悪くないなって思っちゃう ちがこさんでありマス
(うひ♪)
小屋まであと15分
看板を見ながら 嬉しそうに ひとしさんが苦笑い。
ホントに15分で到着できるのかな?

トリカブトが歓迎してくれている。
お盆あたりには最盛期であった彼らも 色があせはじめ、最後の力を振り絞って登山者を喜ばせようと咲き誇っているのだろうか。

濡れネズミもようやく終了、現在新しい小屋を建設中の千枚小屋に到着♪


仮設のプレハブ小屋で受け付けを済ませる。

メインである月光荘、百枚小屋、十枚荘と宿泊できる施設は3棟だ。



月光荘 百枚小屋 十枚荘
すでに月光荘はコミコミ 満員御礼、宿泊者の熱気で小屋の中は モンモンしている
十枚荘は建物もプレハブ、年配の登山者で足の踏み場もない
ひとちがは百枚小屋にお世話になることとなった。
ラッキーなことに 百枚小屋は指定場所もなく 好きな場所を選ぶことができた。
スペースにもゆとりがあり他の小屋に比べると寒いくらいなのだ。
さぁ~てと、どこにしますかねぇー・・・
そ・し・て!
ひとちがが選んだのは・・・
悪沢と名のつく 2階のロフト部分の角っちょ、小さな窓からは花畑を楽しむことができるゴキゲンなスペースであ~る



さっそく濡れた衣類を乾かすために そこらじゅうにぶら下げる。
ありがたいことにハンガーも使いたい放題、おまけにザック置き場も別にあるので嬉しい
広々と小屋を満喫して使えるわけ!
ぶら下げた衣類は まるで個室のようにもなって なんとも かんともお贅沢♪

寝具は やや湿っていまして 快適とは言い難く
でもね、新しい小屋を建設中ってこともあって なかなか寝具を干すスペースもないんじゃないかと・・・
きっと新しい小屋が完成すれば 改善されるよね。
トイレは小屋から やや離れた場所にあるので臭いも気になりません。
水洗、トイレットペーパーもあり なかなか快適です。
水場も前にあるので問題なし、手洗い用のシャボネットもあって 汚れた手を綺麗にできます
夕食は、受付横の食堂で15名程 順番こ
千枚小屋では 大きなメイン料理ではなく、お皿にたくさんの種類の料理が盛られて出てきた。
ボリュームもあり、ご飯とみそ汁はお代わりし放題


う~ん、大満足♪


今日は忍耐登りだったけど 快適な小屋にお世話になることができてよかったね ひとちが。
 誰もイビキをかく人もいない静かな小屋・・・
誰もイビキをかく人もいない静かな小屋・・・
ぢゃなかった
素晴らしいスペースにも穴があった。
雨は降っていたわけじゃない、木からしたたる雨粒がハンパじゃないのだ
トタン屋根に叩きつける雨粒の音、それも ひとちがの頭の真上
タカタン タカタン
タカタカ タカタカ
タ タタ タ タタ
ダダダダ ダダ
それも夜中 ず~~~~~~~っと
に、賑やかすぎませんかねぇー
これ! がまんしなさい
はい、はい そうですな。
爆睡!
真夜中、うなされたのか おぢさんの悲鳴が聞こえた
うおぉぉぉぉーーーっ!!
いつの間にか空には星が 輝いている
輝いている
早朝4:30、小屋に灯りが灯る。
本日は10時間の長丁場、早々に出発しなければいけない
朝食メニューもね、これまたボリュームのある美味しい料理
うんま♪


お世話になった千枚小屋を後に いよいよ稜線に向けて出発
新しい小屋の完成が楽しみだね。
また同じコースを歩く日には 必ずお世話になりたい小屋のひとつとなった
ほら!
富士山も今日は ゴキゲンに顔を出している

よっしゃ!
いっくよぉーっ!!
 翌日の山歩きはこちら
翌日の山歩きはこちら
忍耐登り!
荒川三山・赤石岳
(南アルプス南部エリア)
全山行 250回
標高 千枚小屋 2500m
天気
 晴れ・
晴れ・ ガス・
ガス・ 雨
雨山行時間 6時間
〈コース〉自宅(3:15)-畑薙ダム駐車場(7:30-8:00)-東海フォレストバスで移動-椹島ロッジ(9:00-9:20)-滝見橋-小石下-清水平-千枚小屋(3:20)
一昨年わぁー、茶臼・光岳。
去年わぁー、聖岳。
ふんじゃぁ 今年わぁー、 もちろん荒川三山&赤石岳っきゃない!
うはははは!
お贅沢な小屋泊で
南部のお山を縦走しよう♪
 何故だか南部のお山の山歩きはキビシー上に 毎年天候不順に悩まされ 一筋縄ではいかなかった現実
何故だか南部のお山の山歩きはキビシー上に 毎年天候不順に悩まされ 一筋縄ではいかなかった現実
込み合うお盆は避けたものの、近づいている台風と競争しあいながら 今年もまたチャレンジすることにした。
それにしても畑薙ダムの駐車場までの道のりは長い

ウネウネと曲がりくねった道のりを走ること3時間、あと一息という所でハプニングはやってきた。
何かって?
ナビに表示された ×マーク?
「げっ
 これって通行止めだよね
これって通行止めだよね 」
」いきなり通せんぼですか・・・
ムカつく ひとしさん

「どうします? もうここまできたら今更引き返すなんてできませんよ、通行止めだったら諦めるしかありませんね・・・」
 へっ?
へっ?諦める?
冗談ぢゃない!
 まぁ、まぁ 落ち着いて 落ち着いて!
まぁ、まぁ 落ち着いて 落ち着いて!現場まで行ってみなきゃわかんないじゃん

(そう そう
 )
)不安になりながらも車を走らせる。
×マークの地点であ~る。
?
何もない、フツーに通れた

よかったぁー・・・
と またもやナビ上に×マーク

げっ↓
「今度もきっと何にもないから先行って
 」
」案の定、×マーク地点は何もない。
(よかった よかった
 )
)ラッキー♪
*後の情報で 金曜日の午後遅くまで道は通れなかった模様、ひとちがは土曜の早朝でしたので問題なかったわけです。
駐車場に到着、車も少なくお盆に比べて人影もまばらなのが現実

うへへへへ!
これゃ 静かな山歩きが楽しめそうな予感♪
(わく わく
 )
)さっそく朝一番の8:00発のバスに乗り込むことに

乗車の際、運転手のおじさんが 予定を確認。
「どこまで行かれますか?」
嬉しそうに答える ひとしさん。
二枚小屋!
「に、二枚小屋?」
そんなのあったっけ?
おじさん びっくり

ひとしさんの中では 二軒小屋と千枚小屋が一緒になってしまった模様

あはははは!
それにしても二枚小屋とは

慌てて 千枚小屋です と訂正

 バスに乗車、登山基地 椹島へ向かう。
バスに乗車、登山基地 椹島へ向かう。凸凹した道のりをバスに揺られて1時間、空は青く秋に近づいているのがよくわかる。
ダム湖に溜まった水は モスグリーン♪
秋の紅葉はさぞかし綺麗なんだろうな

椹島ロッジに到着、トイレでもたもたしている ちがこさんのおかげで またもやどん尻の出発であ~る

(いつものことですが・・・)
神社で今回の山歩きの無事を祈る。
お盆に同じコースを歩いている こむちゃんが怪我をしたらしい写真を見ていた ちがこさんとしては ちょいと恐怖だったのだ

そ、そんなに危険な山なわけ?
怪我は絶対しないで 無事下山する!
心に誓い神頼み

(結果的に怪我しましたが・・・)
よっしゃぁーっ!
気合入れは十分!!
お参りをしている間に若いカップルが勢いよく登山道を登っていくのが見えた。
南部のお山は年齢層が高く 山ボーイ&山ガールはあんまり見かけないもんねぇー

さぁ~てと ひとちがも がんばりますかぁー!
(うりゃ
 )
)舗装路から千枚小屋へのルートに突入、橋の上からは大井川の源流が涼しげに流れている。
滝見橋を渡る。
ひとちが二人が乗っかっても 150キロの制限重量の橋は びくともしない。
大好きな吊り橋を渡ろう♪
急な登りではないものの、出発時間が遅いので気温も上昇 尋常でない汗が出始めた

あぢぃーーーーーっ↓
いつもなら 後方の ひとしさんが びとんびとんになっているわけだが 今回は違った。
先頭を行く ちがこさんが振り返る。
「な、なんですか その汗わ
 」
」ひとしさん びっくり仰天、水玉模様の顔の ちがこさんが笑っている


ねっ!
スゴイ汗でしょ!
*この汗が乾くと更に恐ろしいことになりマス。最悪ですな・・・
水玉模様→塩大福
「大丈夫ですか? 具合悪いわけじゃありませんよね?」
 へっ?
へっ?どっこも悪くないってば

暑いだけだしぃー

そういう ひとしさんだって負けちゃいない

(うはははは!)

ようやく鉄塔に出た

忍耐の登りであ~る

林道と交差するポイントには アサギマダラが飛び交っていた。
鉄梯子に恋したのか 花には目もくれず 蝶は手すりにキスしている

あはは!
相手が違うんぢゃない?
鉄梯子を登り まだ若い美しい
 樹林帯を登っていく。
樹林帯を登っていく。 うが
うが  うが
うが  うが
うが  うが
うが
横目でちらちら登山道と沿っている林道を恨めしそうに眺める

 うが
うが  うが
うが  うが
うが  うが
うが
まだ先は長い

今日は展望のない樹林歩きと覚悟は決めてきたものの 怪しくなり始めた天気、いつものごとくのカッパ隊となると やっぱりテンションは下がってくるもんであ~る

うほ♪
キノコ発見!!
 秋が近づいている証拠?
秋が近づいている証拠?食べられるのか 食べられないのか よくわかんないけど芸術的な
 キノコが
キノコが  ニョキ
ニョキ ニョキと顔を出している。
ニョキと顔を出している。交差している林道沿いの展望地に到着。
もちろぉ~んガスガスですからね 展望なしです

ここで ちがこさん不思議なもの発見

林道脇に小さな小屋?
 そうさねぇー、畳 2畳っていったところ。
そうさねぇー、畳 2畳っていったところ。簡易トイレかな?

鍵がかかっている様子もない

人間、こーいうのを見ると開けてみたくなるもんです。
(ちがこさんだけだって?)
さっそく覗いてみましょう!
オ~プン!!
?
???
何もない・・・


床です、でも中身はありません。
これって避難小屋なんでしょうか?
結局、よくわかんないまんま その場を去ることにぃー

(どなたか これが何であるのか わかる方がいたら教えて下さい。)
小石下を登り、清水平(水場)を通過、ズンズン先を急ぐ

どんどん悪化していく天候

あまりの暑さゆえ、カッパのフードをかぶることもできず そんでもひたすら前に進むっきゃない

がんばれぇーっ!!
随分たくさんの登山者を追い抜いた

駒鳥池に到着。
倒木が静かに浮かぶ 青々した藻がなんとも幻想的♪
きゃぁ~っ!!
す・て・きぃ~っ♪
今まで見た池の中でも5本の指に入る池

きっと霧がかかっていたのも ステキに見えた理由のひとつかも!
こ~いうの見ると 雨やガスの山歩きも悪くないなって思っちゃう ちがこさんでありマス

(うひ♪)
小屋まであと15分
看板を見ながら 嬉しそうに ひとしさんが苦笑い。
ホントに15分で到着できるのかな?
トリカブトが歓迎してくれている。
お盆あたりには最盛期であった彼らも 色があせはじめ、最後の力を振り絞って登山者を喜ばせようと咲き誇っているのだろうか。
濡れネズミもようやく終了、現在新しい小屋を建設中の千枚小屋に到着♪
仮設のプレハブ小屋で受け付けを済ませる。
メインである月光荘、百枚小屋、十枚荘と宿泊できる施設は3棟だ。
月光荘 百枚小屋 十枚荘
すでに月光荘はコミコミ 満員御礼、宿泊者の熱気で小屋の中は モンモンしている

十枚荘は建物もプレハブ、年配の登山者で足の踏み場もない

ひとちがは百枚小屋にお世話になることとなった。
ラッキーなことに 百枚小屋は指定場所もなく 好きな場所を選ぶことができた。
スペースにもゆとりがあり他の小屋に比べると寒いくらいなのだ。
さぁ~てと、どこにしますかねぇー・・・
そ・し・て!
ひとちがが選んだのは・・・
悪沢と名のつく 2階のロフト部分の角っちょ、小さな窓からは花畑を楽しむことができるゴキゲンなスペースであ~る

さっそく濡れた衣類を乾かすために そこらじゅうにぶら下げる。
ありがたいことにハンガーも使いたい放題、おまけにザック置き場も別にあるので嬉しい

広々と小屋を満喫して使えるわけ!
ぶら下げた衣類は まるで個室のようにもなって なんとも かんともお贅沢♪
寝具は やや湿っていまして 快適とは言い難く

でもね、新しい小屋を建設中ってこともあって なかなか寝具を干すスペースもないんじゃないかと・・・
きっと新しい小屋が完成すれば 改善されるよね。
トイレは小屋から やや離れた場所にあるので臭いも気になりません。
水洗、トイレットペーパーもあり なかなか快適です。
水場も前にあるので問題なし、手洗い用のシャボネットもあって 汚れた手を綺麗にできます

夕食は、受付横の食堂で15名程 順番こ

千枚小屋では 大きなメイン料理ではなく、お皿にたくさんの種類の料理が盛られて出てきた。
ボリュームもあり、ご飯とみそ汁はお代わりし放題

う~ん、大満足♪
今日は忍耐登りだったけど 快適な小屋にお世話になることができてよかったね ひとちが。
 誰もイビキをかく人もいない静かな小屋・・・
誰もイビキをかく人もいない静かな小屋・・・ぢゃなかった

素晴らしいスペースにも穴があった。
雨は降っていたわけじゃない、木からしたたる雨粒がハンパじゃないのだ

トタン屋根に叩きつける雨粒の音、それも ひとちがの頭の真上

タカタン タカタン
タカタカ タカタカ
タ タタ タ タタ
ダダダダ ダダ
それも夜中 ず~~~~~~~っと

に、賑やかすぎませんかねぇー

これ! がまんしなさい

はい、はい そうですな。
爆睡!
真夜中、うなされたのか おぢさんの悲鳴が聞こえた

うおぉぉぉぉーーーっ!!
いつの間にか空には星が
 輝いている
輝いている
早朝4:30、小屋に灯りが灯る。
本日は10時間の長丁場、早々に出発しなければいけない

朝食メニューもね、これまたボリュームのある美味しい料理

うんま♪
お世話になった千枚小屋を後に いよいよ稜線に向けて出発

新しい小屋の完成が楽しみだね。
また同じコースを歩く日には 必ずお世話になりたい小屋のひとつとなった

ほら!
富士山も今日は ゴキゲンに顔を出している

よっしゃ!
いっくよぉーっ!!
 翌日の山歩きはこちら
翌日の山歩きはこちら
2011年08月18日
青春の1ページ♪ 後編・・・
2011/8/13・14
山頂アタック!
北 岳
(赤石山脈北部エリア)
全山行 248回
百名山 40座

 前編はこちら
前編はこちら
標高 北岳 3192.4m
天気 晴れ
晴れ
山行時間 7時間40分
〈コース〉14日:北岳山荘(7:00)-山頂(8:20-9:00)-北岳肩ノ小屋(9:40-10:00)-草スベリ-白根御池小屋(12:00-12:50)-広河原(2:40)
空は青かった・・・
山頂からの景色は 日常生活とは違う別世界!
少年たちはいったい何を感じたのだろう?
2011年夏、14歳の少年達はこの頂に立ち大きく成長したはずだ!
 午前4:00、にわかに外が騒がしい
午前4:00、にわかに外が騒がしい
山小屋から、登山者たちが次々と自分たちの目的地に向かって出発していく
テント場も同様、朝日が昇るころには大半のテントがたたまれていた。
( はや!)
はや!)

ひとちが一行、本日は北岳のピークアタック、広河原に戻る計画のため余裕での出発準備であ~る
(よっしゃ )
)
一夜明けた じゃりんこ隊のふたり、地味ぃ~に斜めっちょのテントでやや苦戦したものの、よ~く眠れたみたいだね


今日も元気バリバリ、テントの片づけもなかなか手際がよろしい
(うん、うん♪)

朝食を済ませ稜線より いざ出発♪

すっきりと顔を出している北岳山頂までの道のりをブンブン飛ばす


きっもちいい♪
最高!!

昨日は午後からお天気が不安定だったため景色もあまりよろしくなかったが 本日はちがぁ~う
ゴキゲンな稜線は 富士山を始め、遠くの山々たちが美し く輝いている
く輝いている

スゴイ景色だねぇー・・・

ふたりとも早朝の山に魅了されていた
重たいザックも背負っていることさえ忘れてしまいそうなくらい
高度を上げる。



小屋とテン場が小さくなっていく。
間ノ岳が朝日に輝いて大きな山容を誇らしげに見せている。

岩場に咲く花々も朝露に濡れ ピカピカ
ピカピカ
夏山から秋に変化する短い時間を懸命に生きているのだ。


巨大ザックを背負った ひとしさんは今日も言葉少なげなのが残念

鎖場に突入、稜線とはいえ油断はできない
「しっかり鎖を持って 山側に身体を寄せて 」
」
ちがこさんが叫んだ。
しょうたろう選手はともかく、ひらぴーは登山初体験。
怪我をさせるわけにはいかない
(そう、そう!)

山頂に到着
たくさんの登山者たちが南アルプス最高峰に酔いしれていた。

イエーっ!!

空は青かった・・・
山頂からの景色は 日常生活とは違う別世界!
少年たちはいったい何を感じたのだろう?



昨日からの激しい山登り。
重たいザックを背負い 自分自身と戦い続けた。
そして今、山頂を踏む
2011年夏、14歳の少年達はこの頂に立ち大きく成長したはずだ!
やったね じゃりんこ隊!!
しばし山頂を楽しむ
短い時間、名残惜しいが 肩ノ小屋に向けて下山開始であ~る。

ここからは激しい下りの連続、ガレ場歩きなどしたことのない じゃりんこ隊たちにとって長い忍耐の下山でもある

肩ノ小屋に到着。
小屋の屋根にはカラフルに寝具が干され 小屋の前には 北肩バットレスなる岩登りのアトラクションも設置されていた。
わぁ~~~~い♪
こりゃ登るっきやない!
さっそく登ってみた




本物の北岳バットレスにいつの日にか登ることができるだろうか?
(無理! 無理!)
雄大に続く広い尾根を歩く。
この瞬間がアルプスを感じることのできる優越感なのかも♪
(うひ。)

分岐から草スベリを下る。
急な上 足場がよくない
白根御池を下に見ながら 花畑の中をジグザグに延々と下っていく・・・




あっ!
ズル・・・
ひらぴーが足を滑らせた。
一歩間違えば草の中の急斜面を転落しかねなかった。
昨日からの山行で かなり足が疲労していることは間違いない。
気が抜けない

白根御池小屋に到着
大きくて綺麗な小屋であ~る。
水も豊富で無料で水場を使わせてもらえるのが嬉しい。

その上、小屋の入口には ソフトクリーム♪
うへへへへ!
ご飯の後に食べよう♪
じゃりんこ隊のふたり、足の裏が痛くて山靴を脱ぎ捨てた。
できることなら もう一歩も歩きたくないのだろう。
小屋の前で休憩している登山者たちも 疲れ果てた様子、皆さん抜け殻のようになっている
元気なのは ひとちが。
特に ちがこさん
「ねぇ ねぇ 桃のソフトクリームにするぅ?」
嬉しそうに小屋前をウロウロ。
ランチのカップラーメンもグッドでしたな。
こらしょと持ってきた食材も ほぼ食べつくした
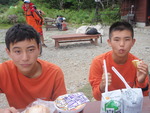


桃ソフト うまうまです♪
さぁ~てと出発だ。
樹林帯の急坂を下る。
ここではかなり怪我人が勃発しているらしいから注意が必要。
(うん、うん )
)
足の裏が痛いふたりは無言で下る。

まだかなぁー・・・
ぶつ ぶつ ぶつ・・・

ようやく樹林帯を抜けた。
安心したのか 早く靴を脱ぎたいのか とたんに じゃりんこ隊の歩くスピードが上がる
(あは。。。)
橋を越え広河原に到着、タイミングよく乗ることのできたジャンタクに感謝、芦安の駐車場に無事到着することができた。

お疲れぇーっ!!

がんばった夏の思い出、君たちの青春の1ページとして いつまでも忘れないで欲しい
山の美しさと楽しさを満喫できた北岳山行でした
山頂アタック!
北 岳
(赤石山脈北部エリア)
全山行 248回
百名山 40座
 前編はこちら
前編はこちら
標高 北岳 3192.4m
天気
 晴れ
晴れ山行時間 7時間40分
〈コース〉14日:北岳山荘(7:00)-山頂(8:20-9:00)-北岳肩ノ小屋(9:40-10:00)-草スベリ-白根御池小屋(12:00-12:50)-広河原(2:40)
空は青かった・・・
山頂からの景色は 日常生活とは違う別世界!
少年たちはいったい何を感じたのだろう?
2011年夏、14歳の少年達はこの頂に立ち大きく成長したはずだ!
 午前4:00、にわかに外が騒がしい
午前4:00、にわかに外が騒がしい
山小屋から、登山者たちが次々と自分たちの目的地に向かって出発していく

テント場も同様、朝日が昇るころには大半のテントがたたまれていた。
(
 はや!)
はや!)ひとちが一行、本日は北岳のピークアタック、広河原に戻る計画のため余裕での出発準備であ~る

(よっしゃ
 )
)一夜明けた じゃりんこ隊のふたり、地味ぃ~に斜めっちょのテントでやや苦戦したものの、よ~く眠れたみたいだね

今日も元気バリバリ、テントの片づけもなかなか手際がよろしい

(うん、うん♪)
朝食を済ませ稜線より いざ出発♪
すっきりと顔を出している北岳山頂までの道のりをブンブン飛ばす

きっもちいい♪
最高!!
昨日は午後からお天気が不安定だったため景色もあまりよろしくなかったが 本日はちがぁ~う

ゴキゲンな稜線は 富士山を始め、遠くの山々たちが美し
 く輝いている
く輝いている
スゴイ景色だねぇー・・・
ふたりとも早朝の山に魅了されていた

重たいザックも背負っていることさえ忘れてしまいそうなくらい

高度を上げる。
小屋とテン場が小さくなっていく。
間ノ岳が朝日に輝いて大きな山容を誇らしげに見せている。
岩場に咲く花々も朝露に濡れ
 ピカピカ
ピカピカ
夏山から秋に変化する短い時間を懸命に生きているのだ。
巨大ザックを背負った ひとしさんは今日も言葉少なげなのが残念

鎖場に突入、稜線とはいえ油断はできない

「しっかり鎖を持って 山側に身体を寄せて
 」
」ちがこさんが叫んだ。
しょうたろう選手はともかく、ひらぴーは登山初体験。
怪我をさせるわけにはいかない

(そう、そう!)
山頂に到着

たくさんの登山者たちが南アルプス最高峰に酔いしれていた。
イエーっ!!
空は青かった・・・
山頂からの景色は 日常生活とは違う別世界!
少年たちはいったい何を感じたのだろう?
昨日からの激しい山登り。
重たいザックを背負い 自分自身と戦い続けた。
そして今、山頂を踏む

2011年夏、14歳の少年達はこの頂に立ち大きく成長したはずだ!
やったね じゃりんこ隊!!
しばし山頂を楽しむ

短い時間、名残惜しいが 肩ノ小屋に向けて下山開始であ~る。
ここからは激しい下りの連続、ガレ場歩きなどしたことのない じゃりんこ隊たちにとって長い忍耐の下山でもある

肩ノ小屋に到着。
小屋の屋根にはカラフルに寝具が干され 小屋の前には 北肩バットレスなる岩登りのアトラクションも設置されていた。
わぁ~~~~い♪
こりゃ登るっきやない!
さっそく登ってみた

本物の北岳バットレスにいつの日にか登ることができるだろうか?
(無理! 無理!)
雄大に続く広い尾根を歩く。
この瞬間がアルプスを感じることのできる優越感なのかも♪
(うひ。)
分岐から草スベリを下る。
急な上 足場がよくない

白根御池を下に見ながら 花畑の中をジグザグに延々と下っていく・・・
あっ!
ズル・・・
ひらぴーが足を滑らせた。
一歩間違えば草の中の急斜面を転落しかねなかった。
昨日からの山行で かなり足が疲労していることは間違いない。
気が抜けない

白根御池小屋に到着

大きくて綺麗な小屋であ~る。
水も豊富で無料で水場を使わせてもらえるのが嬉しい。
その上、小屋の入口には ソフトクリーム♪
うへへへへ!
ご飯の後に食べよう♪
じゃりんこ隊のふたり、足の裏が痛くて山靴を脱ぎ捨てた。
できることなら もう一歩も歩きたくないのだろう。
小屋の前で休憩している登山者たちも 疲れ果てた様子、皆さん抜け殻のようになっている

元気なのは ひとちが。
特に ちがこさん

「ねぇ ねぇ 桃のソフトクリームにするぅ?」
嬉しそうに小屋前をウロウロ。
ランチのカップラーメンもグッドでしたな。
こらしょと持ってきた食材も ほぼ食べつくした

桃ソフト うまうまです♪
さぁ~てと出発だ。
樹林帯の急坂を下る。
ここではかなり怪我人が勃発しているらしいから注意が必要。
(うん、うん
 )
)足の裏が痛いふたりは無言で下る。
まだかなぁー・・・
ぶつ ぶつ ぶつ・・・
ようやく樹林帯を抜けた。
安心したのか 早く靴を脱ぎたいのか とたんに じゃりんこ隊の歩くスピードが上がる

(あは。。。)
橋を越え広河原に到着、タイミングよく乗ることのできたジャンタクに感謝、芦安の駐車場に無事到着することができた。
お疲れぇーっ!!
がんばった夏の思い出、君たちの青春の1ページとして いつまでも忘れないで欲しい

山の美しさと楽しさを満喫できた北岳山行でした

2011年08月17日
青春の1ページ♪ 前編・・・
2011/8/13・14
根性登り!
北 岳
(赤石山脈北部エリア)
全山行 248回
百名山 40座

標高 北岳 3192.4m
天気 晴れ・
晴れ・ ガス
ガス
山行時間 9時間20分
〈コース〉13日:自宅(2:30)-芦安駐車場(4:30)/ジャンボタクシーで移動(4:45)-夜叉神(5:00-5:20)-広河原(6:00-6:10)-二俣(9:00)-八本歯ノコル(11:10)-北岳山荘(12:30-2:00)-水場(2:30)-北岳山荘(3:30)
夏休みの思い出を作ろう♪
少年から青年に・・・
少しずつ大人に近づいているじゃりんこ登山隊。
ひとちがと共に日本で二番目に高い山、北岳山頂を目指す。
うりゃぁーっ!!
 中学二年生になった しょうたろう選手、部活でシゴかれ小学校時代のメタボ体系から一転、
中学二年生になった しょうたろう選手、部活でシゴかれ小学校時代のメタボ体系から一転、
身長170センチを超え、体重も60キロを割り すっかりスリムになった
 今回わぁー、同じ部活仲間の ひらぴーとの山歩だ。
今回わぁー、同じ部活仲間の ひらぴーとの山歩だ。
新しく登山隊のメンバとなった ひらぴーはバレー部でエースアタッカーでもある
身長も180センチ近くあり、細身ではあるが筋肉質の少年なのだ
こりゃ頼もしい少年たち♪
期待できる!!
荷物をこらしょと背負っていただくことにしよう。
(うひひひひ。。。)
ふたりのザックの重さは ひとり13キロとかなりの重さ
今回の山行のために新しく購入したテント(三人用)と二人用のテント、食欲旺盛な少年たちのために食材も こらしょと詰め込んだ。
(こんなに食べるんかいな?)


よし、準備万端!
 13日深夜・・・
13日深夜・・・
午前2:30、北岳山行に向けていよいよ出発することに
芦安駐車場に到着、お盆の休暇を利用して たくさんの登山者が始発のバスやタクシーに乗り込んでいる。
心配していた駐車場もなんとか確保できた
(ほっ。)
それにしても山のジャンボタクシーなど見たこともない じゃりんこ隊。
「これがジャンボタクシー?」
フツーの9人乗りのでっかいワゴン車が何台も停車する待合で 不思議そうな顔
ジャンタク!
じゃりんこ隊も気に入ったようであ~る
座席の後ろに詰め込まれた大きなザックは ギュウギュウ詰め、うっすらと夜が明け始めた南アルプス林道に向けジャンタクは走り出す

抑えきれない期待と不安・・・
少年たちは 今、まさにこれから始まる 高山へテント泊、翌日登頂 という大きな挑戦に心奮えていたに違いない。
(うん、うん )
)
夜叉神峠でジャンタクは一時停車した、ゲートがまだ閉じているからであ~る。
ひとちが一行が乗り込んだジャンタクの前にも数台のタクシーが並んでいた。
20分程停車待ち、外で出発を待つ登山者たち

皆さん気合入っているようですな。。。
ようやくゲートが開いた、滑りだすようにジャンタクが連なって曲がりくねった林道を上っていく50分ほどの道のりであ~る。
野呂川を挟むようにして 奈良田からの林道が見えた、もう広河原への到着も間近、
高まるテンション
うりゃぁーっ!!
広河原に到着、大きなザックを背負い いよいよ山行のスタートであ~る

北岳の山頂が 輝いている
輝いている

橋の手前にある登山マップの看板で 今日のコースを確認


吊り橋を渡ろう
山行前に注意として 高山、重い荷物、体力の維持のために ゆっくりペースで歩くことを促したはずなのに じゃりんこ隊たちは ズンズン行ってしまった

おい、おい そんな早いペースで歩くと 後半、もたないよぉーっ
ちがこさんが叫ぶ声も聞こえないみたいじゃん
分岐より大樺沢沿いにコースをとる。
山から染み出た水が多い、たくさんの登山者が大きな荷物を背負い登って行く。
ひとちが一行もマケズに登る。
うが うが
うが うが
うが うが
うが

暑い・・・
滝のように汗が出てきた
橋を渡る、大樺沢を流れる水の綺麗なこと

時折休憩を入れ、水分補給、行動食を確実に摂る。
先急ぐ少年たちには 休むことも必要だと教える、熱中症やエネルギー切れにならないようにしなくてはいけないからだ
(そう、そう!)

崩壊地に出た。
沢の上部は雪渓が残っている。

雪渓の横を 豆つぶのような大きさの登山者たちが登っていく
す、すごい 人 人 人!

近いようで なかなか到達できない雪渓まで

うが うが
うが うが
うが うが
うが

うが うが
うが うが
うが うが
うが

あぢぃーーーーーっ↓
ようやく雪渓まできた
ちょびっと沢に降りて休憩しようじゃないの!

うぉぉぉぉぉーーーーっ!
スゴイ さぶ!
雪渓の解けたトンネルに入って じゃりんこ隊もひえひえ~~~っ♪

暑さで温くなったお茶を雪渓が解けた水に放りこむ。
ジャブン!!

プカプカ浮かぶペットボトル、休憩が終わることには キンキン間違いなし
(うはは!)
ついでに顔も洗ってみよう
うげぇぇぇぇーーーー
ち、ちびたすぎぃーっ!!

更に崩壊地を登って行く、ザレた登山道は登りにくく じゃりんこ隊も苦戦気味
二人ともかなり疲れ始めている。
(大丈夫かなぁー?)

二俣に到着であ~る。
これより先は 梯子場の連続、八本歯ノコルまで急登をバランスよく登りきらなくてはいけない。

ここまで重たいザックを背負い、飛ばし飛ばしで登ってきた じゃりんこ隊、思わず梯子場を見上げる。
「ふくらはぎが ぷるぷるして太くなってきたみたい 」
」
ひらぴー 辛そうであ~る。
それでも登らなくちゃ目的地まで行けないのだ。
這い登るようにして梯子を登っていく。

はぁ はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ・・・
はぁ・・・

がんばれぇーっ!!

はぁ はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ・・・
はぁ・・・

まだ先は長いぞぉーっ!!

はぁ はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ・・・
はぁ・・・

迫力ある北岳バットレスの岩肌が横に迫っている

中腹まで登った
今日の目的地、北岳山荘が稜線の上に見える。


今まで登ってきた 激しい梯子場、ひとちが一行の後にも たくさんの登山者が続く

まだまだ登りは続く・・・

 本日、一番荷物の軽い ちがこさん。
本日、一番荷物の軽い ちがこさん。
何で一番軽いザックなのかって?
あは。
大きなザックがなかったからだよ!
(うほほほほ。)
苦しそうに登る じゃりんこ隊を見かねて声をかける。
「ザック変わろうか?」
「うん、大丈夫、でもお腹すいちゃって動けなくなりそう 」
」
しょうたろう選手、エネルギー切れか?

二人ともお互いを意識しているのか、競うようにして ちがこさんにザックを譲ろうとしない。
(あれ あれ 意地の張り合いか?)
根を上げるようなら ちがこさんが代わりに背負うつもりでいたけど どうやらその必要もなさそうだ


いい具合だ。。。
まだまだ がんばれる!
(うひひひひ)
それ!
いくぞぉーっ!!

はぁ はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ・・・
はぁ・・・

進めぇーっ!

はぁ はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ・・・
はぁ・・・

ここで登場 ひとしさん
本日、あまりの荷物の重さに言葉がでないのか?
ひたすら地面を見つめながら ゆっくりと最後方を歩く
忍耐あるのみ!
さすがマイダーリン、かっちょいいよ ひとしさん
いつも ありがと♪
普段なら ひとしさんがカメラーマン、今日は荷物の軽い ちがこさんがカメラーマンだ
(うはははは!)
山を巻くようにして 更に梯子場は続く

そしてお花畑♪

うっひょぉぉぉーーーっ♪
今までの大変さが 吹っ飛んでしまうほど綺麗な山斜面
色とりどりの花が咲き乱れ 重たいザックで苦戦していた ひとしさんだが、ちがこさんからカメラを奪い取り自分で撮影せずにはいられないほどの美しさだ
ひとちが しばし花に夢中!!












それにひきかえ・・・

花そっちのけで ズンズン山荘に向かって行ってしまう じゃりんこ隊
 へっ?
へっ?
なんで?
夏休みの研究のデータ集めをするはずの しょうたろう選手、すでに疲れて写真撮影がはかどらない様子早くテント場に到着したい
(あれま!)
一方、ひらぴーもトイレに行きたくて花畑どころではないらしい
(あらら。。。)
昼、予定通り北岳山荘にテントを張る。
もちろぉ~ん、じゃりんこ隊、大活躍!

到着時間が早かったせいか なかなかいい場所にテントを張ることができた
(よっしゃ!)
 まだ時間も早い、じゃ何する?
まだ時間も早い、じゃ何する?
うはははは!
もちろん水場まで水をゲットしに行くっきゃないでしょ
なんたって 小屋で水を買えば1リットル100円、自分で汲みに行けば無料なわけだから行きましょうか水場まで
始まりました ひとちがのケチケチ山行!
ってなわけで テント場から水場まで 下り30分、登り1時間の水場へゴー♪
疲れ果てている じゃりんこ隊のイヤそうな顔ったら
(がんばりましょうか!)

せっかく登った山の斜面、30分下るってなるとかなり厳しい。
途中で会ったご夫妻も あまりに急で遠そうなので諦めて帰ってきたそうな。
(あは。)
それでも ひとちが一行は行く!
意地でも!

ザレた斜面は歩きにくく ひらぴー苦戦気味

天気も不安定、怪しい黒雲が接近、大粒の雨がボツボツ降ってきた
ひょぇぇぇーーーっ!
カッパ隊ですかぁー↓
泣きっ面にハチ!
とはこのようなことを言うのか?
疲れてヨレヨレの じゃりんこ隊、無言で長い水場までの道を下って行く
それでも花の撮影を続ける しょうたろう選手

無言・・・
がさ がさ がさ・・・
登山道から外れた木の上で 数匹のサルがこちらを見ている

「ねぇ、バカな登山者が こんな雨の中 水場へ行くよ。小屋で水なんか買えばいいじゃんね、ケェ~~~チ!」
サルたちの会話が聞こえた
 ふん!
ふん!
いいじゃん、これが ひとちが流なんだからさ
なんだかよくわからない水場までの道を 半信半疑で下って行く。
本当に水の出ている水場があるのか?
じゃりんこ隊、半ベソ。。。
旧北岳小屋跡を通過、現在の山荘にひかれている黒いホースを発見、やっぱり水場はちゃんとあるらしい。
 ぶぅ
ぶぅ ぶぅ言いながら じゃりんこ隊もついてきた。
ぶぅ言いながら じゃりんこ隊もついてきた。
ようやく水場に到着
ほどよい水量で 三年前の北肩ノ小屋近くの チョロチョロ水場よりかなりよかった。
とても冷たい水、顔を洗いたくても冷たすぎて凍りつきそうじゃん。
8リットルの水を確保、これで水の心配もなくなったわけであ~る

帰り道、もちろん8リットルの水を背負ったのは ひとしさん
エライ!
頼りになりますマイダーリン♪
下った道を1時間かけて ひたすら登る、せっかく洗った顔も汗ダクになった

やっとテント場に戻れたぞぉー
いつの間にかテント場には カラフルにたくさんのテントが立ち並んでいる

ガスですっかり景色のなくなった小屋付近、気温も下がり始めた。
(さぶぅ~っ!)
暗くなる前に夕食を作ろう!
さてさて お楽しみの夕食のメニューは♪
ハムステーキ、カレーライス、パスタにチーズ、野菜となかなか豪華なメニューだったよ
じゃりんこ隊も大喜び!
うま♪
腹いっぺぇー!

 夜になった。
夜になった。
隣のテントで じゃりんこ隊のふたりが ゴソゴソ話をする声が聞こえる・・・
そのうち力尽きたのであろうか?
・・・・・・・・・。。。
爆睡!
ふたりとも一日よく がんばったね
満月の月明かりでペルセウス流星群を見ることはできなかったけど 初めて泊まった山のテント、きっと思い出の1ページになったはず♪
(うん、うん )
)
明日はいよいよ北岳の山頂にアタックだ
 後編はこちら
後編はこちら
根性登り!
北 岳
(赤石山脈北部エリア)
全山行 248回
百名山 40座
標高 北岳 3192.4m
天気
 晴れ・
晴れ・ ガス
ガス山行時間 9時間20分
〈コース〉13日:自宅(2:30)-芦安駐車場(4:30)/ジャンボタクシーで移動(4:45)-夜叉神(5:00-5:20)-広河原(6:00-6:10)-二俣(9:00)-八本歯ノコル(11:10)-北岳山荘(12:30-2:00)-水場(2:30)-北岳山荘(3:30)
夏休みの思い出を作ろう♪
少年から青年に・・・
少しずつ大人に近づいているじゃりんこ登山隊。
ひとちがと共に日本で二番目に高い山、北岳山頂を目指す。
うりゃぁーっ!!
 中学二年生になった しょうたろう選手、部活でシゴかれ小学校時代のメタボ体系から一転、
中学二年生になった しょうたろう選手、部活でシゴかれ小学校時代のメタボ体系から一転、身長170センチを超え、体重も60キロを割り すっかりスリムになった

 今回わぁー、同じ部活仲間の ひらぴーとの山歩だ。
今回わぁー、同じ部活仲間の ひらぴーとの山歩だ。新しく登山隊のメンバとなった ひらぴーはバレー部でエースアタッカーでもある

身長も180センチ近くあり、細身ではあるが筋肉質の少年なのだ

こりゃ頼もしい少年たち♪
期待できる!!
荷物をこらしょと背負っていただくことにしよう。
(うひひひひ。。。)
ふたりのザックの重さは ひとり13キロとかなりの重さ

今回の山行のために新しく購入したテント(三人用)と二人用のテント、食欲旺盛な少年たちのために食材も こらしょと詰め込んだ。
(こんなに食べるんかいな?)
よし、準備万端!
 13日深夜・・・
13日深夜・・・午前2:30、北岳山行に向けていよいよ出発することに

芦安駐車場に到着、お盆の休暇を利用して たくさんの登山者が始発のバスやタクシーに乗り込んでいる。
心配していた駐車場もなんとか確保できた

(ほっ。)
それにしても山のジャンボタクシーなど見たこともない じゃりんこ隊。
「これがジャンボタクシー?」
フツーの9人乗りのでっかいワゴン車が何台も停車する待合で 不思議そうな顔

ジャンタク!
じゃりんこ隊も気に入ったようであ~る

座席の後ろに詰め込まれた大きなザックは ギュウギュウ詰め、うっすらと夜が明け始めた南アルプス林道に向けジャンタクは走り出す

抑えきれない期待と不安・・・
少年たちは 今、まさにこれから始まる 高山へテント泊、翌日登頂 という大きな挑戦に心奮えていたに違いない。
(うん、うん
 )
)夜叉神峠でジャンタクは一時停車した、ゲートがまだ閉じているからであ~る。
ひとちが一行が乗り込んだジャンタクの前にも数台のタクシーが並んでいた。
20分程停車待ち、外で出発を待つ登山者たち

皆さん気合入っているようですな。。。
ようやくゲートが開いた、滑りだすようにジャンタクが連なって曲がりくねった林道を上っていく50分ほどの道のりであ~る。
野呂川を挟むようにして 奈良田からの林道が見えた、もう広河原への到着も間近、
高まるテンション

うりゃぁーっ!!
広河原に到着、大きなザックを背負い いよいよ山行のスタートであ~る

北岳の山頂が
 輝いている
輝いている
橋の手前にある登山マップの看板で 今日のコースを確認

吊り橋を渡ろう

山行前に注意として 高山、重い荷物、体力の維持のために ゆっくりペースで歩くことを促したはずなのに じゃりんこ隊たちは ズンズン行ってしまった

おい、おい そんな早いペースで歩くと 後半、もたないよぉーっ

ちがこさんが叫ぶ声も聞こえないみたいじゃん

分岐より大樺沢沿いにコースをとる。
山から染み出た水が多い、たくさんの登山者が大きな荷物を背負い登って行く。
ひとちが一行もマケズに登る。
うが
 うが
うが うが
うが うが
うが
暑い・・・
滝のように汗が出てきた

橋を渡る、大樺沢を流れる水の綺麗なこと

時折休憩を入れ、水分補給、行動食を確実に摂る。
先急ぐ少年たちには 休むことも必要だと教える、熱中症やエネルギー切れにならないようにしなくてはいけないからだ

(そう、そう!)
崩壊地に出た。
沢の上部は雪渓が残っている。
雪渓の横を 豆つぶのような大きさの登山者たちが登っていく

す、すごい 人 人 人!
近いようで なかなか到達できない雪渓まで

うが
 うが
うが うが
うが うが
うが
うが
 うが
うが うが
うが うが
うが
あぢぃーーーーーっ↓
ようやく雪渓まできた

ちょびっと沢に降りて休憩しようじゃないの!
うぉぉぉぉぉーーーーっ!
スゴイ さぶ!
雪渓の解けたトンネルに入って じゃりんこ隊もひえひえ~~~っ♪
暑さで温くなったお茶を雪渓が解けた水に放りこむ。
ジャブン!!
プカプカ浮かぶペットボトル、休憩が終わることには キンキン間違いなし

(うはは!)
ついでに顔も洗ってみよう

うげぇぇぇぇーーーー
ち、ちびたすぎぃーっ!!
更に崩壊地を登って行く、ザレた登山道は登りにくく じゃりんこ隊も苦戦気味

二人ともかなり疲れ始めている。
(大丈夫かなぁー?)
二俣に到着であ~る。
これより先は 梯子場の連続、八本歯ノコルまで急登をバランスよく登りきらなくてはいけない。
ここまで重たいザックを背負い、飛ばし飛ばしで登ってきた じゃりんこ隊、思わず梯子場を見上げる。
「ふくらはぎが ぷるぷるして太くなってきたみたい
 」
」ひらぴー 辛そうであ~る。
それでも登らなくちゃ目的地まで行けないのだ。
這い登るようにして梯子を登っていく。
はぁ
 はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ・・・
はぁ・・・がんばれぇーっ!!
はぁ
 はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ・・・
はぁ・・・まだ先は長いぞぉーっ!!
はぁ
 はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ・・・
はぁ・・・迫力ある北岳バットレスの岩肌が横に迫っている

中腹まで登った

今日の目的地、北岳山荘が稜線の上に見える。
今まで登ってきた 激しい梯子場、ひとちが一行の後にも たくさんの登山者が続く

まだまだ登りは続く・・・
 本日、一番荷物の軽い ちがこさん。
本日、一番荷物の軽い ちがこさん。何で一番軽いザックなのかって?
あは。
大きなザックがなかったからだよ!
(うほほほほ。)
苦しそうに登る じゃりんこ隊を見かねて声をかける。
「ザック変わろうか?」
「うん、大丈夫、でもお腹すいちゃって動けなくなりそう
 」
」しょうたろう選手、エネルギー切れか?
二人ともお互いを意識しているのか、競うようにして ちがこさんにザックを譲ろうとしない。
(あれ あれ 意地の張り合いか?)
根を上げるようなら ちがこさんが代わりに背負うつもりでいたけど どうやらその必要もなさそうだ

いい具合だ。。。
まだまだ がんばれる!
(うひひひひ)
それ!
いくぞぉーっ!!
はぁ
 はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ・・・
はぁ・・・進めぇーっ!
はぁ
 はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ・・・
はぁ・・・ここで登場 ひとしさん

本日、あまりの荷物の重さに言葉がでないのか?
ひたすら地面を見つめながら ゆっくりと最後方を歩く

忍耐あるのみ!
さすがマイダーリン、かっちょいいよ ひとしさん

いつも ありがと♪
普段なら ひとしさんがカメラーマン、今日は荷物の軽い ちがこさんがカメラーマンだ

(うはははは!)
山を巻くようにして 更に梯子場は続く

そしてお花畑♪
うっひょぉぉぉーーーっ♪
今までの大変さが 吹っ飛んでしまうほど綺麗な山斜面

色とりどりの花が咲き乱れ 重たいザックで苦戦していた ひとしさんだが、ちがこさんからカメラを奪い取り自分で撮影せずにはいられないほどの美しさだ

ひとちが しばし花に夢中!!
それにひきかえ・・・
花そっちのけで ズンズン山荘に向かって行ってしまう じゃりんこ隊

 へっ?
へっ?なんで?
夏休みの研究のデータ集めをするはずの しょうたろう選手、すでに疲れて写真撮影がはかどらない様子早くテント場に到着したい

(あれま!)
一方、ひらぴーもトイレに行きたくて花畑どころではないらしい

(あらら。。。)
昼、予定通り北岳山荘にテントを張る。
もちろぉ~ん、じゃりんこ隊、大活躍!
到着時間が早かったせいか なかなかいい場所にテントを張ることができた

(よっしゃ!)
 まだ時間も早い、じゃ何する?
まだ時間も早い、じゃ何する?うはははは!
もちろん水場まで水をゲットしに行くっきゃないでしょ

なんたって 小屋で水を買えば1リットル100円、自分で汲みに行けば無料なわけだから行きましょうか水場まで

始まりました ひとちがのケチケチ山行!
ってなわけで テント場から水場まで 下り30分、登り1時間の水場へゴー♪
疲れ果てている じゃりんこ隊のイヤそうな顔ったら

(がんばりましょうか!)
せっかく登った山の斜面、30分下るってなるとかなり厳しい。
途中で会ったご夫妻も あまりに急で遠そうなので諦めて帰ってきたそうな。
(あは。)
それでも ひとちが一行は行く!
意地でも!
ザレた斜面は歩きにくく ひらぴー苦戦気味

天気も不安定、怪しい黒雲が接近、大粒の雨がボツボツ降ってきた

ひょぇぇぇーーーっ!
カッパ隊ですかぁー↓
泣きっ面にハチ!
とはこのようなことを言うのか?
疲れてヨレヨレの じゃりんこ隊、無言で長い水場までの道を下って行く

それでも花の撮影を続ける しょうたろう選手

無言・・・
がさ がさ がさ・・・
登山道から外れた木の上で 数匹のサルがこちらを見ている

「ねぇ、バカな登山者が こんな雨の中 水場へ行くよ。小屋で水なんか買えばいいじゃんね、ケェ~~~チ!」
サルたちの会話が聞こえた

 ふん!
ふん!いいじゃん、これが ひとちが流なんだからさ

なんだかよくわからない水場までの道を 半信半疑で下って行く。
本当に水の出ている水場があるのか?
じゃりんこ隊、半ベソ。。。
旧北岳小屋跡を通過、現在の山荘にひかれている黒いホースを発見、やっぱり水場はちゃんとあるらしい。
 ぶぅ
ぶぅ ぶぅ言いながら じゃりんこ隊もついてきた。
ぶぅ言いながら じゃりんこ隊もついてきた。ようやく水場に到着

ほどよい水量で 三年前の北肩ノ小屋近くの チョロチョロ水場よりかなりよかった。
とても冷たい水、顔を洗いたくても冷たすぎて凍りつきそうじゃん。
8リットルの水を確保、これで水の心配もなくなったわけであ~る

帰り道、もちろん8リットルの水を背負ったのは ひとしさん

エライ!
頼りになりますマイダーリン♪
下った道を1時間かけて ひたすら登る、せっかく洗った顔も汗ダクになった

やっとテント場に戻れたぞぉー

いつの間にかテント場には カラフルにたくさんのテントが立ち並んでいる

ガスですっかり景色のなくなった小屋付近、気温も下がり始めた。
(さぶぅ~っ!)
暗くなる前に夕食を作ろう!
さてさて お楽しみの夕食のメニューは♪
ハムステーキ、カレーライス、パスタにチーズ、野菜となかなか豪華なメニューだったよ

じゃりんこ隊も大喜び!
うま♪
腹いっぺぇー!
 夜になった。
夜になった。隣のテントで じゃりんこ隊のふたりが ゴソゴソ話をする声が聞こえる・・・
そのうち力尽きたのであろうか?
・・・・・・・・・。。。
爆睡!
ふたりとも一日よく がんばったね

満月の月明かりでペルセウス流星群を見ることはできなかったけど 初めて泊まった山のテント、きっと思い出の1ページになったはず♪
(うん、うん
 )
)明日はいよいよ北岳の山頂にアタックだ

 後編はこちら
後編はこちら
2010年11月14日
帰路もまた楽し♪
2010/11/06・07
寄って得する おすすめピーク♪
辻 山
(赤石山脈北部エリア)
全山行 203回
百名山 40座

後 編
 前編はこちらから♪
前編はこちらから♪
 中編はこちらから♪
中編はこちらから♪
標高 辻山 2584m
天気 晴れ♪・
晴れ♪・ 曇り
曇り
山行時間 4時間35分
〈コース〉南御室小屋(7:15)-苺平(7:50)-辻山(8:10-8:35)-苺平(8:50)-杖立峠(10:00)-夜叉神峠(11:10)-駐車場(11:50)
行きのバスの中で Yちゃんが立ち寄ることをオススメしてくれた辻山。
白根三山を正面から見ることのできる素晴しいスポットであ~る。
残念なことに立ち寄る登山者は少ないようだ・・・
夜叉神から鳳凰三山に向うなら ちょいと寄り道して欲しい!
白根三山を 一番かっちょいいアングルで見ることができるのは 辻山だよ!!
 後編だよん♪
後編だよん♪
山小屋で色々なことがありましたが ようやく出発です
 山のサンタクロースに 辻山に向うなら苺平の手前で近道があると教えてもらった。
山のサンタクロースに 辻山に向うなら苺平の手前で近道があると教えてもらった。
(うはは! ラッキー♪)
 シラビソの林をなだらかに下っていく。
シラビソの林をなだらかに下っていく。
昨日からの楽しかったこと、余韻を残しての下山であ~る

お天気もマズマズ、近道の分岐を気にしながらも ひとしさんと話に ついつい夢中になり気がついたら苺平に着いちゃったじゃん!
(あち゛ゃぁーっ )
)
うっへぇーーーっ!
近道、見落としちゃったよ↓
 しかたありませんな、きっと目に入らないくらいの地味な看板だったかも。
しかたありませんな、きっと目に入らないくらいの地味な看板だったかも。
(だはははは。)
でも大丈夫、苺平からでも辻山には行けちゃうもんねぇーっ
(うひひひひ)

千頭星山との分岐でもある苺平、樹林帯なので景色はよろしいわけじゃない
 さぁ~てと、辻山のルートはどこかなぁー?
さぁ~てと、辻山のルートはどこかなぁー?
見渡すと ありました ありました じみぃ~な看板
(へっ )
)
よぉーく見ないと書かれている字が読めないじゃん。
登山道も本線とは違い、落ち葉が積もり ほとんど踏み跡がわからない状態です
(ぶぅ )
)

地図では、標高差もほとんどなく ほぼ一直線のルートなので 道迷いを怖がらないで出発です。
先頭を行くのは もちろぉ~ん ちがこさんだよぉー!
(いつものことですが )
)
う~ん、どっちかな?
そんな場所が数箇所あったけど 赤テープを頼りに ひとしさんと進む。
(うりゃ )
)

20分も歩いただろうか?
 サンタに教えてもらった近道との分岐も確認、ようやく山頂にぃー♪
サンタに教えてもらった近道との分岐も確認、ようやく山頂にぃー♪
(やったぁー!!)

す、すごい!
言葉にならない素晴しい景色・・・
辻山の山頂は 山の斜面が丸坊主、景色を遮るものはなく、目の前には白根三山が どかぁーんと広がる・・・
嬉しいのは この山々の裾まで見ることができること
紅葉時期なので 山の上には雪、裾にはカラフルな 紅葉で山は彩られている。
紅葉で山は彩られている。

綺麗・・・
あーーーっ、Yちゃん 教えてくれて ありがとう♪
ひとちが超ゴキゲン
昨日がんばって登った鳳凰三山、そして富士山の絶景・・・

下山路とはいえ、こんな素晴しいスポットを満喫できるのは縦走できたからだね。
(うん、うん )
)

本線に戻り杖立峠を目指そう♪
登山道はなだらかであ~る。

のんびり ちんたら下る。
登山道の脇には こんなものが・・・

霜柱です♪
花がなくなってしまっても 土の間から にょきにょきと成長する霜柱、なかなか可愛いじゃん!
(うひ♪)

水溜りも凍りついて のっかるとパリパリして面白い♪
横道に反れて 遊びまくる ひとちが。
(だから山行時間が遅くなるわけで )
)


いつの間にか景色が開けている。
登山道からも白根三山が美しい姿を楽しませてくれた。

ようやく杖立峠に到着
先客がいるじゃん!
おぉぉぉぉーっ!
昨日、ひとちがと同じ白鳳峠からの縦走コースを歩いていたご夫妻で~る。
昨夜は薬師小屋に宿泊したそうで、ご来光を眺めて下山してきたそうだ。

広島から 73座目の百名山を登った 大和さんご夫妻、お疲れさまでした。
しばし楽しい会話をしてお別れした。
さあ さあ、ピッチを上げて夜叉神峠まで下りますよぉー
序所に 紅葉が目立ってきた。
紅葉が目立ってきた。





本日もたくさんの登山者が鳳凰山を目指している。
(後にわかっかことですが、この辺りで ひとちがを偶然発見したという ブナ太郎さんとすれ違ったそうで、、、お話できず残念でした )
)
ハイカーで賑わう夜叉神峠に到着、あまりの人の多さに 後ずさり
うげぇぇぇーーーっ↓
さすが人気のハイキングスポット

あ゛――――っ
ここじゃ休憩は無理そうね
写真撮影だけして先を急ごう。
そこから先も 次々と登ってくる軽装備のハイカーとすれ違い・・・
なだらかな 紅葉が絶頂期の樹林帯を下っていく。
紅葉が絶頂期の樹林帯を下っていく。
ブナやミズナラの美しい林、ハイカーで人気なのが理解できるねぇー・・・




駐車場に到着、ここもまた 紅葉が素晴しい
紅葉が素晴しい



帰りの林道からは 南アルプス今年の秋を飾る 紅葉した山々を満喫した ひとちがであ~る。
紅葉した山々を満喫した ひとちがであ~る。



今回も最高に楽しい山歩きだったね ひとしさん!
たくさんの人々とコミュニケーションすることができた 鳳凰三山大縦走でした♪
寄って得する おすすめピーク♪
辻 山
(赤石山脈北部エリア)
全山行 203回
百名山 40座
後 編
 前編はこちらから♪
前編はこちらから♪ 中編はこちらから♪
中編はこちらから♪標高 辻山 2584m
天気
 晴れ♪・
晴れ♪・ 曇り
曇り山行時間 4時間35分
〈コース〉南御室小屋(7:15)-苺平(7:50)-辻山(8:10-8:35)-苺平(8:50)-杖立峠(10:00)-夜叉神峠(11:10)-駐車場(11:50)
行きのバスの中で Yちゃんが立ち寄ることをオススメしてくれた辻山。
白根三山を正面から見ることのできる素晴しいスポットであ~る。
残念なことに立ち寄る登山者は少ないようだ・・・
夜叉神から鳳凰三山に向うなら ちょいと寄り道して欲しい!
白根三山を 一番かっちょいいアングルで見ることができるのは 辻山だよ!!
 後編だよん♪
後編だよん♪山小屋で色々なことがありましたが ようやく出発です

 山のサンタクロースに 辻山に向うなら苺平の手前で近道があると教えてもらった。
山のサンタクロースに 辻山に向うなら苺平の手前で近道があると教えてもらった。(うはは! ラッキー♪)
 シラビソの林をなだらかに下っていく。
シラビソの林をなだらかに下っていく。昨日からの楽しかったこと、余韻を残しての下山であ~る

お天気もマズマズ、近道の分岐を気にしながらも ひとしさんと話に ついつい夢中になり気がついたら苺平に着いちゃったじゃん!
(あち゛ゃぁーっ
 )
)うっへぇーーーっ!
近道、見落としちゃったよ↓
 しかたありませんな、きっと目に入らないくらいの地味な看板だったかも。
しかたありませんな、きっと目に入らないくらいの地味な看板だったかも。(だはははは。)
でも大丈夫、苺平からでも辻山には行けちゃうもんねぇーっ

(うひひひひ)
千頭星山との分岐でもある苺平、樹林帯なので景色はよろしいわけじゃない

 さぁ~てと、辻山のルートはどこかなぁー?
さぁ~てと、辻山のルートはどこかなぁー?見渡すと ありました ありました じみぃ~な看板

(へっ
 )
)よぉーく見ないと書かれている字が読めないじゃん。
登山道も本線とは違い、落ち葉が積もり ほとんど踏み跡がわからない状態です

(ぶぅ
 )
)地図では、標高差もほとんどなく ほぼ一直線のルートなので 道迷いを怖がらないで出発です。
先頭を行くのは もちろぉ~ん ちがこさんだよぉー!
(いつものことですが
 )
)う~ん、どっちかな?
そんな場所が数箇所あったけど 赤テープを頼りに ひとしさんと進む。
(うりゃ
 )
)20分も歩いただろうか?
 サンタに教えてもらった近道との分岐も確認、ようやく山頂にぃー♪
サンタに教えてもらった近道との分岐も確認、ようやく山頂にぃー♪(やったぁー!!)
す、すごい!
言葉にならない素晴しい景色・・・
辻山の山頂は 山の斜面が丸坊主、景色を遮るものはなく、目の前には白根三山が どかぁーんと広がる・・・
嬉しいのは この山々の裾まで見ることができること

紅葉時期なので 山の上には雪、裾にはカラフルな
 紅葉で山は彩られている。
紅葉で山は彩られている。綺麗・・・
あーーーっ、Yちゃん 教えてくれて ありがとう♪
ひとちが超ゴキゲン

昨日がんばって登った鳳凰三山、そして富士山の絶景・・・
下山路とはいえ、こんな素晴しいスポットを満喫できるのは縦走できたからだね。
(うん、うん
 )
)本線に戻り杖立峠を目指そう♪
登山道はなだらかであ~る。
のんびり ちんたら下る。
登山道の脇には こんなものが・・・
霜柱です♪
花がなくなってしまっても 土の間から にょきにょきと成長する霜柱、なかなか可愛いじゃん!
(うひ♪)
水溜りも凍りついて のっかるとパリパリして面白い♪
横道に反れて 遊びまくる ひとちが。
(だから山行時間が遅くなるわけで
 )
)いつの間にか景色が開けている。
登山道からも白根三山が美しい姿を楽しませてくれた。
ようやく杖立峠に到着

先客がいるじゃん!
おぉぉぉぉーっ!
昨日、ひとちがと同じ白鳳峠からの縦走コースを歩いていたご夫妻で~る。
昨夜は薬師小屋に宿泊したそうで、ご来光を眺めて下山してきたそうだ。
広島から 73座目の百名山を登った 大和さんご夫妻、お疲れさまでした。
しばし楽しい会話をしてお別れした。
さあ さあ、ピッチを上げて夜叉神峠まで下りますよぉー

序所に
 紅葉が目立ってきた。
紅葉が目立ってきた。本日もたくさんの登山者が鳳凰山を目指している。
(後にわかっかことですが、この辺りで ひとちがを偶然発見したという ブナ太郎さんとすれ違ったそうで、、、お話できず残念でした
 )
)ハイカーで賑わう夜叉神峠に到着、あまりの人の多さに 後ずさり

うげぇぇぇーーーっ↓
さすが人気のハイキングスポット
あ゛――――っ

ここじゃ休憩は無理そうね

写真撮影だけして先を急ごう。
そこから先も 次々と登ってくる軽装備のハイカーとすれ違い・・・
なだらかな
 紅葉が絶頂期の樹林帯を下っていく。
紅葉が絶頂期の樹林帯を下っていく。ブナやミズナラの美しい林、ハイカーで人気なのが理解できるねぇー・・・
駐車場に到着、ここもまた
 紅葉が素晴しい
紅葉が素晴しい
帰りの林道からは 南アルプス今年の秋を飾る
 紅葉した山々を満喫した ひとちがであ~る。
紅葉した山々を満喫した ひとちがであ~る。今回も最高に楽しい山歩きだったね ひとしさん!
たくさんの人々とコミュニケーションすることができた 鳳凰三山大縦走でした♪
2010年11月12日
山小屋 VS テント泊!
2010/11/06・07
山のサンタクロースたち♪
南御室小屋
(赤石山脈北部エリア)

中 編
 前編はこちらから♪
前編はこちらから♪
色々な出会いがある・・・
山小屋での暖炉を囲んでの楽しいひととき。
サンタクロースたちから 大きなプレゼントもらっちゃった♪
今回の山行にでかける数日前、ちがこさんは山小屋に電話した。
「もし もぉ~し、山小屋さんですか?
土曜に寝具なしの素泊で2名お願いしまぁ~す 」
」
でもって 小屋の混み具合を ついでに聞いてみた。
 すると・・・
すると・・・
「お客さんを入れても 今のところ4名です。
もう寒いですから宿泊客は少ないですよ、本当に 寝具なしの素泊でいいんですかぁー
気温は夜になると氷点下5度以下になりますから真冬装備でお出かけください。」
とのこと
ええええーーーっ!
そ、そんなにサブイのぉーっ?
なんだか小屋の人の意味深な言葉
う~ん 怪しい・・・・
何かある・・・
ひとしさんとは テントはもう寒いからヤメにして 小屋もシュラフと食料を持ち込めば 混雑も気にしないで気軽に宿泊できるんじゃないかと 寝具なしの素泊と決めていたのであ~る
 しかぁ~し、たった4名の宿泊者なら 重たい荷物を背負って 山を縦走しなくてもいいんじゃないかと・・・
しかぁ~し、たった4名の宿泊者なら 重たい荷物を背負って 山を縦走しなくてもいいんじゃないかと・・・
(うししししし。)
やっぱり やぁ~めた!
「すんません、やっぱし 一泊二食でお願いしまぁ~す♪」
ひとしさんの了解も得ずに ころっと予定変更。
(ケチな ちがこさんとしては優秀な判断でしたな )
)
 前編の続きです。
前編の続きです。
鳳凰三山を縦走し、ゴキゲンで山を下り 南御室小屋に到着した ひとちが。

いくつかのテントを横目で チラリ。
日が暮れ始め 外は冷え始めていた。

テント泊の方には気の毒と思いながらも ひとちがは ウハウハであ~る。
うはははは!
今夜は ごはんももらえるし、暖かい小屋で のんびり楽しむもんねぇー
(わぁーい )
)
さっそく手続きをする。
丁度、ひとちがと ほぼ同時に小屋に到着した2人の登山者がいた。

ん?
もしかして ひとちがの他 宿泊2名の方々?
夜叉神方面から登ってこられたみたいであ~る。
部屋に案内された。
暖炉の火が ほどよく部屋を暖めている。

広々した部屋には すでに到着して くつろいでいる お兄さんがひとり。
今夜は 全部で5名ってわけだぁー。
(ラッキー♪)
ひとちがの寝場所を確認、どかっとザックを降ろす。
床の間の上に 広い敷布団、毛布も敷かれ 掛け布団、毛布も温かそうであ~る
それにしても この小屋は清潔なのだ。
とても居心地よさそうじゃん!
(うん、うん )
)
テント泊とは違い テントを張ることも食事の支度をすることもない。
同時に到着した2名の方たちは 暖炉の前を陣取り酒盛りを始めた。
うは!
ひとちがも お邪魔しまぁ~す♪
ずーずーしい ちがこさんのこと、さっさとコッヘルを出して 梅酒とツマミを机に並べる。
暖炉の上には やかんが チンチン音をたてて酒盛りを盛り上げてくれたよ。
 はっ!
はっ!
ちがこさん驚いた!!
目の前にいるのは
サンタクロース♪
フツーの登山者と思っていたが よくよく見ると やっぱりサンタクロースなのだ
きゃぁーーーーっ♪
 赤いフリースを着た白いお髭の大柄なサンタ(宮川さん)と 青いダウンを着た小柄なサンタ(高橋さん)♪
赤いフリースを着た白いお髭の大柄なサンタ(宮川さん)と 青いダウンを着た小柄なサンタ(高橋さん)♪
ふたりとも髪も真っ白、どこから見てもサンタとしか言いようがない
「サンタクロースの おじいちゃんだぁー 」
」
思わず叫ぶ ちがこさん。
サンタクロースと呼ばれても否定しないんだから サンタクロースに間違いない
「何もあげないけどね!」
そう言って 青いサンタが笑う。
それから・・・・
食事の時間まで雑談が はじまった。
このサンタたち、実はスゴイ人たちなのだ!
お年は60代後半、ふたりとも大学時代から 山岳部、ワンダーフォーゲルに所属し、今日まで 海外の高山にも足を運ぶ お山のスペシャリストたち・・・
ふたりのお話は 面白く、赤いサンタと 青いサンタは交互に 色々な山の経験談を聞かせてくれたよ
(*高橋さんのホームページ、【山旅記】。海外のお山を中心に素晴しい山行記録を見ることができます。)
食事を済ませ、そしてまた呑みなおし・・・
(とても美味しい夕食でした。)

ふたりの話は尽きることはない。
小屋番さんの 「7時半 消灯です・・・」というまで楽しい話は続いた
また素晴しい人たちと出会うことができた。
まだ クリスマスには ちょいと早いけど 山の楽しい話をプレゼントしてもらった ひとちがであ~る。
クリスマスには ちょいと早いけど 山の楽しい話をプレゼントしてもらった ひとちがであ~る。
気の利いた小屋は 快適だった。
残念なことに 小屋の人たちとは ほとんど会話をすることはなかったけど 山小屋泊は
いいもんだ!(そう! そう!!)
 夜は動けないほど重たい布団で 寒いこともなく
夜は動けないほど重たい布団で 寒いこともなく 爆睡した ひとちがであった・・・
爆睡した ひとちがであった・・・
 朝がきた。
朝がきた。
お兄さんも サンタたちも山頂を目指して出発していった
(別れは淋しいもんですな )
)
ひとちがは?
はははは!
のんびり下るだけですから・・・
小屋の前にあるトイレに寄ってから出発することにぃー
 ところが
ところが
夜は 小屋の中にあるトイレを使わせてもらえるが 日中は外のトイレを利用する決まり。
水場の横にある女性トイレに立ち寄る ちがこさん。

 トイレは3つある。
トイレは3つある。
一番最初のドアを開けた。
がびーーーーん↓
こりゃ ちょいと無理かな
ちがこさんが見たものは・・・
( 写真では撮れないので 図解します
写真では撮れないので 図解します )
)

便器の場外で盛り上がっていた 立派な う○ち。
あ゛―――っ↓
犯人は
ちがこさんじゃありませんからねぇー
テント泊の方に 女性がいたかはわかりませんが、小屋に泊った女性は ちがこさんだけ。
疑われる可能性大!
慌てて二番目のトイレのドアを開ける。
 へっ?
へっ?
何か変だ。
何が変って 床が段差になっているのはいいけど 壁側に便器の後ろがあるので 用を足すのに不便じゃん

このトイレって便器のつけ方
間違ってませんかぁー?
とりあえず三番目のトイレのドアを開ける。
あは↓
便器がない。
床の上に便器型の穴が ぽこんと開いている

究極のトイレ三択!
さぁ、どれにする ちがこさん?
はははは
三番目で
変な汗をかいてしまった
苦笑いをしながら 小屋の前に戻ると ひとしさんが悲惨な顔で 男性トイレから戻ってきた。
「大変でしたぁー 」
」
 ひとしさんの説明によると・・・
ひとしさんの説明によると・・・

男性トイレはふたつある。
最初のトイレに入った所、大変なことに気がついた。
ドアの鍵が壊れている
でもって 扉が開いてしまうので 扉についている紐を 引っ張っていないと用が足せない。
(ひょぇぇーーーっ )
)

落ち着かないので 二番目のトイレに入ってみた。
するとぉー・・・
扉に穴が開いている
丁度 立った位置で目の高さなのだ。
穴は5センチほどあるので 外から覗かれそうで落ち着かない。
(どうしれってか )
)

究極のトイレ選択!
どうやら 穴のトイレに ひとしさんは入ったようだ。
あはははは
色んなことがあるもんですな。
ついでに もうひとつ、トイレの横には な、なんと 素泊小屋なるものがあった。
プレバブの畳の部屋には何もない

うがぁーーーっ!
超サブそうじゃんねぇーっ↓
山小屋の人の意味深な言葉が今ようやく理解できた ひとちが。
危うく凍死する所だった
あ゛―――っ
一泊二食にしといてよかった・・・
 ようやく出発、帰り際にテント泊した登山者に声わかけてみる。
ようやく出発、帰り際にテント泊した登山者に声わかけてみる。
「テントどうでした?」
「サブくて大変でした。あるものすべて着込んでシュラフに潜って眠りましたが あまりの寒さで動けませんでした。テントの中も凍ってましたし 」
」
よ、よかったぁー
テント泊じゃなくて!
山小屋VSテント泊、今回の 勝利は 山小屋かな♪
勝利は 山小屋かな♪
今日もお天気なかなかじゃん!
さぁ、夜叉神峠へ向うよぉーっ♪
 後編に続く・・・
後編に続く・・・
山のサンタクロースたち♪
南御室小屋
(赤石山脈北部エリア)
中 編
 前編はこちらから♪
前編はこちらから♪色々な出会いがある・・・
山小屋での暖炉を囲んでの楽しいひととき。
サンタクロースたちから 大きなプレゼントもらっちゃった♪
今回の山行にでかける数日前、ちがこさんは山小屋に電話した。
「もし もぉ~し、山小屋さんですか?
土曜に寝具なしの素泊で2名お願いしまぁ~す
 」
」でもって 小屋の混み具合を ついでに聞いてみた。
 すると・・・
すると・・・「お客さんを入れても 今のところ4名です。
もう寒いですから宿泊客は少ないですよ、本当に 寝具なしの素泊でいいんですかぁー

気温は夜になると氷点下5度以下になりますから真冬装備でお出かけください。」
とのこと

ええええーーーっ!
そ、そんなにサブイのぉーっ?
なんだか小屋の人の意味深な言葉

う~ん 怪しい・・・・
何かある・・・
ひとしさんとは テントはもう寒いからヤメにして 小屋もシュラフと食料を持ち込めば 混雑も気にしないで気軽に宿泊できるんじゃないかと 寝具なしの素泊と決めていたのであ~る

 しかぁ~し、たった4名の宿泊者なら 重たい荷物を背負って 山を縦走しなくてもいいんじゃないかと・・・
しかぁ~し、たった4名の宿泊者なら 重たい荷物を背負って 山を縦走しなくてもいいんじゃないかと・・・(うししししし。)
やっぱり やぁ~めた!
「すんません、やっぱし 一泊二食でお願いしまぁ~す♪」
ひとしさんの了解も得ずに ころっと予定変更。
(ケチな ちがこさんとしては優秀な判断でしたな
 )
) 前編の続きです。
前編の続きです。鳳凰三山を縦走し、ゴキゲンで山を下り 南御室小屋に到着した ひとちが。
いくつかのテントを横目で チラリ。
日が暮れ始め 外は冷え始めていた。
テント泊の方には気の毒と思いながらも ひとちがは ウハウハであ~る。
うはははは!
今夜は ごはんももらえるし、暖かい小屋で のんびり楽しむもんねぇー

(わぁーい
 )
)さっそく手続きをする。
丁度、ひとちがと ほぼ同時に小屋に到着した2人の登山者がいた。
ん?
もしかして ひとちがの他 宿泊2名の方々?
夜叉神方面から登ってこられたみたいであ~る。
部屋に案内された。
暖炉の火が ほどよく部屋を暖めている。
広々した部屋には すでに到着して くつろいでいる お兄さんがひとり。
今夜は 全部で5名ってわけだぁー。
(ラッキー♪)
ひとちがの寝場所を確認、どかっとザックを降ろす。
床の間の上に 広い敷布団、毛布も敷かれ 掛け布団、毛布も温かそうであ~る

それにしても この小屋は清潔なのだ。
とても居心地よさそうじゃん!
(うん、うん
 )
)テント泊とは違い テントを張ることも食事の支度をすることもない。
同時に到着した2名の方たちは 暖炉の前を陣取り酒盛りを始めた。
うは!
ひとちがも お邪魔しまぁ~す♪
ずーずーしい ちがこさんのこと、さっさとコッヘルを出して 梅酒とツマミを机に並べる。
暖炉の上には やかんが チンチン音をたてて酒盛りを盛り上げてくれたよ。
 はっ!
はっ!ちがこさん驚いた!!
目の前にいるのは
サンタクロース♪
フツーの登山者と思っていたが よくよく見ると やっぱりサンタクロースなのだ

きゃぁーーーーっ♪
 赤いフリースを着た白いお髭の大柄なサンタ(宮川さん)と 青いダウンを着た小柄なサンタ(高橋さん)♪
赤いフリースを着た白いお髭の大柄なサンタ(宮川さん)と 青いダウンを着た小柄なサンタ(高橋さん)♪ふたりとも髪も真っ白、どこから見てもサンタとしか言いようがない

「サンタクロースの おじいちゃんだぁー
 」
」思わず叫ぶ ちがこさん。
サンタクロースと呼ばれても否定しないんだから サンタクロースに間違いない

「何もあげないけどね!」
そう言って 青いサンタが笑う。
それから・・・・
食事の時間まで雑談が はじまった。
このサンタたち、実はスゴイ人たちなのだ!
お年は60代後半、ふたりとも大学時代から 山岳部、ワンダーフォーゲルに所属し、今日まで 海外の高山にも足を運ぶ お山のスペシャリストたち・・・
ふたりのお話は 面白く、赤いサンタと 青いサンタは交互に 色々な山の経験談を聞かせてくれたよ

(*高橋さんのホームページ、【山旅記】。海外のお山を中心に素晴しい山行記録を見ることができます。)
食事を済ませ、そしてまた呑みなおし・・・
(とても美味しい夕食でした。)
ふたりの話は尽きることはない。
小屋番さんの 「7時半 消灯です・・・」というまで楽しい話は続いた

また素晴しい人たちと出会うことができた。
まだ
 クリスマスには ちょいと早いけど 山の楽しい話をプレゼントしてもらった ひとちがであ~る。
クリスマスには ちょいと早いけど 山の楽しい話をプレゼントしてもらった ひとちがであ~る。気の利いた小屋は 快適だった。
残念なことに 小屋の人たちとは ほとんど会話をすることはなかったけど 山小屋泊は
いいもんだ!(そう! そう!!)
 夜は動けないほど重たい布団で 寒いこともなく
夜は動けないほど重たい布団で 寒いこともなく 爆睡した ひとちがであった・・・
爆睡した ひとちがであった・・・ 朝がきた。
朝がきた。お兄さんも サンタたちも山頂を目指して出発していった

(別れは淋しいもんですな
 )
)ひとちがは?
はははは!
のんびり下るだけですから・・・
小屋の前にあるトイレに寄ってから出発することにぃー

 ところが
ところが
夜は 小屋の中にあるトイレを使わせてもらえるが 日中は外のトイレを利用する決まり。
水場の横にある女性トイレに立ち寄る ちがこさん。
 トイレは3つある。
トイレは3つある。一番最初のドアを開けた。
がびーーーーん↓
こりゃ ちょいと無理かな

ちがこさんが見たものは・・・
(
 写真では撮れないので 図解します
写真では撮れないので 図解します )
)
便器の場外で盛り上がっていた 立派な う○ち。
あ゛―――っ↓
犯人は
ちがこさんじゃありませんからねぇー
テント泊の方に 女性がいたかはわかりませんが、小屋に泊った女性は ちがこさんだけ。
疑われる可能性大!
慌てて二番目のトイレのドアを開ける。
 へっ?
へっ?何か変だ。
何が変って 床が段差になっているのはいいけど 壁側に便器の後ろがあるので 用を足すのに不便じゃん


このトイレって便器のつけ方
間違ってませんかぁー?
とりあえず三番目のトイレのドアを開ける。
あは↓
便器がない。
床の上に便器型の穴が ぽこんと開いている


究極のトイレ三択!
さぁ、どれにする ちがこさん?
はははは

三番目で

変な汗をかいてしまった

苦笑いをしながら 小屋の前に戻ると ひとしさんが悲惨な顔で 男性トイレから戻ってきた。
「大変でしたぁー
 」
」 ひとしさんの説明によると・・・
ひとしさんの説明によると・・・男性トイレはふたつある。
最初のトイレに入った所、大変なことに気がついた。
ドアの鍵が壊れている

でもって 扉が開いてしまうので 扉についている紐を 引っ張っていないと用が足せない。
(ひょぇぇーーーっ
 )
)
落ち着かないので 二番目のトイレに入ってみた。
するとぉー・・・
扉に穴が開いている

丁度 立った位置で目の高さなのだ。
穴は5センチほどあるので 外から覗かれそうで落ち着かない。
(どうしれってか
 )
)
究極のトイレ選択!
どうやら 穴のトイレに ひとしさんは入ったようだ。
あはははは

色んなことがあるもんですな。
ついでに もうひとつ、トイレの横には な、なんと 素泊小屋なるものがあった。
プレバブの畳の部屋には何もない

うがぁーーーっ!
超サブそうじゃんねぇーっ↓
山小屋の人の意味深な言葉が今ようやく理解できた ひとちが。
危うく凍死する所だった

あ゛―――っ
一泊二食にしといてよかった・・・
 ようやく出発、帰り際にテント泊した登山者に声わかけてみる。
ようやく出発、帰り際にテント泊した登山者に声わかけてみる。「テントどうでした?」
「サブくて大変でした。あるものすべて着込んでシュラフに潜って眠りましたが あまりの寒さで動けませんでした。テントの中も凍ってましたし
 」
」よ、よかったぁー
テント泊じゃなくて!
山小屋VSテント泊、今回の
 勝利は 山小屋かな♪
勝利は 山小屋かな♪今日もお天気なかなかじゃん!
さぁ、夜叉神峠へ向うよぉーっ♪
 後編に続く・・・
後編に続く・・・2010年11月10日
鳳凰三山 ピーカン晴れ♪
2010/11/06・07
とっておきのスペシャルコース♪
鳳凰三山
(赤石山脈北部エリア)
全山行 203回
百名山 40座

前 編
標高 高峰 2778m 地蔵ヶ岳 2764m 観音岳 2840m 薬師岳 2780m
天気 ピーカン晴れ♪
ピーカン晴れ♪
山行時間 9時間10分
〈コース〉自宅(2:30)-広河原(6:50)-白鳳峠登山口(7:05)-白鳳峠(9:00)-高峰(10:40-11:00)-赤ヌケ沢ノ頭(11:45)-地蔵ヶ岳(12:00-12:40)-赤ヌケ沢ノ頭-観音岳(1:50-2:20)-薬師岳(2:50)-南御室小屋(4:00)
素晴しい花崗岩の山・・・
白い砂、青空に聳え立つ地蔵ヶ岳のオベリスク・・・
鳳凰三山を縦走しよう!
ガッツり登っちゃいますよぉー!!
今週も ひとちがの旅が始まった。
 げっ。。。。
げっ。。。。
車、停まっちゃいそうじゃん
ハプニングであ~る
真夜中、前日拝借した すえたろうさんのエクストレールは 朝霧付近でエンジントラブル!
まだ走行している車は少ないが 霧の中これ以上進むのは不可能、愕然とする ひとちが
 以前の ひとしさんなら、こんなハプニングにみまわれた場合、
以前の ひとしさんなら、こんなハプニングにみまわれた場合、
「もう いいです、ヤメましょう 」
」
と 間違いなく言った
しかぁ~し、ひとしさんも強くなりましたよぉー
Uターンして すえちせ宅に直行、山にはあまり出番のないご老体のギャランに乗り換え改めて出発することにぃー
内心 ちがこさんもピンチであ~る
ご老体のギャランのナビは 全く役に立たないので地図がないと南アルプスのバスが出る 芦安には行けないのだ!
道路マップ持ってこなかったしぃー
(道がわからんじゃん )
)
 おっ!
おっ!
そうそう・・・
思い出した、先日 ちせこさんに貸してやった 山のアクセス本が すえちせっちにあったっけ!
(ラッキー♪)
すえちせ宅の裏口から まるで泥棒のように侵入する ちがこさん
生まれ育った家とはいえ、真っ暗闇の中、裏口の鍵の隠し場所を探すのも大変、その上 鍵穴がよく見えないときた!
(ふんがぁー )
)
ようやく開いた裏口が開いた。
なんとかギャランのキーとアクセス本をゲットし ようやく一時間遅れで出発
(よっしゃ
 )
)
ふはぁぁぁ・・・・
朝から大変だったぁー・・・
ひとしさんは 遅れた時間を取り戻すために車をブンブン飛ばす。
(うっひょぉーーーっ )
)
なんたって始発の バスに間に合いたいからであ~る。
バスに間に合いたいからであ~る。
 今回の縦走は 夜叉神へ車を停め、始発の
今回の縦走は 夜叉神へ車を停め、始発の バスに乗車、広河原から白鳳峠を登りたい。
バスに乗車、広河原から白鳳峠を登りたい。
そのためには 手前にある芦安のバス停で 料金を支払い 夜叉神で待っていなくてはいけないからだ。
しかぁ~し、現実は甘くはないですな
芦安に到着したのは 始発の バスには ちょいと間に合わなかった。
バスには ちょいと間に合わなかった。
(がぁぁぁ~~~ん )
)
 おや?
おや?
ラッキーなことに タクシーが乗客待ちしてるじゃん!
バスは出発しちゃったけど 満員になれば タクシーは出る。
(うほほ!)
さっそく交渉
二人分のお金を払い 夜叉神へ再び車を飛ばす。
「よかったねぇー、ひとしさん。これで予定通りの山行ができるね♪」
ひとしさんも ホッとしたようであ~る。
ホッとしたようであ~る。
山靴を履いて支度していると タクシーがきた。
(わぁーい )
)
大急ぎで荷物を ずるずる引きずりながらタクシーへ向う ちがこさん。
 ん?こちらを見ている人物がぁー・・・
ん?こちらを見ている人物がぁー・・・
「ひとちがさんじゃありませんか 」
」
な、なんと ひとちがに声をかけた人物・・・
うっへぇぇぇーーーーっ!
Yちゃんじゃん!
ぶ、ぶったまげぇーっ!!

Yちゃんは ひとちがの山友であ~る。
ブログ上でも 長いお付き合い。
偶然とはいえ、同じタクシーに乗り合わせることになるとは
(うはははは!)
これも 車が故障して時間がずれたハプニング
なんてラッキー♪
(うん、うん )
)
南アルプス林道の紅葉も絶頂期、タクシーの運転手さんのトークと Yちゃんとの会話を楽しみながら広河原に向う ひとちがであった
広河原に到着、甲斐駒に向うYちゃんとは ここでお別れ、北沢峠行きのバスに 手を振る ちがこさん。
手を振る ちがこさん。
って・・・
Yちゃんに 手を振ったのに 乗客の皆さん ほぼ全員 ちがこさんに
手を振ったのに 乗客の皆さん ほぼ全員 ちがこさんに 手を振っている。
手を振っている。
(あはははは・・・ちょいと恥ずかしい ちがこさんでした )
)
さっそく登山口に向う
林道から見える北岳が雪化粧した姿も格別であ~る。

登山口から いきなりの急登が始まった

ひとちがの他にも登山者が数名、同じコースから鳳凰三山を目指す。
地図にも 【厳しい登り】と記載はあったが う~ん、ホントにキビシーッ
 延々と登る
延々と登る
 登るしかない
登るしかない
うっへぇーーーっ!!
美しいシラビソの林を抜け ようやく大きな石が ゴロゴロした白鳳峠に到着。
(やったね )
)

ぶふぁぁぁぁーーーっ
た、大変だったねぇー・・・・
振り返ると 北岳が どかんとスゴイ迫力であ~る

八ヶ岳が くっきりと青空に浮かんでいる・・・

きゃぁーっ!
超綺麗♪
あまりの素晴しさに見とれ 足が先に進まない程なのだ

と。
 安心しちゃいけません。
安心しちゃいけません。
ここからも急登が続く、高峰までは景色はよいけど なかなか手ごわい。
 うが
うが  うが
うが  うが
うが  うが・・・・
うが・・・・
がんばれぇーっ!
 おっ♪
おっ♪
あれに見えるは 地蔵ヶ岳のオベリスクじゃん!
とんがった頭が ぴょこんと見えた。
俄然張り切る ひとちが。

高峰に到着、さっそく 携帯で すえちせに連絡を入れとこう。
朝起きたら いつの間にか 車が入れ替わっているのを見たら さぞかし驚くでしょうからね!
(すえちせは爆睡してましたから )
)

わぁ~ぉ♪
それにしても なんていい景色・・・
360度の大パノラマじゃんねぇーっ!!

高峰からの展望を満喫して 地蔵ヶ岳に向う。

地蔵ヶ岳の山容は 花崗岩の隆起した無数の岩に囲まれ、まるでたくさんの仏像が立ち並んでいるようにも見える
ちょいと下って アカヌケ沢ノ頭に到着、観音岳と地蔵ヶ岳の分岐であ~る。
ザックをデポして 10分ほど下ると 賽の河原、オベリスクの直下なのだが だぁ~れもいない
な、なんで?
皆さんオベリスクに
登らないんですかぁー?
こんなにスゴイ オベリスクに登れちゃうのに

賽の河原に降りた。

ひとちが?
もちろん登りますとも!
(うはははは!)

さっそく岩を這い登る
(うりゃぁーーーっ!)
でっかい岩は見上げるとクラクラするほど高い
三年前に登った岩の限界まできた。
やっぱし怖いもんは 怖い
大きな石は なんとか手は届くものの 重たいお尻の ちがこさんには よいこらしょとがんばっても登れそうにない。
(ふぇぇぇーん )
)
もし登れたとしても 降りるのは絶対無理そうなので やっぱり断念、ひとしさんに希望を託す・・・
さすが マイダ~リン♪
 ひょい
ひょい  ひょいと岩を登る姿は かっちょいい!
ひょいと岩を登る姿は かっちょいい!
 しかぁ~し、山頂岩の割れ目に垂れ下がるロープまでは 難しいらしい・・・
しかぁ~し、山頂岩の割れ目に垂れ下がるロープまでは 難しいらしい・・・
「 怖いですぅー・・・、行けないこともないですが 危険そうなので今回は ここまでにしておきます。」
怖いですぅー・・・、行けないこともないですが 危険そうなので今回は ここまでにしておきます。」
(慎重派の ひとしさんですから )
)
さぁ~て、ひとしさんは どこまで登ったのかな?
うはは!
ここまでじゃぁーっ!

誰もいない地蔵岳を満喫し、デポしたザックの アカヌケ沢ノ頭まで 登り返す。
地蔵ヶ岳を眺めながら ランチを楽しむご夫妻と合流、ひとちがも おむすびをパクつく。
(山ごはんは最高ですな )
)

まだまだ先は長い
観音岳に向けて出発♪
(よっしゃ!)

 登って
登って 降りて
降りて  登って
登って 降りて・・・
降りて・・・
過去の記憶は乏しくなりかけていた。
本日は山小屋に宿泊なので時間のゆとりがあるので 素晴しい稜線を楽しもう
(うん うん )
)




観音岳に到着、振り返ると さっき登ったばかりのオベリスクが小さくなっている。

薬師岳方向は 花崗岩の白い美しい稜線が続く・・・

がんばって登って ホントよかったぁー・・・

超ゴキゲンな ひとちが、
薬師岳でイエーっ!

ちょいと遊びすぎたかな
(あはは。)
雲が湧き上がって雲海を作り出している。
そろそろ小屋へ向おう!
今夜は 南御室小屋に宿泊であ~る
(ケチな ひとちがが一泊二食の小屋泊なんで珍しいでしょ? これには深いわけがあったのだ!)
下っていくと すぐ下にある薬師小屋は 随分と賑わっている。
夜叉神方面からの登山者で 小屋の外にあるテーブルベンチも満席じゃん
(この日、50名程の宿泊者がいたそうです。)

薬師小屋
最後の 砂払い岳を越えよう
11月を過ぎると山は冬支度を始める。
ツララも成長し始めてこの通り

大きな巨岩が立ち並ぶその中には ガマ石なるカエルが どでんと座っていたよ。
(わはははは!)

 樹林帯を のんびり下ると広い敷地に到着、南御室小屋であ~る。
樹林帯を のんびり下ると広い敷地に到着、南御室小屋であ~る。
テント場も広く、快適そうな小屋じゃんねぇー

南御室小屋


テント場 小屋の中


小屋のデッキ 水場
 ん?
ん?
夜叉神方面から ひとちがと山小屋にほぼ同時に到着したのは?
 続きは中編でのお楽しみ♪
続きは中編でのお楽しみ♪
 後編はこちらから♪
後編はこちらから♪
とっておきのスペシャルコース♪
鳳凰三山
(赤石山脈北部エリア)
全山行 203回
百名山 40座
前 編
標高 高峰 2778m 地蔵ヶ岳 2764m 観音岳 2840m 薬師岳 2780m
天気
 ピーカン晴れ♪
ピーカン晴れ♪山行時間 9時間10分
〈コース〉自宅(2:30)-広河原(6:50)-白鳳峠登山口(7:05)-白鳳峠(9:00)-高峰(10:40-11:00)-赤ヌケ沢ノ頭(11:45)-地蔵ヶ岳(12:00-12:40)-赤ヌケ沢ノ頭-観音岳(1:50-2:20)-薬師岳(2:50)-南御室小屋(4:00)
素晴しい花崗岩の山・・・
白い砂、青空に聳え立つ地蔵ヶ岳のオベリスク・・・
鳳凰三山を縦走しよう!
ガッツり登っちゃいますよぉー!!
今週も ひとちがの旅が始まった。
 げっ。。。。
げっ。。。。車、停まっちゃいそうじゃん

ハプニングであ~る

真夜中、前日拝借した すえたろうさんのエクストレールは 朝霧付近でエンジントラブル!
まだ走行している車は少ないが 霧の中これ以上進むのは不可能、愕然とする ひとちが

 以前の ひとしさんなら、こんなハプニングにみまわれた場合、
以前の ひとしさんなら、こんなハプニングにみまわれた場合、「もう いいです、ヤメましょう
 」
」と 間違いなく言った

しかぁ~し、ひとしさんも強くなりましたよぉー

Uターンして すえちせ宅に直行、山にはあまり出番のないご老体のギャランに乗り換え改めて出発することにぃー

内心 ちがこさんもピンチであ~る

ご老体のギャランのナビは 全く役に立たないので地図がないと南アルプスのバスが出る 芦安には行けないのだ!
道路マップ持ってこなかったしぃー

(道がわからんじゃん
 )
) おっ!
おっ!そうそう・・・
思い出した、先日 ちせこさんに貸してやった 山のアクセス本が すえちせっちにあったっけ!
(ラッキー♪)
すえちせ宅の裏口から まるで泥棒のように侵入する ちがこさん

生まれ育った家とはいえ、真っ暗闇の中、裏口の鍵の隠し場所を探すのも大変、その上 鍵穴がよく見えないときた!
(ふんがぁー
 )
)ようやく開いた裏口が開いた。
なんとかギャランのキーとアクセス本をゲットし ようやく一時間遅れで出発

(よっしゃ

 )
)ふはぁぁぁ・・・・
朝から大変だったぁー・・・
ひとしさんは 遅れた時間を取り戻すために車をブンブン飛ばす。
(うっひょぉーーーっ
 )
)なんたって始発の
 バスに間に合いたいからであ~る。
バスに間に合いたいからであ~る。 今回の縦走は 夜叉神へ車を停め、始発の
今回の縦走は 夜叉神へ車を停め、始発の バスに乗車、広河原から白鳳峠を登りたい。
バスに乗車、広河原から白鳳峠を登りたい。そのためには 手前にある芦安のバス停で 料金を支払い 夜叉神で待っていなくてはいけないからだ。
しかぁ~し、現実は甘くはないですな

芦安に到着したのは 始発の
 バスには ちょいと間に合わなかった。
バスには ちょいと間に合わなかった。(がぁぁぁ~~~ん
 )
) おや?
おや?ラッキーなことに タクシーが乗客待ちしてるじゃん!
バスは出発しちゃったけど 満員になれば タクシーは出る。
(うほほ!)
さっそく交渉

二人分のお金を払い 夜叉神へ再び車を飛ばす。
「よかったねぇー、ひとしさん。これで予定通りの山行ができるね♪」
ひとしさんも
 ホッとしたようであ~る。
ホッとしたようであ~る。山靴を履いて支度していると タクシーがきた。
(わぁーい
 )
)大急ぎで荷物を ずるずる引きずりながらタクシーへ向う ちがこさん。
 ん?こちらを見ている人物がぁー・・・
ん?こちらを見ている人物がぁー・・・「ひとちがさんじゃありませんか
 」
」な、なんと ひとちがに声をかけた人物・・・
うっへぇぇぇーーーーっ!
Yちゃんじゃん!
ぶ、ぶったまげぇーっ!!
Yちゃんは ひとちがの山友であ~る。
ブログ上でも 長いお付き合い。
偶然とはいえ、同じタクシーに乗り合わせることになるとは

(うはははは!)
これも 車が故障して時間がずれたハプニング

なんてラッキー♪
(うん、うん
 )
)南アルプス林道の紅葉も絶頂期、タクシーの運転手さんのトークと Yちゃんとの会話を楽しみながら広河原に向う ひとちがであった

広河原に到着、甲斐駒に向うYちゃんとは ここでお別れ、北沢峠行きのバスに
 手を振る ちがこさん。
手を振る ちがこさん。って・・・
Yちゃんに
 手を振ったのに 乗客の皆さん ほぼ全員 ちがこさんに
手を振ったのに 乗客の皆さん ほぼ全員 ちがこさんに 手を振っている。
手を振っている。(あはははは・・・ちょいと恥ずかしい ちがこさんでした
 )
)さっそく登山口に向う

林道から見える北岳が雪化粧した姿も格別であ~る。
登山口から いきなりの急登が始まった

ひとちがの他にも登山者が数名、同じコースから鳳凰三山を目指す。
地図にも 【厳しい登り】と記載はあったが う~ん、ホントにキビシーッ

 延々と登る
延々と登る
 登るしかない
登るしかない
うっへぇーーーっ!!
美しいシラビソの林を抜け ようやく大きな石が ゴロゴロした白鳳峠に到着。
(やったね
 )
)ぶふぁぁぁぁーーーっ
た、大変だったねぇー・・・・
振り返ると 北岳が どかんとスゴイ迫力であ~る

八ヶ岳が くっきりと青空に浮かんでいる・・・
きゃぁーっ!
超綺麗♪
あまりの素晴しさに見とれ 足が先に進まない程なのだ

と。
 安心しちゃいけません。
安心しちゃいけません。ここからも急登が続く、高峰までは景色はよいけど なかなか手ごわい。
 うが
うが  うが
うが  うが
うが  うが・・・・
うが・・・・がんばれぇーっ!
 おっ♪
おっ♪あれに見えるは 地蔵ヶ岳のオベリスクじゃん!
とんがった頭が ぴょこんと見えた。
俄然張り切る ひとちが。
高峰に到着、さっそく 携帯で すえちせに連絡を入れとこう。
朝起きたら いつの間にか 車が入れ替わっているのを見たら さぞかし驚くでしょうからね!
(すえちせは爆睡してましたから
 )
)わぁ~ぉ♪
それにしても なんていい景色・・・
360度の大パノラマじゃんねぇーっ!!
高峰からの展望を満喫して 地蔵ヶ岳に向う。
地蔵ヶ岳の山容は 花崗岩の隆起した無数の岩に囲まれ、まるでたくさんの仏像が立ち並んでいるようにも見える

ちょいと下って アカヌケ沢ノ頭に到着、観音岳と地蔵ヶ岳の分岐であ~る。
ザックをデポして 10分ほど下ると 賽の河原、オベリスクの直下なのだが だぁ~れもいない

な、なんで?
皆さんオベリスクに
登らないんですかぁー?
こんなにスゴイ オベリスクに登れちゃうのに

賽の河原に降りた。
ひとちが?
もちろん登りますとも!
(うはははは!)
さっそく岩を這い登る

(うりゃぁーーーっ!)
でっかい岩は見上げるとクラクラするほど高い

三年前に登った岩の限界まできた。
やっぱし怖いもんは 怖い

大きな石は なんとか手は届くものの 重たいお尻の ちがこさんには よいこらしょとがんばっても登れそうにない。
(ふぇぇぇーん
 )
)もし登れたとしても 降りるのは絶対無理そうなので やっぱり断念、ひとしさんに希望を託す・・・
さすが マイダ~リン♪
 ひょい
ひょい  ひょいと岩を登る姿は かっちょいい!
ひょいと岩を登る姿は かっちょいい! しかぁ~し、山頂岩の割れ目に垂れ下がるロープまでは 難しいらしい・・・
しかぁ~し、山頂岩の割れ目に垂れ下がるロープまでは 難しいらしい・・・「
 怖いですぅー・・・、行けないこともないですが 危険そうなので今回は ここまでにしておきます。」
怖いですぅー・・・、行けないこともないですが 危険そうなので今回は ここまでにしておきます。」(慎重派の ひとしさんですから
 )
)さぁ~て、ひとしさんは どこまで登ったのかな?
うはは!
ここまでじゃぁーっ!
誰もいない地蔵岳を満喫し、デポしたザックの アカヌケ沢ノ頭まで 登り返す。
地蔵ヶ岳を眺めながら ランチを楽しむご夫妻と合流、ひとちがも おむすびをパクつく。
(山ごはんは最高ですな
 )
)まだまだ先は長い

観音岳に向けて出発♪
(よっしゃ!)
 登って
登って 降りて
降りて  登って
登って 降りて・・・
降りて・・・過去の記憶は乏しくなりかけていた。
本日は山小屋に宿泊なので時間のゆとりがあるので 素晴しい稜線を楽しもう

(うん うん
 )
)観音岳に到着、振り返ると さっき登ったばかりのオベリスクが小さくなっている。
薬師岳方向は 花崗岩の白い美しい稜線が続く・・・
がんばって登って ホントよかったぁー・・・
超ゴキゲンな ひとちが、
薬師岳でイエーっ!
ちょいと遊びすぎたかな

(あはは。)
雲が湧き上がって雲海を作り出している。
そろそろ小屋へ向おう!
今夜は 南御室小屋に宿泊であ~る

(ケチな ひとちがが一泊二食の小屋泊なんで珍しいでしょ? これには深いわけがあったのだ!)
下っていくと すぐ下にある薬師小屋は 随分と賑わっている。
夜叉神方面からの登山者で 小屋の外にあるテーブルベンチも満席じゃん

(この日、50名程の宿泊者がいたそうです。)
薬師小屋
最後の 砂払い岳を越えよう

11月を過ぎると山は冬支度を始める。
ツララも成長し始めてこの通り

大きな巨岩が立ち並ぶその中には ガマ石なるカエルが どでんと座っていたよ。
(わはははは!)
 樹林帯を のんびり下ると広い敷地に到着、南御室小屋であ~る。
樹林帯を のんびり下ると広い敷地に到着、南御室小屋であ~る。テント場も広く、快適そうな小屋じゃんねぇー

南御室小屋
テント場 小屋の中
小屋のデッキ 水場
 ん?
ん?夜叉神方面から ひとちがと山小屋にほぼ同時に到着したのは?
 続きは中編でのお楽しみ♪
続きは中編でのお楽しみ♪ 後編はこちらから♪
後編はこちらから♪2010年08月16日
終わりよければ すべてよし!
2010/08/13・14
聖岳
南アルプス
全山行 193回
百名山 38座

標高 聖岳 3013m
天気
 ガス
ガス
山行時間 28時間10分
距離 33.10km
〈コース〉13日・自宅(2:30)-畑薙第一ダム・夏季臨時駐車場(6:45/バス)-聖登山口(7:45)-造林小屋跡(10:20-10:30)-聖平小屋(2:10)
14日・聖平小屋(4:10)-山頂(7:10-7:20)-聖平小屋(9:10)-登山口(?)
タイムリミットは 昼12時ジャスト。
登山口の下山ルートの山行タイムは平均4時間45分。
現在の時刻は9時10分、たった2時間50分しかないのであ~る。
「2時間も山行タイムを縮めることなんて できるわけないじゃん!」
そして・・・
ひとちがの無謀なる挑戦が今始まった・・・・
最終バスに間に合うことができるか ひとちが!!
駐車場までの車でのアクセスは長く、クネクネと曲がる山間の道路は体調不良の ちがこさんには最悪の状況。
(ふぇぇぇ~ん )
)
車がカーブで揺れるたび 気持ちが悪く本日の山行の行く先は雲行きが怪しい
「ちがこさん、大丈夫?」
ようやく夏休みに入ったばかりの ひとしさんとしては楽しく車中を いつもじゃぁ ひとりしゃべりまくっている ちがこさんが無言で大人しいのは不安で仕方ないのであ~る
「うん・・・ 大丈夫だよぉ 」
」
答える ちがこさんも大丈夫という割には力もなくクジケ気味だ。
せっかく計画していた山行が おじゃんになるのは忍びなく、気合だけで今回の山行を続けることを決意していた。
(本当に大丈夫なわけ?)
ようやく畑薙ダム臨時駐車場に到着、去年は手前にあったゲートは取り除かれ 時間を気にすることもなく早めに車を駐車できたのは予想外、すでにたくさんの車が駐車されている駐車場に ひとちがも乗り込む!
(よっしゃ )
)

〈今回の山行予定〉
初日:聖登山口→聖平小屋
2日目:聖岳→兎岳→中盛丸山→大沢岳→赤石岳非難小屋
3日目:赤石岳→椹島ロッジ
初日の聖平小屋までは6時間であ~る。
バスを降りた たくさんの登山者と共に いよいよスタート
(うりゃ )
)

2日目に宿泊予定の 赤石岳非難小屋はテントを張ることができない、ってことは 3000円のバス代をチャラにするためにも小屋泊しなければいけない現状があるわけで・・・
(うはははは。)
ザックの中身は 食料と着替え、いつもより少なめの水と前回の甲斐駒山行より やや軽めであ~る
ところが・・・
楽しいはずの登り、ちがこさんの体調はやっぱりすぐれない
いつも元気な ちがこさん!
どうしちゃったの?
歩けど 歩けど 一向に回復しない体調と闘う ちがこさん。
周りをキョロキョロする気力もなく 必死で登る。
が・・・
はぁ はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ
はぁ ・・・・
・・・・
息が荒く余裕がない。
「大丈夫?」
後方を歩く ひとしさんも心配を隠せない
吊橋の横で たくさんの登山者が休憩中。
しかぁ~し、ひとちがは進む!
混雑がキライな ひとしさんと 少しでも早く山小屋に到着したい 体調不良の ちがこさんとしては休んでいる暇はないのであ~る。


長いトラバース道を通過、たくさんの柵を越え、九十九折の急登をがんばって歩く。

やっとこ さっとこ 乗越をクリア、岩頭滝見台に到着。
(ふへぇーっ )
)

流れ落ちる白い滝、水の流れが ひとちがを ホッとさせてくれた。
ホッとさせてくれた。
見上げれば 聖岳が大きく姿を見せてくれている

あ゛――――っ
長かったぁーーーーっ
ここまでは樹林帯と登りの連続だったから
ほとんど休憩することもなくここまできちゃったもんねぇー
実際・・・
ちがこさんは 登ることが必死で ほとんど地面しか見ていないのであ~る。
ってことは ポイントをよく覚えていないってこと!
これが後に大きな悲劇を生むことになろうとは 予想もしない ひとちが・・・
そこからは!
夏の花が咲き乱れる露地を通り、せせらぎを横切り・・・








わぁ~ぉ♪
トリカブトが満開じゃん!!



小屋までの花畑を ゴキゲンで歩く ひとちががいる
小屋に到着、時刻もまだ早いのに すでにテント場には カラフルなテントがひしめき合って並んでいる。
(お盆は混みあうんですな )
)
小屋の前にも 小屋泊の人たちか? なんでこんな山奥に こんなにたくさんの人がいるのかと思うほど・・・

さっそく手続きをしよう。
予約はいっぱいで ひとちがの今夜の宿泊は 山小屋の隣にある 冬季避難小屋。
(えっ )
)
通常なら6人のスペースを8人で使うとのこと。
混雑してるんだから仕方ないけど 山男に挟まれたら ちがこさんが可哀相と ひとしさんがお願いして 一番すみっちょにスペースをもらった。
(よかった よかった )
)
はい!
こんなんですよ!

5時、ちゃちゃっと食事を済ませ すでにシュラフに潜り込んで フガフガしている ひとちが。
フガフガしている ひとちが。
次々に到着し、賑やかになった小屋の中で じっとしている・・・
(あれ あれ・・・)
天気は怪しい。

予想は 台風一過で明日は 気持ちのよい稜線歩きを楽しむはずなのだが 外は霧、気温も高く雨をもっている。
(はぁぁぁーーーっ )
)
う~~~~ん
明日は あまり期待できそうにないぞぉー
ちょびっと ちがこさんはクジケ気味
天気もそうだけど 体調がやっぱしイマイチから脱出できない。
明日の長丁場の稜線歩きが不安であ~る。
(やっぱし・・・)
予約していた登山者も山の天気が荒れ模様のため キャンセルが続出、結局 窮屈な思いをすることなく 柱と ひとしさんに挟まれた ちがこさんは ぐっすり眠ることができたよ
ひとしさんは どうだったのかな?
「私は 交互に寝ていた隣のお兄さんに 何度も ボカッと蹴っ飛ばされて大変でしたぁー 」
」
と ブゥたれていたけどね!
ブゥたれていたけどね!
(ははははは。。。。)
真夜中、雨が強く降る音で目が覚めた。
『やっぱり予定変更しかないのかなぁー 』
』
早朝3時。
チチッ チチッ
小さな目覚ましの音が 静かな小屋に響いた。
がばっ!!
飛び起きたのは 目覚ましの持ち主だけじゃない!
( へっ?)
へっ?)
そう・・・
小屋の ほぼ全員が 暗闇の中、ヘッドランプを装着し ゴソゴソと荷物をまとめ始めた。
うっへぇーーーーっ!!
み、みなさん なんだか
やたら早くないですかぁー?
どうやら ひとちがが宿泊した小屋は ほとんどの人は素泊り、小屋の食事やお弁当ができるまでの時間を のんびり待つ人はいないらしい・・・
4時には ほとんどの人が 自分達の目的場所に向って旅立っていった。
(お見事!)
ちがこさん、体調は?
う~ん、やっぱしダメみたい
それでも ひとちがも暗闇の登山道を 聖岳に向けて出発
本日は 11時間は歩かなければ避難小屋までたどりつけないからね。

ところが・・・
天気がぁー、ガス
ヘッドランプの光は 反射して登山道が見えずらい。
必死で コースアウトしないように 目を凝らしてコースを探すのは 先頭の ちがこさんだ。
ようやくヘッドランプがいらなくなり夜が白々と明けた始めたころ 森林限界を抜け山の斜面をカッパを着て登る ひとちががいた。
(よくやります・・・)

おえぇぇぇーーっ
時々 吐き気を催す ちがこさん
「大丈夫? 無理しない方がいいんじゃないかな・・・」
心配する ひとしさん。
「うん、大丈夫 大丈夫!」
ちがこさんは それでも進むつもりであ~る。
(無理しないほうが いいんじゃないの?)
なんとか小聖岳に到着

危ないガレ場のヤセ尾根にさしかかった。

風が強くガスは 霧状になり目の中に飛び込んでくる。
大きなザックは 風にふられて よろけまくる ちがこさん

ひょぇぇぇーーーっ
こ、コワイじゃん!!

低姿勢になって進むしかない

 おや?
おや?
岩場に座っている若いご夫婦が・・・
「この天気ですから 私は帰る気マンマンなんですが 妻が進むっていうんですよ。」
笑いながら余裕たっぷりの すらりとした山男のご主人。
どうやら進む方向は ひとちがと同じらしい。
「では 山頂でお会いしましょう 」
」
山頂まで無事たどりつけるかどうかわからないのに この若いご夫婦は その先を進むかどうか モメてるっていうんだからスゴイ!
と、とりあえず ひとちがも がんばれる所までいくつもりだけど
益々風は強くなった。
景色どころか 吹き荒れる風と霧で 足元を見るのが背いっぱい。
ともかく 風で吹き飛ばされないように 慎重に進む。
(がんばれぇー )
)

「ひとしさぁ~ん、明日も天気が大荒れだっていうし、今日非難小屋までは この風じゃ歩ききれないよ、ザックをデポしてとりあえず山頂までがんばろう・・・」
ヤセ尾根のハイマツの間にザックを捨てて 身ひとつで山頂に向かう。
更に風が強くなった。
砂礫の大斜面の急登は 荒れ狂った状態であ~る。
(きゃぁーーーーっ )
)
ひとちが ぴーーーんち!

う、動けない・・・
限界かぁー?
「どうする?」
ひとしさんが じっと ちがこさんを見る。
山頂まではあと30分足らず。
いつもなら 「進む!」と間違いなく答えるであろう ちがこさんだが今回は違った。
「このまま進んでも 危ないし、体調不良を考えれば やっぱり下山した方がいいよね 」
」
残念だけど仕方ない・・・
下山開始。
10分も下っただろうか?

先ほどのご夫婦とすれ違った。
そして更に下る。
(後味が悪い、、、)
げっ!
たくさん登ってくるじゃん!
この悪天候の中をものともせず カラフルなカッパを着た登山者が列をなして斜面を登ってきた。

ひとちが顔を見合わせる・・・
や、やっぱり登りますかぁー
半分クジケていたのに なんだか元気がでてきたぞぉー

ひとちがも負けちゃおれん
くるりとUターン
山頂目指してゴー
再び風と戦いながら山頂までどうにか登りきった。
やったぁーっ!!

ガスガスの山頂、天気がよければ最高の展望であろう。
が 本日は山頂標識のポールに必死で風と戦いながら しがみついているのが精々であ~る
先ほどのご夫婦とも合流、記念撮影♪
奥さんは 元ワンダーフォーゲルのバリバリの山女であった・・・
どうりで この天気でもへっちゃらなわけだ。
(うはははは!)

がんばったね、ひとちが・・・
こんな天気でも ちゃんと山頂まで登れたじゃん♪
(うん、うん )
)
いつの間にか ちがこさんの体調も回復方向に向っている。
下山開始、ひとしさんのデポした 黄色いザックカバーがガスの中に ぼんやりと浮かび上がって見えた。

早朝に暗くて見ることのできなかった小屋の近くのお花畑





山小屋に到着。

いつもじゃ フツウに下山して終わるのが ひとちがの山行であ~る。
ところが、ここからが問題だった
予定では 赤石岳の避難小屋に宿泊し、椹島ロッジに下る予定だったから 東海フォレストのバスに乗る予定が 井川の観光協会のバスに乗るしかない。
なのにバスの時間は調べていなかったのであ~る。
山小屋でバスの時間を聞いた。
「すみません、聖登山口から観光協会のバスに乗りたいんですけど 最終バスの時刻は何時ですか?」
「最終は12時ジャストです。慣れた人なら間に合うかもしれません、しかし それは天気がよくて登山道が危なくない状態であればですね・・・フツウの人は無理かなぁ、でも今すぐ出発すれば もしかすると間に合うかも・・・」
えええええええーーーーっ!
タイムリミットは 昼12時ジャスト。
登山口の下山ルートの山行タイムは平均4時間45分。
現在の時刻は9時10分、たった2時間50分しかないのであ~る。
「2時間も山行タイムを縮めることなんて できるわけないじゃん 」
」
 しかぁ~し、観光協会のバスに乗り遅れるってことは次の選択をしなければいけないってことだ。
しかぁ~し、観光協会のバスに乗り遅れるってことは次の選択をしなければいけないってことだ。
1、 聖登山口まで下山したら 椹島ロッジまで40分かけて歩き椹島ロッジに宿泊、翌日東海フォレストのバスに乗る。
2、 聖登山口から 畑薙の駐車場まで5時間かけて歩く。
3、 乗れないなら このままもう一泊 聖平小屋に宿泊して翌日観光協会のバスに乗る。
究極の三択であ~る。
さぁ、どうする ひとちが?
そして・・・
ひとちがの無謀なる挑戦が今始まった
無理を承知で観光協会のバスに乗ろう
最終バスに間に合うことができるか ひとちが
お腹がすいた・・・
パンをちぎって 口に詰め込む、水を飲むゆとりもない。
山小屋を飛び出した!
ともかく 走る!
走る!
 走るしかないのであ~る。
走るしかないのであ~る。
本来なら・・・
登りでコースを楽しむことができなかった ちがこさんは のんびり花を眺めたり写真を撮ったりと下っていきたかった。
(ふぇぇ~ん )
)
でも 今回は違うのだぁー!!
後方で ひとしさんが叫ぶ!
「ほれほれ 走って! 間に合わないよぉー
走って! 間に合わないよぉー 」
」
危ない斜面でズルズル滑り、気の根っこでけっつまずいて何度 ちがこさんは転びそうになったことか・・・
それでも 走り続ける・・・
走り続ける・・・
丁度 南アルプスを縦走して抜けていく トレランの大会が催されていた。
まるで ひとちがも選手のひとりのようだ。
ただ彼らと違うのは でっかい重たいザックを背負っていることと、ちがこさんが 走っているという割に 他から見ると
走っているという割に 他から見ると 走ってるんじゃなくて 歩いているようにしか見えないこと
走ってるんじゃなくて 歩いているようにしか見えないこと
(あちゃ )
)
でも 本人は必死。
下りで こんなに ゼエ ゼエ
ゼエ 言いながら喉をカレ枯れにして下るってのは 初めての経験であ~る。
言いながら喉をカレ枯れにして下るってのは 初めての経験であ~る。
登りの際にコースをきちんと見ていないので ポイントごとに何分かかるのかさえわからい・・・
だだ ひとしさんの 「もっと早く 走って
走って 」という言葉を聞きながら ひたすら下り続けるのみ!
」という言葉を聞きながら ひたすら下り続けるのみ!
横っ腹が痛い
給食を食べたてで 走るマラソンの授業のような。
でも休むわけにはいかない!
時間は待ってはくれないのだから・・・
(そう そう )
)
ようやく 長い九十九折の急坂を下り 吊橋を渡った。
そこから先は更にコースの記憶が不明瞭、いったい登山口まで何分でたどり着けるんだろう?
地図を確認する余裕なんてない
後方の ひとしさんは半分すでに諦めていた・・・
『このペースじゃ 無理だろうな 』
』
トラバースの道に入った。
意外アップダウンがある 長いコース。
下りですでに膝が ガクガクな ちがこさん、しかぁ~し、登りは順調。
(よっしゃ )
)
はぁ はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ
はぁ
ゼェ ゼェ
ゼェ ゼェ
ゼェ ゼェ
ゼェ ゼェ
ゼェ ・・・
・・・
ものすごい勢いで坂を登る。
そしてとうとう出会所小屋跡にぃー
ひとしさんが 時計を見た。
「残りあと15分です 」
」
登山口に停車しているバスのエンジン音が聞こえる・・・
ここからは 最後の激しい下りだ。
膝が弱っている ちがこさんには限界は近い
「ひとしさん、先に行って! なんとか間に合ったらバスにお願いして5分だけ待ってもらって! ちがこさんの足じゃ絶対間に合わないから・・・」
風のように ひとしさんは 走った
走った
『足の指の先が痛い、ええい! どうにでもなれ!』
もう ちがこさんだけじゃなくて ひとしさんだって限界だったのであ~る
足を引きずるようにして 最後の力をふりしぼって下る ちがこさん
エンジン音は まだちゃんと聞こえている・・・
『早く下らなくっちゃ! ひとしさん、間に合ったかな?』
時計を持たない ちがこさんには時間がわからないのであ~る。
あっ!
み、見えた!!
バス停に バスが停車、10名ほどの人が 林を見上げるようにして じっとこちらを見ていた。
(ちがこさん びっくり )
)
はぁ はぁ
はぁ はぁ
はぁ ・・・
・・・
声が聞こえた。
「急がなくていいよぉー! ゆっくり下って 」
」
涙がでてきた
まるで小学校のマラソン大会にビリでゴールした子供と同じ。
待っていてくれた人たちが拍手で迎えてくれた。
時刻は12時2分。
たった2分の遅刻だったけど ひとしさんが先に到着できていなかったら バスには乗ることができなかったもんねぇ・・・
これが 一度も休むことなく走り続けた ひとちがの結果であ~る
ひとしさんも笑っている。
「私は11時55分に到着できたんですよ、皆さん 私がまだ連れが下ってくるって言ったら信じてくれなくてね、その辺に隠れてるんじゃないのなんて・・・」
待っていてくださった井川観光協会の運転手さん、そして乗客の皆さん、本当にありがとうございました。

疲れきった体でバスの一番後の席に乗車、一緒に乗り合わせた 台風の中、お山を徘徊していたという東京の渡辺さんと 楽しく話をしながら畑薙の駐車場まで戻ることができた ひとちがであ~る
(よかった よかった )
)

林道を トレランの選手が走っている・・・
疲れきってヘロヘロだ。
それでも彼らは走り続けるのだ。
そう・・・
ゴールまで
がんばれぇーっ!!!
バスの中から大きく手を振って応援する。
目的が違っても 最後まで諦めないで がんばり抜くこと・・
体の限界への挑戦って なかなかできることじゃない!
今年の夏休みも 素晴しい経験と 素晴しい人たちに巡り会うことができたね ひとちが。
大・大・大満足の南アルプス山行でした
聖岳
南アルプス
全山行 193回
百名山 38座
標高 聖岳 3013m
天気

 ガス
ガス山行時間 28時間10分
距離 33.10km
〈コース〉13日・自宅(2:30)-畑薙第一ダム・夏季臨時駐車場(6:45/バス)-聖登山口(7:45)-造林小屋跡(10:20-10:30)-聖平小屋(2:10)
14日・聖平小屋(4:10)-山頂(7:10-7:20)-聖平小屋(9:10)-登山口(?)
タイムリミットは 昼12時ジャスト。
登山口の下山ルートの山行タイムは平均4時間45分。
現在の時刻は9時10分、たった2時間50分しかないのであ~る。
「2時間も山行タイムを縮めることなんて できるわけないじゃん!」
そして・・・
ひとちがの無謀なる挑戦が今始まった・・・・
最終バスに間に合うことができるか ひとちが!!
駐車場までの車でのアクセスは長く、クネクネと曲がる山間の道路は体調不良の ちがこさんには最悪の状況。
(ふぇぇぇ~ん
 )
)車がカーブで揺れるたび 気持ちが悪く本日の山行の行く先は雲行きが怪しい

「ちがこさん、大丈夫?」
ようやく夏休みに入ったばかりの ひとしさんとしては楽しく車中を いつもじゃぁ ひとりしゃべりまくっている ちがこさんが無言で大人しいのは不安で仕方ないのであ~る

「うん・・・ 大丈夫だよぉ
 」
」答える ちがこさんも大丈夫という割には力もなくクジケ気味だ。
せっかく計画していた山行が おじゃんになるのは忍びなく、気合だけで今回の山行を続けることを決意していた。
(本当に大丈夫なわけ?)
ようやく畑薙ダム臨時駐車場に到着、去年は手前にあったゲートは取り除かれ 時間を気にすることもなく早めに車を駐車できたのは予想外、すでにたくさんの車が駐車されている駐車場に ひとちがも乗り込む!
(よっしゃ
 )
)〈今回の山行予定〉
初日:聖登山口→聖平小屋
2日目:聖岳→兎岳→中盛丸山→大沢岳→赤石岳非難小屋
3日目:赤石岳→椹島ロッジ
初日の聖平小屋までは6時間であ~る。
バスを降りた たくさんの登山者と共に いよいよスタート

(うりゃ
 )
)2日目に宿泊予定の 赤石岳非難小屋はテントを張ることができない、ってことは 3000円のバス代をチャラにするためにも小屋泊しなければいけない現状があるわけで・・・
(うはははは。)
ザックの中身は 食料と着替え、いつもより少なめの水と前回の甲斐駒山行より やや軽めであ~る

ところが・・・
楽しいはずの登り、ちがこさんの体調はやっぱりすぐれない

いつも元気な ちがこさん!
どうしちゃったの?
歩けど 歩けど 一向に回復しない体調と闘う ちがこさん。
周りをキョロキョロする気力もなく 必死で登る。
が・・・
はぁ
 はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ
はぁ ・・・・
・・・・息が荒く余裕がない。
「大丈夫?」
後方を歩く ひとしさんも心配を隠せない

吊橋の横で たくさんの登山者が休憩中。
しかぁ~し、ひとちがは進む!
混雑がキライな ひとしさんと 少しでも早く山小屋に到着したい 体調不良の ちがこさんとしては休んでいる暇はないのであ~る。
長いトラバース道を通過、たくさんの柵を越え、九十九折の急登をがんばって歩く。
やっとこ さっとこ 乗越をクリア、岩頭滝見台に到着。
(ふへぇーっ
 )
)流れ落ちる白い滝、水の流れが ひとちがを
 ホッとさせてくれた。
ホッとさせてくれた。見上げれば 聖岳が大きく姿を見せてくれている

あ゛――――っ
長かったぁーーーーっ
ここまでは樹林帯と登りの連続だったから

ほとんど休憩することもなくここまできちゃったもんねぇー

実際・・・
ちがこさんは 登ることが必死で ほとんど地面しか見ていないのであ~る。
ってことは ポイントをよく覚えていないってこと!
これが後に大きな悲劇を生むことになろうとは 予想もしない ひとちが・・・
そこからは!
夏の花が咲き乱れる露地を通り、せせらぎを横切り・・・
わぁ~ぉ♪
トリカブトが満開じゃん!!
小屋までの花畑を ゴキゲンで歩く ひとちががいる

小屋に到着、時刻もまだ早いのに すでにテント場には カラフルなテントがひしめき合って並んでいる。
(お盆は混みあうんですな
 )
)小屋の前にも 小屋泊の人たちか? なんでこんな山奥に こんなにたくさんの人がいるのかと思うほど・・・
さっそく手続きをしよう。
予約はいっぱいで ひとちがの今夜の宿泊は 山小屋の隣にある 冬季避難小屋。
(えっ
 )
)通常なら6人のスペースを8人で使うとのこと。
混雑してるんだから仕方ないけど 山男に挟まれたら ちがこさんが可哀相と ひとしさんがお願いして 一番すみっちょにスペースをもらった。
(よかった よかった
 )
)はい!
こんなんですよ!
5時、ちゃちゃっと食事を済ませ すでにシュラフに潜り込んで
 フガフガしている ひとちが。
フガフガしている ひとちが。次々に到着し、賑やかになった小屋の中で じっとしている・・・
(あれ あれ・・・)
天気は怪しい。
予想は 台風一過で明日は 気持ちのよい稜線歩きを楽しむはずなのだが 外は霧、気温も高く雨をもっている。
(はぁぁぁーーーっ
 )
)う~~~~ん
明日は あまり期待できそうにないぞぉー

ちょびっと ちがこさんはクジケ気味

天気もそうだけど 体調がやっぱしイマイチから脱出できない。
明日の長丁場の稜線歩きが不安であ~る。
(やっぱし・・・)
予約していた登山者も山の天気が荒れ模様のため キャンセルが続出、結局 窮屈な思いをすることなく 柱と ひとしさんに挟まれた ちがこさんは ぐっすり眠ることができたよ

ひとしさんは どうだったのかな?
「私は 交互に寝ていた隣のお兄さんに 何度も ボカッと蹴っ飛ばされて大変でしたぁー
 」
」と
 ブゥたれていたけどね!
ブゥたれていたけどね!(ははははは。。。。)
真夜中、雨が強く降る音で目が覚めた。
『やっぱり予定変更しかないのかなぁー
 』
』早朝3時。
チチッ チチッ
小さな目覚ましの音が 静かな小屋に響いた。
がばっ!!
飛び起きたのは 目覚ましの持ち主だけじゃない!
(
 へっ?)
へっ?)そう・・・
小屋の ほぼ全員が 暗闇の中、ヘッドランプを装着し ゴソゴソと荷物をまとめ始めた。
うっへぇーーーーっ!!
み、みなさん なんだか
やたら早くないですかぁー?
どうやら ひとちがが宿泊した小屋は ほとんどの人は素泊り、小屋の食事やお弁当ができるまでの時間を のんびり待つ人はいないらしい・・・
4時には ほとんどの人が 自分達の目的場所に向って旅立っていった。
(お見事!)
ちがこさん、体調は?
う~ん、やっぱしダメみたい

それでも ひとちがも暗闇の登山道を 聖岳に向けて出発

本日は 11時間は歩かなければ避難小屋までたどりつけないからね。
ところが・・・
天気がぁー、ガス

ヘッドランプの光は 反射して登山道が見えずらい。
必死で コースアウトしないように 目を凝らしてコースを探すのは 先頭の ちがこさんだ。
ようやくヘッドランプがいらなくなり夜が白々と明けた始めたころ 森林限界を抜け山の斜面をカッパを着て登る ひとちががいた。
(よくやります・・・)
おえぇぇぇーーっ
時々 吐き気を催す ちがこさん

「大丈夫? 無理しない方がいいんじゃないかな・・・」
心配する ひとしさん。
「うん、大丈夫 大丈夫!」
ちがこさんは それでも進むつもりであ~る。
(無理しないほうが いいんじゃないの?)
なんとか小聖岳に到着

危ないガレ場のヤセ尾根にさしかかった。
風が強くガスは 霧状になり目の中に飛び込んでくる。
大きなザックは 風にふられて よろけまくる ちがこさん

ひょぇぇぇーーーっ
こ、コワイじゃん!!
低姿勢になって進むしかない

 おや?
おや?岩場に座っている若いご夫婦が・・・
「この天気ですから 私は帰る気マンマンなんですが 妻が進むっていうんですよ。」
笑いながら余裕たっぷりの すらりとした山男のご主人。
どうやら進む方向は ひとちがと同じらしい。
「では 山頂でお会いしましょう
 」
」山頂まで無事たどりつけるかどうかわからないのに この若いご夫婦は その先を進むかどうか モメてるっていうんだからスゴイ!
と、とりあえず ひとちがも がんばれる所までいくつもりだけど

益々風は強くなった。
景色どころか 吹き荒れる風と霧で 足元を見るのが背いっぱい。
ともかく 風で吹き飛ばされないように 慎重に進む。
(がんばれぇー
 )
)「ひとしさぁ~ん、明日も天気が大荒れだっていうし、今日非難小屋までは この風じゃ歩ききれないよ、ザックをデポしてとりあえず山頂までがんばろう・・・」
ヤセ尾根のハイマツの間にザックを捨てて 身ひとつで山頂に向かう。
更に風が強くなった。
砂礫の大斜面の急登は 荒れ狂った状態であ~る。
(きゃぁーーーーっ
 )
)ひとちが ぴーーーんち!
う、動けない・・・
限界かぁー?
「どうする?」
ひとしさんが じっと ちがこさんを見る。
山頂まではあと30分足らず。
いつもなら 「進む!」と間違いなく答えるであろう ちがこさんだが今回は違った。
「このまま進んでも 危ないし、体調不良を考えれば やっぱり下山した方がいいよね
 」
」残念だけど仕方ない・・・
下山開始。
10分も下っただろうか?
先ほどのご夫婦とすれ違った。
そして更に下る。
(後味が悪い、、、)
げっ!
たくさん登ってくるじゃん!
この悪天候の中をものともせず カラフルなカッパを着た登山者が列をなして斜面を登ってきた。
ひとちが顔を見合わせる・・・
や、やっぱり登りますかぁー

半分クジケていたのに なんだか元気がでてきたぞぉー


ひとちがも負けちゃおれん

くるりとUターン

山頂目指してゴー

再び風と戦いながら山頂までどうにか登りきった。
やったぁーっ!!
ガスガスの山頂、天気がよければ最高の展望であろう。
が 本日は山頂標識のポールに必死で風と戦いながら しがみついているのが精々であ~る

先ほどのご夫婦とも合流、記念撮影♪
奥さんは 元ワンダーフォーゲルのバリバリの山女であった・・・
どうりで この天気でもへっちゃらなわけだ。
(うはははは!)
がんばったね、ひとちが・・・
こんな天気でも ちゃんと山頂まで登れたじゃん♪
(うん、うん
 )
)いつの間にか ちがこさんの体調も回復方向に向っている。
下山開始、ひとしさんのデポした 黄色いザックカバーがガスの中に ぼんやりと浮かび上がって見えた。
早朝に暗くて見ることのできなかった小屋の近くのお花畑

山小屋に到着。
いつもじゃ フツウに下山して終わるのが ひとちがの山行であ~る。
ところが、ここからが問題だった

予定では 赤石岳の避難小屋に宿泊し、椹島ロッジに下る予定だったから 東海フォレストのバスに乗る予定が 井川の観光協会のバスに乗るしかない。
なのにバスの時間は調べていなかったのであ~る。
山小屋でバスの時間を聞いた。
「すみません、聖登山口から観光協会のバスに乗りたいんですけど 最終バスの時刻は何時ですか?」
「最終は12時ジャストです。慣れた人なら間に合うかもしれません、しかし それは天気がよくて登山道が危なくない状態であればですね・・・フツウの人は無理かなぁ、でも今すぐ出発すれば もしかすると間に合うかも・・・」
えええええええーーーーっ!
タイムリミットは 昼12時ジャスト。
登山口の下山ルートの山行タイムは平均4時間45分。
現在の時刻は9時10分、たった2時間50分しかないのであ~る。
「2時間も山行タイムを縮めることなんて できるわけないじゃん
 」
」 しかぁ~し、観光協会のバスに乗り遅れるってことは次の選択をしなければいけないってことだ。
しかぁ~し、観光協会のバスに乗り遅れるってことは次の選択をしなければいけないってことだ。1、 聖登山口まで下山したら 椹島ロッジまで40分かけて歩き椹島ロッジに宿泊、翌日東海フォレストのバスに乗る。
2、 聖登山口から 畑薙の駐車場まで5時間かけて歩く。
3、 乗れないなら このままもう一泊 聖平小屋に宿泊して翌日観光協会のバスに乗る。
究極の三択であ~る。
さぁ、どうする ひとちが?
そして・・・
ひとちがの無謀なる挑戦が今始まった

無理を承知で観光協会のバスに乗ろう

最終バスに間に合うことができるか ひとちが

お腹がすいた・・・

パンをちぎって 口に詰め込む、水を飲むゆとりもない。
山小屋を飛び出した!
ともかく
 走る!
走る!  走るしかないのであ~る。
走るしかないのであ~る。本来なら・・・
登りでコースを楽しむことができなかった ちがこさんは のんびり花を眺めたり写真を撮ったりと下っていきたかった。
(ふぇぇ~ん
 )
)でも 今回は違うのだぁー!!
後方で ひとしさんが叫ぶ!
「ほれほれ
 走って! 間に合わないよぉー
走って! 間に合わないよぉー 」
」危ない斜面でズルズル滑り、気の根っこでけっつまずいて何度 ちがこさんは転びそうになったことか・・・
それでも
 走り続ける・・・
走り続ける・・・丁度 南アルプスを縦走して抜けていく トレランの大会が催されていた。
まるで ひとちがも選手のひとりのようだ。
ただ彼らと違うのは でっかい重たいザックを背負っていることと、ちがこさんが
 走っているという割に 他から見ると
走っているという割に 他から見ると 走ってるんじゃなくて 歩いているようにしか見えないこと
走ってるんじゃなくて 歩いているようにしか見えないこと
(あちゃ
 )
)でも 本人は必死。
下りで こんなに ゼエ
 ゼエ
ゼエ 言いながら喉をカレ枯れにして下るってのは 初めての経験であ~る。
言いながら喉をカレ枯れにして下るってのは 初めての経験であ~る。登りの際にコースをきちんと見ていないので ポイントごとに何分かかるのかさえわからい・・・
だだ ひとしさんの 「もっと早く
 走って
走って 」という言葉を聞きながら ひたすら下り続けるのみ!
」という言葉を聞きながら ひたすら下り続けるのみ!横っ腹が痛い

給食を食べたてで 走るマラソンの授業のような。
でも休むわけにはいかない!
時間は待ってはくれないのだから・・・
(そう そう
 )
)ようやく 長い九十九折の急坂を下り 吊橋を渡った。
そこから先は更にコースの記憶が不明瞭、いったい登山口まで何分でたどり着けるんだろう?
地図を確認する余裕なんてない

後方の ひとしさんは半分すでに諦めていた・・・
『このペースじゃ 無理だろうな
 』
』トラバースの道に入った。
意外アップダウンがある 長いコース。
下りですでに膝が ガクガクな ちがこさん、しかぁ~し、登りは順調。
(よっしゃ
 )
)はぁ
 はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ
はぁ はぁ
はぁ
ゼェ
 ゼェ
ゼェ ゼェ
ゼェ ゼェ
ゼェ ゼェ
ゼェ ・・・
・・・ものすごい勢いで坂を登る。
そしてとうとう出会所小屋跡にぃー

ひとしさんが 時計を見た。
「残りあと15分です
 」
」登山口に停車しているバスのエンジン音が聞こえる・・・
ここからは 最後の激しい下りだ。
膝が弱っている ちがこさんには限界は近い

「ひとしさん、先に行って! なんとか間に合ったらバスにお願いして5分だけ待ってもらって! ちがこさんの足じゃ絶対間に合わないから・・・」
風のように ひとしさんは
 走った
走った
『足の指の先が痛い、ええい! どうにでもなれ!』
もう ちがこさんだけじゃなくて ひとしさんだって限界だったのであ~る

足を引きずるようにして 最後の力をふりしぼって下る ちがこさん

エンジン音は まだちゃんと聞こえている・・・
『早く下らなくっちゃ! ひとしさん、間に合ったかな?』
時計を持たない ちがこさんには時間がわからないのであ~る。
あっ!
み、見えた!!
バス停に バスが停車、10名ほどの人が 林を見上げるようにして じっとこちらを見ていた。
(ちがこさん びっくり
 )
)はぁ
 はぁ
はぁ はぁ
はぁ ・・・
・・・声が聞こえた。
「急がなくていいよぉー! ゆっくり下って
 」
」涙がでてきた

まるで小学校のマラソン大会にビリでゴールした子供と同じ。
待っていてくれた人たちが拍手で迎えてくれた。
時刻は12時2分。
たった2分の遅刻だったけど ひとしさんが先に到着できていなかったら バスには乗ることができなかったもんねぇ・・・
これが 一度も休むことなく走り続けた ひとちがの結果であ~る

ひとしさんも笑っている。
「私は11時55分に到着できたんですよ、皆さん 私がまだ連れが下ってくるって言ったら信じてくれなくてね、その辺に隠れてるんじゃないのなんて・・・」
待っていてくださった井川観光協会の運転手さん、そして乗客の皆さん、本当にありがとうございました。
疲れきった体でバスの一番後の席に乗車、一緒に乗り合わせた 台風の中、お山を徘徊していたという東京の渡辺さんと 楽しく話をしながら畑薙の駐車場まで戻ることができた ひとちがであ~る

(よかった よかった
 )
)林道を トレランの選手が走っている・・・
疲れきってヘロヘロだ。
それでも彼らは走り続けるのだ。
そう・・・
ゴールまで

がんばれぇーっ!!!
バスの中から大きく手を振って応援する。
目的が違っても 最後まで諦めないで がんばり抜くこと・・
体の限界への挑戦って なかなかできることじゃない!
今年の夏休みも 素晴しい経験と 素晴しい人たちに巡り会うことができたね ひとちが。
大・大・大満足の南アルプス山行でした









